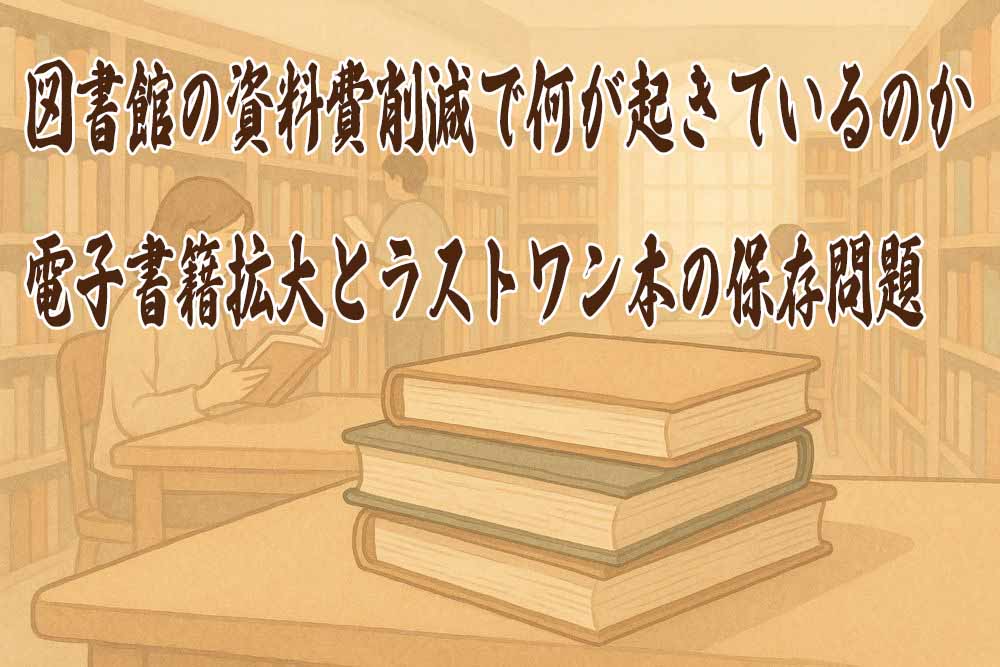 DALL-Eで作成
DALL-Eで作成
全国の公共図書館で、紙の書籍をめぐる環境が静かに変質している。資料費の縮小により新刊購入は細り、書庫は飽和し、地域に1冊しか残らない“ラストワン本”まで廃棄の危険にさらされる。一方で電子書籍の利用は拡大し、読書の重心はデジタルへ移りつつある。しかし、紙の本を求める利用者の声は根強く、図書館が果たすべき役割を問い直す動きも出ている。紙と電子の狭間で揺れる日本の読書環境とその課題を追った。
紙の本離れと電子書籍拡大が加速 図書館予算削減で進む“知の格差”とは
全国の公共図書館が直面する“静かな危機”は、紙の本を取り巻く社会全体の変化とも深く結びついている。図書館が購入する新刊は20年で3割減り、資料費も縮小。書庫が飽和し、廃棄数だけが増えていく現状は、日本の読書環境そのもののゆらぎを象徴している。
その背景には、電子書籍の普及、財政圧縮、情報環境の変化が複雑に重なっている。紙・電子どちらか一方ではなく、生活者の声に寄り添って状況を見つめる必要がある。
紙の書籍離れと電子書籍拡大:生活者の選択が示すもの
出版科学研究所の統計では、紙の書籍・雑誌の販売金額は20年で約4割減少している。一方で、電子書籍市場は拡大を続けており、読書の主軸をスマートフォンやタブレットに置く層が増えている。
電子書籍は
保管スペース不要
通勤のスキマ時間に便利
価格やセールが安定
などの理由から若年層・ビジネス層を中心に支持を広げている。
しかし、こうした変化の陰で、紙の本を好む層の声が置き去りにされつつある。
紙の本を支持する人たちの「図書館への切実な思い」
電子書籍の普及が進む中でも、紙の本を重んじる利用者は多い。図書館で聞かれる声は次のようなものだ。
「紙の質感に安心感がある。図書館で本を選ぶ行為そのものが楽しみだ」
「専門書や歴史資料は紙で読むべきだと思う。地域の記録は紙で残してほしい」
「子どもには紙の絵本を手にしてほしい。ページをめくる体験は学びにつながる」
岐阜県郡上市で新聞・雑誌購入が止まった際にも、利用者からは
「図書館で日々の情報に触れられるのが大事なのに」
という戸惑いが相次いだ。紙の本を好む人ほど、図書館を“地域の文化と情報の拠点”として捉え、縮小に強い危機感を抱いている。
図書館利用者が語る“居場所としての価値”
貸出冊数が長期的に減少する一方、図書館を「安心して過ごせる居場所」として利用する動きは広がっている。
利用者からは次のような声が寄せられる。
「静かに過ごせる場所として貴重。紙の本が減ると選ぶ楽しみが奪われる」
「最終的な情報確認は紙の資料の方が信用できる」
「電子が苦手なので、紙を減らされると生活情報が追えなくなる」
特に高齢者、子ども連れ、デジタルに不慣れな層にとって、紙の本が減ることは“情報アクセスの後退”につながる。
書庫の飽和と「ラストワン」の危機
令和5年度の除籍(廃棄)は1100万冊。25年前の1.5倍に増えた。
書庫が限界を迎えるなか、地域で1冊しか残っていない“ラストワン本”が廃棄される可能性も高まっている。
多摩地域では、岐阜県のIT企業が開発した「TAMALAS」というシステムを用い、
所蔵が2冊以下の本は可能な限り残すルールを導入している。
東村山市立図書館の新倉館長は、
「古くなったから捨てるのではなく、職員の主観に頼らず客観的データで資料を残す仕組みが必要」
と話す(NHK報道による)。
古書・小部数出版が増えつつある昨今、“ラストワン本”の保存は、未来への文化継承という視点でも重要性を増している。
全国の図書館利用傾向:変化する役割と揺らぐ情報基盤
全国的に図書館の利用状況を見ると、貸出冊数は減りつつも「滞在型施設」としての利用が増えている。
一方で、図書館で働く専任司書は減少し、非常勤・委託職員が8割に達している(日本図書館協会による)。
選書の精度や資料のチェック機能が弱まり、誤情報を含む本の所蔵問題も課題として浮上している。
長野県塩尻市立図書館が抱える葛藤はその典型例で、
多様な意見を尊重しつつも信頼性をどう担保するか
という難題に直面している。
電子と紙の“二極化”のなかで失われつつあるもの
電子書籍の利用が増えることは悪いことではない。しかし、公共図書館が紙の資料を十分に揃えられなくなれば、地域ごとに読書体験の質は大きく分かれる。
紙を重視する人にとっては「選択肢の減少」
電子ユーザーにとっては「信頼性の確認手段の喪失」
ともなり、図書館の存在意義はどちらの層にとっても軽くはない。
図書館は、紙・電子の“両立”を社会にもたらす最後の公共機能である。
その基盤が揺らぐいまこそ、図書館の価値を地域社会全体で再考すべき時期に来ている。
