2025年11月17日 22時30分
動画

最近の映画がどこか偽物っぽく感じられる、という不満は珍しい意見ではありません。そして、それはデジタル撮影やカラーグレーディング、照明、CGのせいだという意見もよくみられます。この問題について、映画批評を行うYouTubeチャンネル・Like Stories of Oldを運営するトム・ヴァン・デル・リンデン氏が1つの見解をムービーで示しています。
Why Movies Just Don’t Feel “Real” Anymore – YouTube

リンデン氏は、最近の映画がリアルさに欠けているように思うのは、デジタル撮影やCG技術が確かに関係しているものの、それだけでは映画がなぜリアルに感じられなくなるのかという本質を説明できない、と述べています。

映画がリアルに「感じられる」ことは、映画が現実そのものだという意味ではありません。観客である私たちは映画が作り物であることを当然理解しています。それでも、たとえ劇中に恐竜や宇宙人が登場しても、観客はその世界を知覚的に本物として受け取ることができます。映画が現実のように思えるのは、私たちが現実を構築するのと同じ知覚の仕組みを刺激するからです。

映画研究者のスティーブン・プリンス氏は「知覚的にリアルな映像とは、観客が三次元空間をどのように知覚し処理しているか、その構造に対応する映像である」と述べています。光や色、質感、動き、音といった手がかりが階層的に配置され、私たちの現実の理解に一致しているとき、たとえ映像が実在を写していなくても知覚的リアリズムが成立するというわけです。つまり、映像がその世界を私たちが普段と同じように知覚していると錯覚させるからリアルに感じるというわけです。
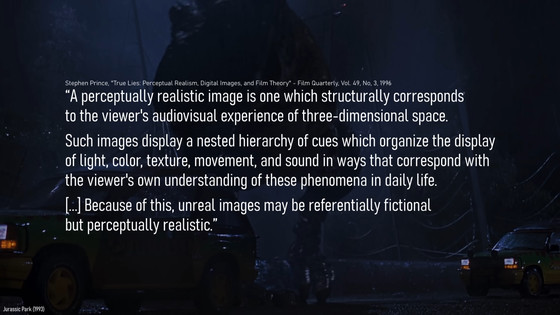
リンデン氏は昔の映画を見返す中で、被写界深度を深くして画面の大部分にピントを合わせて撮っている場面が多いということに気付いたと述べています。昔の映画では、人物から距離を取って周囲の環境を広く写し込むショットが多く、背景の質感や遠くの顔まで読み取れる映像が数多くあります。こうした映像は、観客にその場の空間的広がりを感じさせ、実際にその場に立っているような三次元的感覚をもたらします。

映画研究者のノエル・キャロル氏は、被写界深度を深く取った構図は「映画館の外で私たちが世界を知覚する方法に近く、よりリアルに感じられる」と述べています。これは画面の中にある情報の内容そのものより、観客がどう映像と関わるかという形そのものを重視した考え方です。そのため、この議論はフィルム撮影かデジタル撮影かという古い対立とは別である、とリンデン氏。
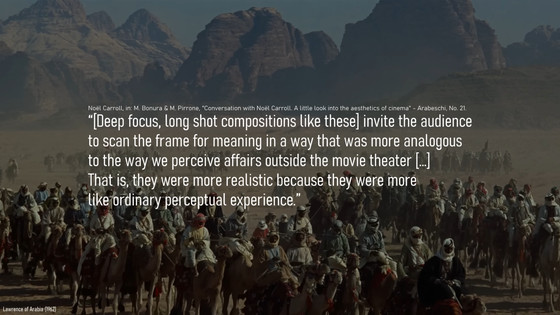
実際にデジタルで撮られた『レヴェナント:蘇えりし者』や『名もなき生涯』のような作品には、古典映画にも匹敵するほど豊かで没入的な映像があります。古い映画の見た目を模倣しているわけではなく、映像の形式そのものが知覚的リアルさを生んでいます。

もちろん、現実のロケーションや手作りのセットがリアリティに寄与することも事実。グリーンバックに頼った映像より、実物の風景や物質感のある場所で撮る方が「世界が生きている」という感覚が強まります。しかし、リンデン氏は「結局のところ、その映画が観客とどれだけ『触覚的な関係』を築けるかという形式の問題だ」と述べています。

リンデン氏は、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』で水の民の村に着く場面を例に挙げ、「画面のどこを見ても情報があり、人物と環境が無理なく一体化していることが分かります」と評価しています。画面の隅々を自由にスキャンし、気づかない細部まで知覚の端で捉えることで世界に厚みが生まれ、観客はリアルだと感じます。

一方、『アントマン&ワスプ クアントマニア』では、多くの背景がぼやけて画面に厚みがなく、中距離のショットばかりなので環境との統合が弱く、三次元的な実在感を欠いている、とリンデン氏。

本来、浅い被写界深度とクローズアップは強い効果を持つ手法ですが、何も考えずに乱用すると逆に平板化を招きます。『アントマン&ワスプ クアントマニア』は決して特殊な例ではなく、多くの現代映画で「浅い被写界深度+中寄りショット」が標準化しているとリンデン氏は指摘しています。

また、実際のスタントを用いたにもかかわらず、VFX処理によってその迫力が失われてしまう例として、劇場版『アサシンクリード』の「イーグルダイブ」シーンが挙げられました。この作品では38mの高さから命綱なしで落下するスタントが宣伝でアピールされました。

しかし、劇中では現実の肉体の動きがCGの煙や色調の処理に埋もれてしまい、観客の知覚はそれを「本物」と認識できなくなっています。つまり問題の本質は、映画がどのように観客の知覚と関わるべきかという本質への理解が希薄になっていることにあるとリンデン氏は指摘しました。

ここで現代映画におけるもう一つの問題が浮かび上がります。それは「ポストプロダクション前提の撮影」です。撮影時に最適な画作りを追求するのではなく、「後で変えられるから」と平板で退屈な映像のまま撮る傾向が一般化しているとリンデン氏は主張しています。

ポストプロダクション前提の撮影がリアルさを損なう理由の一つとして、リンデン氏は「インデックス(指標)」という概念を紹介しています。フィルムの映像は「実際の光が直接フィルムに焼き付いた」という物理的因果関係があり、そのため実在感が強いとされてきました。しかしデジタル映像は光をデータとして変換するため「物理的な因果の痕跡」が薄いとされます。とはいえ、観客の知覚においては必ずしもフィルムだからリアルに感じ、デジタルだから偽物に感じるわけではありません。重要なのは映像そのものが「物質的に感じられるかどうか」であり、デジタルでもそれが可能な作品はあります。

この議論を踏まえると、重要なのは撮影方法の物理性ではなく、映像の中に「触れられそうな物質性」があるかどうかだ、とリンデン氏。ここから映画のリアリティをより深く理解するため、映画研究者のローラ・U・マークス氏が提唱した「触覚的視覚性」という概念に話が移ります。
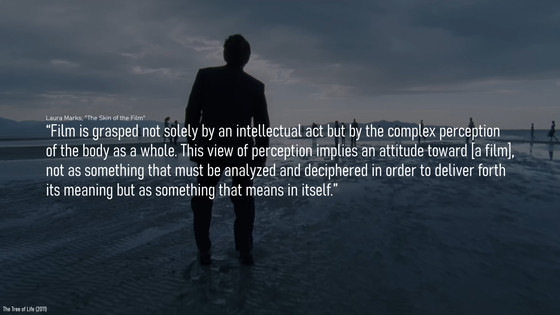
マークス氏は、「映画は視覚と聴覚だけではなく、触覚や身体感覚にも作用する」と述べ、目が触れる感覚を持つかのように映像を知覚する「触覚的視覚性」を提唱しました。これは奥行きを把握する通常の視覚とは異なり、質感や表面の手触りを感じ取るような視覚です。
例えば、フォーカスの浅さや極端なクローズアップ、細部の質感の強調が、観客に「触れている」ような感覚を与えます。深いフォーカスと環境描写が豊かな映像では、三次元性と触覚性が互いを高め合い、観客は風、草、水、岩の質感を想像し、そこに「触れている」ように感じます。

火、風、雨、水といった自然の要素は、とりわけ強い身体的反応を呼び起こし、観客にその環境の物理的存在感を直接感じさせます。触覚は人間が最初に発達させる感覚であり、世界を理解して他者と結びつくための根源的な手段だからこそ、映像が触覚的に感じられるかどうかは没入感に直結します。触覚的な映像は、観客と映画の間に双方向的な関係を生み出します。

ここまでの議論は「触覚的質感」という一側面にすぎません。映画はさらに、感情、記憶、夢、恐怖、身体反応など、より抽象的で主観的なリアリティをも扱うことができ、ショットの連なりによってそれを築き上げていきます。幼少期の記憶や恐怖、孤独感など、人間の内面に深く関わるリアリティは、空間、質感、音、光の重層的な構築の上に成り立ちます。

例えば、登場人物の顔の汚れや汗によるてかりなどは、そのキャラクターの質感だけでなく、キャラクターの性格や内面を観客が把握するのに役立っています。

リンデン氏は、映画のリアルさは一つのショットだけで成立するものではなく、ショットの積み重ね、質感や空間の連続性、音響や美術などのあらゆる要素が有機的に作用し合うことで生まれる、その総体が観客を物語世界へと運び、何か「本当に体験したかのような感覚」を生み出すのだと主張しています。

そして、最終的に求めているのは、観客が何か意味あるものを見たり、触れたり、経験したと感じたりするような深い没入体験です。映画の制作意図や美学、見せ方の全てがこの目的に向けてどれだけ意識的に設計されるかが、作品のリアリティを決定づけるとリンデン氏は論じました。

この記事のタイトルとURLをコピーする






