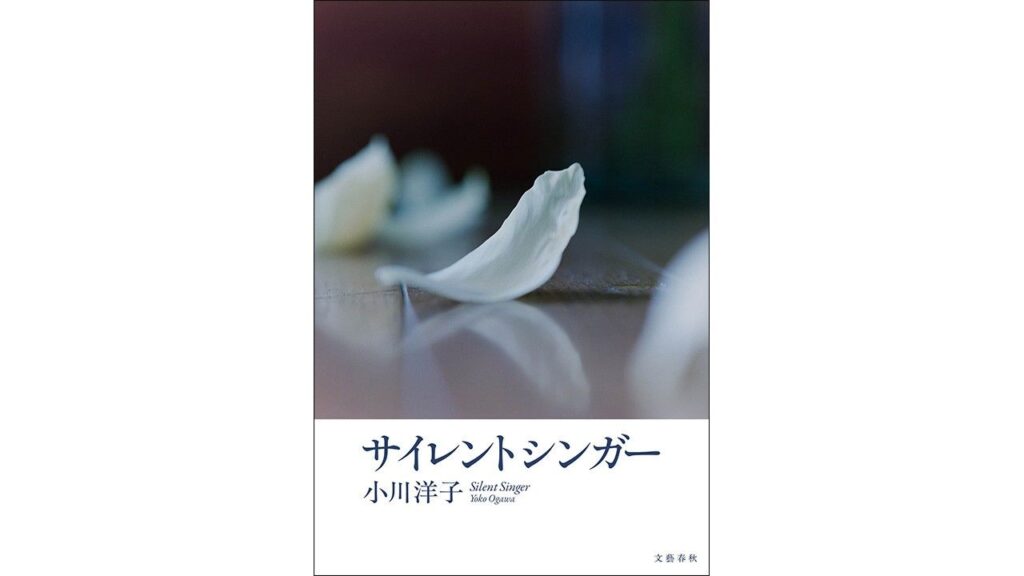まさに小川洋子らしい不思議な世界を紡いだ寓話である。主人公の「リリカ」は、決して人前では歌わないが、その声を聴く者に、いつしか心の平穏をもたらしている。物語は、著者が創造した独特で閉鎖的な空間に暮らすリリカの生き方を描いたものだ。そこから何を読み取るか。
「内気な人」ばかりの「アカシアの野辺」
毎日、夕方の5時になると町役場から放送される『家路』が流れてくる。歌っているのは「リリカ」である。まだ少女の頃に、請われて録音されたものだったが、誰も彼女の声とは気づかない。
山の中腹にポツンとある、深い森に囲まれた元別荘地に「アカシアの野辺」と名付けられた共同体がある。住人は「内気な人」ばかりで、人と交わることを避け、周囲を金網で囲って敷地内を開墾し、動物を飼い、ひっそりと自給自足の生活を送っていた。
「魂を慰めるのは沈黙である」という会則らしきものがある。彼らは静寂に最もなじむとされる黒い服を着て、独自に編み出した「指言葉」という指の仕草で意思疎通する。それも生活に必要な最低限の言葉しかない。
「森に吹く風」のような歌声
主人公の「リリカ」は、祖母と共同体の近くで暮らしていた。祖母は門番小屋の雑用係として雇われ、下界の人たちに野辺で生産される農作物や自家製のお菓子、放牧場の羊から刈った上質な毛糸を売っていた。
リリカは赤ん坊の頃から野辺の人々にかわいがられて育ってきた。祖母が働いている間は、老介護人が面倒を見て、子守歌がわりに『家路』を聞かせた。長じて、彼女には人や動物を和ませる不思議な歌声が備わっていた。まるで「森に吹く風」のようだった。
祖母とリリカは、迷子になって行方不明になったままの男の子を慰めるために、端材を集めて人形を作り、湧き水の池のほとりに飾っていた。その数が増えた頃、祖母が亡くなり、彼女は仕事を引き継ぐ傍ら、時に外から歌の仕事も頼まれる。それはおもちゃの人形が歌う音声の吹き替えやCMソングなど、決して人前で歌うものではなかったが、静かに人々の心に響く声だった。森の中で彼女は、死んでいった羊たちや迷子になった子供のために歌う。
血縁に頼らないコミュニティに憧れ
リリカは、仕事で外出する以外は、野辺の人々と同化した暮らしぶりである。クルマを運転して出かける彼女が、唯一、外の世界の人で心を寄せたのが道路の料金所で働く青年だった。
この静謐(せいひつ)な世界でリリカがどう成長していくのか、外の世界とどう関わって生きていくのか、それが読みどころであるが、『サイレントシンガー』は著者の生い立ちや人生観がこれまでになく色濃く反映された作品である。小川洋子自身の言葉が、物語を読み解くヒントになるので紹介しておきたい。
彼女は「子供の頃は金光教の教会の離れに住んでいました」と語っている(月刊『新潮』2025年11月号「角田光代×小川洋子対談」より。以下同)。
「私の信仰体験は、神と自分の一対一の関係ではなく、教会で育ったというところにあるんです。教会には、社会的な肩書や人生観や価値観などを脱ぎ捨てた素の人間が大勢、老若男女を問わず集まってきて、そこで私は育ったわけですね。親がいない間、全く血の繋がりも何もないおばあちゃんと一緒におやつを食べたりして。そういう、血縁関係じゃない赤の他人のコミュニティに守られた記憶が、強くあるんです。そこで他者への信頼というものを得たんですよ」
「そうした経験が土台になっているものですから、私の小説には、よく知らない者同士が、一時期寄り集まってそこで絆を深めるという構成が出てきます。(略)『サイレントシンガー』では、言葉を手放した人たちが野辺と呼ばれる場所に集まって生活をする。そういう血縁に頼らないコミュニティの持つ役割に対する憧れがあるんです」
そうした体験が、「アカシアの野辺」の共同体につながっていく。
「彼女たちはあまりにセンシティブすぎて、下界では生きていけない人々なんです。この話の舞台である『野辺』は、そんな人たちが下界から離れるために山をどんどん登っていって、たどり着いた場所なんです」
「そもそも人間も社会も残酷じゃないですか。その残酷さとどう折り合いをつけるか、誰もがもがいています」と彼女は語る。本作は、繊細な糸で織りなしたように美しい言葉で綴られているが、ところどころに夢物語ではないチクリとした棘(とげ)がある。下界の人間が野辺の住人に投げかけた発言は侮蔑でしかない。青年との関係は深まるのか。リリカは幸せだったのか──。
「沈黙」の世界は心地よいだろうか。ふと、SNSの心ない言葉が溢れる喧噪の世の中を見まわした時、著者が問いかける声が深く心に刺さるだろう。
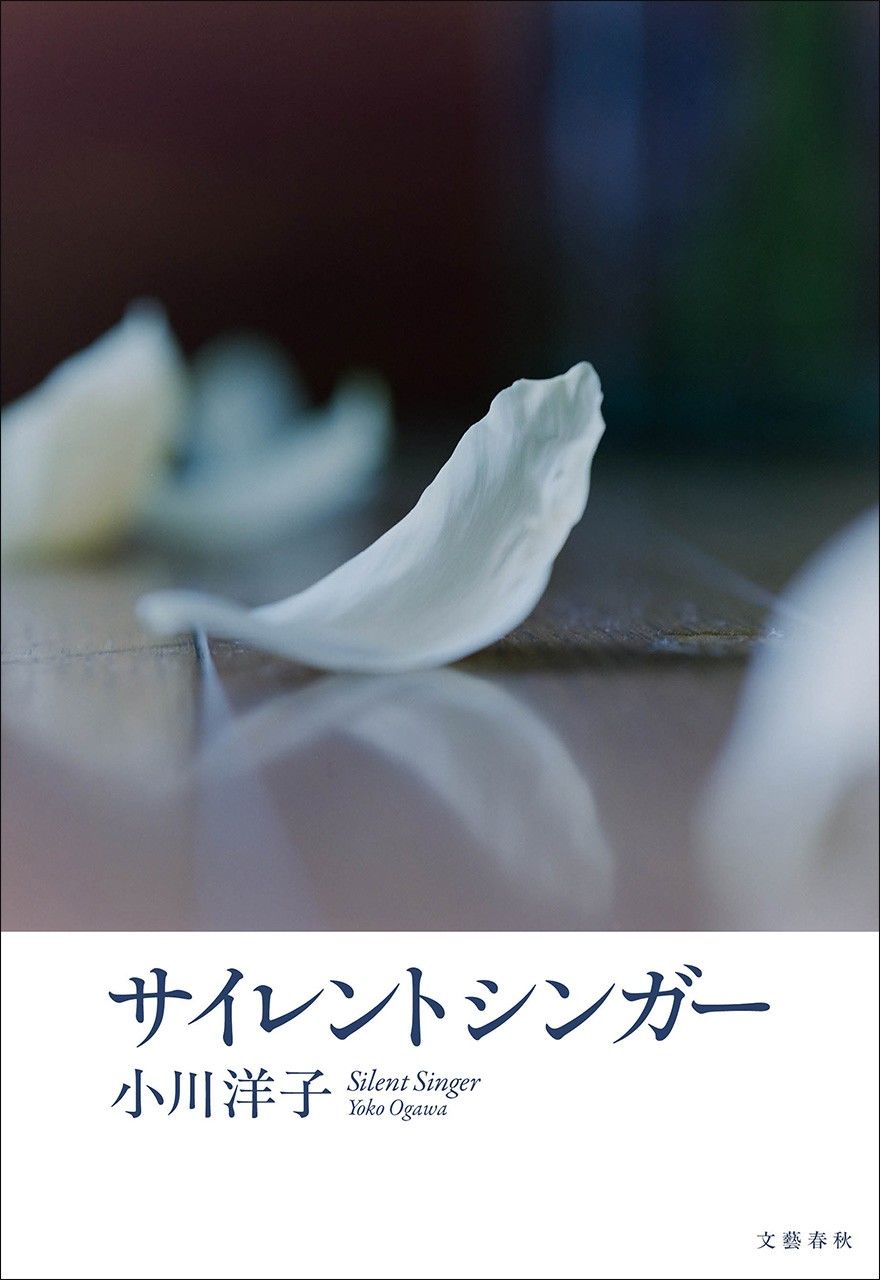
『サイレントシンガー』
文藝春秋
発行日:2025年6月30日
四六版:294ページ
価格:1980円(税込み)
ISBN:978-4-16-39199-1