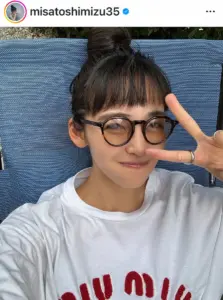——つげ義春作品のなかから、なぜ「海辺の叙景」と「ほんやら洞のべんさん」を選ばれたのか。また、映画内映画でその2篇をつなげるというアイディアはどこからきたのか教えてください。
三宅唱(以下、三宅)
つげ義春全集を読み、自分の好きな作品をリストにして眺めていたときに、「夏と冬を組み合わせたらどうなるんだろう?」という、シンプルな出発点でした。それぞれの季節にロケするのも楽しそうだし、と。企画を考えていたのはコロナ禍だったから余計に旅行したかったのかもしれない。
映画内映画の構造になったのは、当初「蒸発」も組み合わせて3部作にしようと考えていた名残りです。「蒸発」は劇中劇形式のマンガで、途中で江戸末期の井上井月という俳人の話になるんですね。夏と冬と、その時代劇の3部構成を考えていて、途中で「蒸発」をやらないという判断をしたけれど、劇中劇の構造が残りました。
主人公の設定がマンガ家のままでいいのかはだいぶ迷って、実はそのまま夏編の撮影に入ってしまったんだけど、初日に河合優実さんが車の後部座席で起き上がるファーストカットを撮って、「ああ、これは映画内映画にすべきものが撮れちゃったなあ」と。それで脚本家に変更する覚悟が決まった記憶があります。
——素朴な質問なのですが、ファーストシーンでシム・ウンギョンさん演じる主人公が書いている「海辺の叙景」の描写は、三宅監督が夏編を撮るときに脚本に書いた描写と同じなんですか?
三宅 たしかそうです。

© 2025『旅と日々』製作委員会
——面白いのは、「行き止まりに一台の車。後部座席で目を覚ます」と脚本には書かれていますが、映像では後部座席で目を覚ました河合優実さんを見せてから、そこが行き止まりだったことを明かす、というように順番が逆になっているところです。
三宅
「行き止まりに一台の車」というト書きをそのまま再現するようなショットからでももちろんはじめられる。一応撮って、編集でも試しましたが、やっぱり驚きに欠けるな、と。
ただ、「行き止まり」感は必要で、要するに物語をどう扱うか——物語との緊張関係をどう保ってショット連鎖を作っていくか、ということが僕の立場の仕事だと思うんです。撮影現場では、脚本では思いもよらなかったものがぐわっと立ち上がってくる。流れる雲が窓ガラスに反射していて、波の音が渦巻いていて——そういうものに心を奪われることが、映画をつくるときの驚きだし、喜びだと、今回改めて実感しました。
——原作「海辺の叙景」の磯浜での男女の邂逅は、その前に一度別のビーチで出会っているので再会に近いかたちですが、映画では初対面に変更されています。
三宅
原作の冒頭3コマ目に混雑したビーチが描かれているんだけど、実際にその大人数を撮るかどうかがまず問題だった。具体的には、肌を露出するエキストラを多数集められるか。現場の労働を想像すると、ちょっとしんどそうだなと。それに、そもそもそういう現場を回せる体制で撮る物語なのかどうか。撮影隊がビーチを占拠するのはナンセンスな気がしたし、少人数のスタッフ編成で撮りたいと思っていたので、じゃあ、混雑の描写に頼らずに青年のあの雰囲気を立ち上げるにはどうすればいいかな、と考えました。最終的には、高田万作さんのあの佇まいが説得力を持たせてくれた。大人数なんかやっぱり要らなくて、俳優はすごいなと思いました。
ただ、ビーチの人混みを前提としなくなったことで、出会いの偶然を作りづらくなってしまったので、脚本段階で、じゃあどこでどう出会えばいいのかを検討しました。
——初対面にすることに付随した変化のひとつとして、ふたりが出会うまでの道筋を立てることになりますよね。興味深いのは、マンガだとどちらかと言えば男性側に軸をおいて出会いが描写されていたように思えたのですが、映画だと女性側に出会いまでの理屈が用意されているところです。
三宅
景色や天気の変化、雰囲気をどう見せるかが、つげさんのマンガの映画化での重要なポイントだと考えていました。そこで、もともとこの島について少し知っている青年にキャメラがついていくよりも、はじめて訪れた女性とともに歩いたほうが見えてくるのでは、と。
ただ、男視点か女視点かというより、「私」か私じゃないか、正確に言えば、つげさんかそうじゃないか、ということを僕は考えていたんですよね。マンガでは、つげさんの私(わたくし)性が中心にあるけれど、映画にするとなると、どうしたってその私性からは遠ざかってしまう。つげさんの手が描くのとは違って、映画の場合は、男でも女でもないカメラというモノが見る世界だと思うんです。
——河合優実さんの、ふらふらとした歩き方が、磯浜まで彼女が辿り着くことの説得力を強めている気がしました。
三宅
その演出は悩みました。撮影前の顔合わせで、河合さんから「空っぽになりたいと思って旅にきた人なんじゃないか」と聞いたときに、すごい読解力だなと思い、キーワードになりました。でも「空っぽになりたいけれど、なれていない身体」って、何もしないというのも違うし、動きすぎるわけにもいかないし、かなり微妙な塩梅だから。
現場ではたくさん歩いてもらって、テイクによっていろいろと試しました。久々のデジタル撮影を活かして、カメラのかなり遠くの方から手前にアウトするまで長尺でとことん歩いてもらったり。そのやり方だと、撮影現場でOKの確信が持ちづらいときも正直あったんだけれど、編集室で、河合さんはちゃんとやってくれていた、と思いました。

© 2025『旅と日々』製作委員会
——磯浜でのふたりの出会いの場面は、かなりカットを割られていましたよね。
三宅
脚本を読みながら、ふたりはまだ同じフレームに収まらないんじゃないかと感じていました。どちらも、誰かと同一フレームには容易に入りたがらない人たちなのではないかと。撮影時にはツーショットでも通しの演技を撮りましたけど、まずは単独でそれぞれをしっかり見たい、という方針でした。
——あの場面は、ふたりの距離が縮まっていく場面として撮ったのでしょうか?
三宅
むしろ、いつ離れてもおかしくない関係だろうと思って撮っていました。「じゃあ」と不意に立ち去ってもおかしくない。お互い別に親しくなろうとはしていないのが、この関係だと思うんですよね。近づきすぎず、距離を保ちあっている。そして、相手がいてもいなくても変わらないような——互いが思い思いに過ごしているような時間が流れれば、このままふたりは一緒に行動するんじゃないか、と思っていました。
——一方で日が暮れる丘の場面は磯浜と違って、ふたりが同一フレームに収まり、かなりの長回しですよね。俳優たちにあまり動きもつけられないようなシチュエーションです。
三宅
あんなに人が動かない時間を長く撮ったのははじめてだと思います。撮影前夜に宿の広い部屋でテストをして、立ったり座ったりの動きや目線なんかを積み上げようとしたんだけど、しっくりこなかった。それに、刻一刻と陽が落ちる時間にカットを割ったら大変なことになるのに、結構複雑な動きになってしまい、これはやばいぞ、と。それで一旦ゼロに戻して、「動かないでそのままその場所で」と試してみたら、ふたりとも、セリフのトーンも間も、何もかもが変わりました。大事なのはふたりの間の距離だけで。夏編の撮影日数は9日間で、たしか5か6日目ですね。それまで共有した時間も重要だったと思います。もし初日とか序盤の撮影だったら、「声だけでいい」なんて表現は僕にはできなかった。
——場面を通してだんだん暗くなっていくことは想定されていたんですよね。
三宅
そういう時間帯に撮りたいと希望はしていたけれど、具体的にどう面白くなるかは見えていなかったです。前夜のテストを終えた後に、当日は夕方何時にテイク1に取り掛かれば、真っ暗になるまで何テイクいけそうか、各部と相談して、当日はまだ明るいうちにあの岬の展望台に行って、日没前後に向こうの集落に光も灯るはずだし、それを背にするのがきっと面白いよね、とカメラポジションを決定しました。
——次の日の場面は女性が泊まっている宿からはじめています。そのため磯浜までを描いたときと同様に、女性が青年の待つ浜辺に行くまでの道筋が見えてきますよね。なぜこの場面を追加したのですか?
三宅
みんな雨のせいで宿に閉じ込められている、という状況をしっかり明示してからのほうが、青年がひとりでポツンと小屋に座っている姿の味わいが引き立つんじゃないかなと考えました。まず部屋で退屈しのぎに将棋崩しをしている男らがいて、次に、その部屋に入らない河合さんのあの姿が見えて。そういう順番で、青年にじわじわ近づいていくのが映画としては面白いだろうという考えです。
——「海辺の叙景」の最後のコマとほとんど同じ構図のショットが夏編にはありますが、それよりも後に河合さんを寄りで映したショットが置かれています。そこでの河合さんの言い表しようもない、あの凄まじい表情はどのように引き出されたものなのでしょうか?
三宅
あのショットを撮るときに、こういう顔をしてくださいと指示したわけではないです。ただ、島に着いた日から雑談で、お互いに自分の体で感じていること——風の感触とか、海の暗さとかを、「あれ見て」「あっちもすごい」と言葉で共有していました。特に、崖ですね。撮影前に幸田文の『崩れ』を副読本的に読んでもらっていたんだけど、あの浜辺の崩れを雨の日に海のなかから見ていると、「世界の終わりだな」みたいな気分になってゾクゾクするんだよね。それで撮影最終日には、もうとくに何も言わずとも、河合さんは周囲の環境をそのまま受け止め、そのまま反射してくれるような、そういう状態にあったんじゃないかなと思います。クロースアップは、目の前にカメラやスタッフがいる状況で俳優にとって負荷がかかるわけだけど、テイク1で、はいおしまい、という感じでした。
——マンガと同じように女性が青年の泳ぐ海を眺めているバックショットで終えるという選択肢もあり得たと思いますが、なぜ映画では河合さんの顔で終えたのですか?
三宅
河合さんのあの顔が映っていたから、というのがシンプルな答えですが、ああいった顔の微細な変化を途切れなく描写するというのは、マンガではなかなか描けないものなのではないかと思うんです。フレーム外の感覚も紙とスクリーンじゃ違うし。逆に、原作のバックショットはマンガだからこそ味わえる体験で、ページを開いてワッと広がるというあの迫力は、映画ではどうしたって弱まってしまう。じゃあどうすればいいか。たぶん顔だな、というのは事前になんとなく考えていました。
あと、いったん映画を見るシム・ウンギョンさんを映したあとに河合さんへもう一度戻すことで、「彼女がスクリーンのなかに取り残されたような印象」になるんじゃないかと。河合さんの表情を映したあのカットは本当に完成した映画に使われていたのか。実はあの手前で映画が終わっていて、会場にいた学生たちの誰もあれを見ていないんじゃないか。
編集の大川景子さんと、使われなかった撮影素材は、いわばこの世に生まれることのできなかったようなもので、供養した方がいいのかもね、と冗談半分で話していたことがあるんです。あのマンガには妙な気配があって、映画ではあの河合さんの顔を通して、そういう気配がこの映画に立ち上がれば、と思っていました。
——青年が海で泳ぐカットから、それを上映されている映画として見ている主人公に移りますが、あのタイミングというのは編集の段階で見つけたのですか?
三宅
そうです。あれこれかなり大川さんと試して、あそこがベストだと思いました。
続き