スマホを通じて詐欺犯罪被害に遭う人、また犯罪に闇バイトに関わってしまう人もいます。自分の家族は大丈夫でしょうか。「まさか」「自分には関係ない」と思っている人ほど危ないのが現実です。詐欺犯罪から家族を守るために知っておきたいことについて、『家族みんなが楽になる!親にスマホをもっと使ってもらう本』(日経BP)著者の増田由紀さんと『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』(講談社+α新書)著者の高橋暁子さんという、「家族のスマホ」のスペシャリストのお二人に語っていただきました。

増田由紀(ますだ・ゆき)さん:左
2000年から千葉県浦安市でシニアのためのスマホ・パソコン教室を運営、2020年より完全オンライン教室に移行。「“知る”を楽しむ」をコンセプトに、これまで1万5000人を超えるシニア世代に、スマホの魅力と使い方を指導。シニア世代でも分かりやすいスマホの解説には定評があり、自治体や企業主催のセミナーで講師を務めるほか、新聞や雑誌でも活躍中。著書に『世界一簡単!70歳からのスマホの使いこなし術』(アスコム)、『いちばんやさしい 70代からのiPhone』(日経BP)などがある。
高橋暁子(たかはし・あきこ)さん:右
ITジャーナリスト。成蹊大学客員教授。SNSや情報リテラシー教育が専門。スマホやインターネット関連の事件やトラブル、ICT教育事情に詳しい。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、企業などのコンサルタント、講演、セミナー、講義、委員などを手がける。『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』(講談社+α新書)、『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『スマホで受験に失敗する子どもたち』(星海社新書)など著作は20冊以上。元小学校教員であり、高校生の母でもある。
年齢に関係なく、詐欺にひっかかってしまう人の共通点
前回
は、スマホをなかなか使いたくないシニア、逆に使いすぎてしまう子ども世代に親世代がどう向き合うかについてお話しいただきました。今回は「スマホ犯罪やネット犯罪からどう家族を守るのか」ということをお聞きしたいです。
増田由紀(以下、増田) 詐欺にもいろいろなパターンがありますが、シニアといえば「オレオレ詐欺」は今もありますね。これだけニュースで報道されていても、いろいろな偶然が重なると「この電話は本当なのかも」と思ってしまうのです。
つい最近でも私の教室の生徒さんがひっかかってしまったのは「息子が困っている」というストーリーです。シニアは大人ですから、子どもと違ってお金を持っています。家族のために、息子のためにと自ら進んでお金を払ってしまいがちです。生徒さんには「お金の話が出たらまず疑って」「お金と個人情報は、相手に教える前にいったん立ち止まって、家族に相談してほしい」とお願いしています。
私の講座でも詐欺対策はとても関心が高いのですが、次から次へと新しい手法が出てくるので、個別論では対応しきれません。ですので「私は大丈夫と思わずに、詐欺のニュースは自分にも関係あるかも、という気持ちで聞いてほしい」とお願いしています。常に詐欺の情報に注意を払うことで「これはおかしいのかも?」と気付きやすくなります。「自分は関係ない」と情報を遠ざけている人ほど、ひっかかりやすいのかなと思います。

「お金と個人情報は、相手に教える前にいったん立ち止まって、家族に相談して」と増田由紀さん
画像のクリックで拡大表示
高橋暁子(以下、高橋) 私も普段から、「とにかくニュースを見てほしい」と言っています。詐欺には流行があるので、常にアンテナを張ってニュースを見たり読んだりしていれば、詐欺だと気付ける可能性が高まります。新型の詐欺第一号に自分が当たるなんていうことは、そうそうありません。ほとんどの人は「そんなことも知らなかったの」と責められるような、何度も報道されている手口にひっかかっているんです。新聞やテレビでは、毎日のように報道があり、私もその解説で毎日のように発信を行っています。
増田 スマホを使っていると、おかしな広告やフィッシング詐欺にも出会いますよね。『
家族みんなが楽になる!親にスマホをもっと使ってもらう本
』でも触れていますが、生徒さんにはまず「お金や銀行のことを言ってくるもの」は疑ってかかること。それから「自分がしたいわけではないのに、横入りしてくるオファー(おすすめ)などはすべて無視してほしい」とお伝えしています。

『家族みんなが楽になる!親にスマホをもっと使ってもらう本』(増田由紀著、日経BP)/画像クリックでAmazonリンクへ
高橋 ですが、シニアはまだしも、若い世代はまったくと言っていいほどニュースを見ません。大学生にアンケートを取ると、情報ソースの第1位がInstagram、2位がテレビ、その次はYouTube、X、TikTokときて、新聞系はほぼゼロです。ニュースと名の付くものでは、LINEニュースとYahoo!ニュースだと言いますが、これは自分が気になったタイトルを見に行くだけなので、実質芸能ニュースを見ているだけなんです。ですから、情報が必要な相手に行き渡っていないんです。それが根本的な問題です。
ありとあらゆるメディアで何度も警告していても、本人に届かなくて、また同じパターンでだまされているんですね。とにかく毎日ニュースが出ていますから、少しでも関心を持って見てほしいです。
例えば、警視庁が9月に出した「注意喚起・お知らせ」では、警察を装う「ニセ警察」詐欺や、YouTubeから接触する「投資名目」詐欺の被害が増加していると警告されています。これらの情報は把握できていますか? 「今」起きている詐欺を、家族で誰も知らないのはかなり危険な状態です。
ニュースを読まない若者は「コスパがいい獲物」
詐欺は他人事だと思っている人、ニュースを見ない人は、年齢にかかわらず詐欺に遭いやすいということですね。それをジュニア世代、シニア世代に効果的に伝えるいい方法はありますか?
高橋 自分が「ニュース係」になることです。ニュースでトレンドを知って、何か事件があったら、ぜひ家族のLINEグループで定期的に情報をシェアしてください。
増田 家族のLINEグループに流すなら、シニアも子どもも両方に注意喚起できるのでいいですね。
高橋 「いちいち送らなくていいよ」と言われても、それで何百万円、何千万円というお金を失わずに済むなら安いものですよね。赤の他人から言われるよりも、肉親から直接言われたほうが、まだ少しは耳に入ってきます。毎回熱心に読まれなくても「あ、なんか娘が言っていたかな」くらいにはなるのではないでしょうか。特に大切なことは、直接会ったときに対面で伝えてあげるとなお伝わりやすいですね。
子ども世代の詐欺被害も増えていますよね。
高橋 詐欺被害については「若者は貧乏だからだまされない」ということはなくて、数十万円とか数万円程度のお金しか取れなくても、ニュースを読まない若者はだましやすいので、犯罪者にとって「コスパがいい獲物」なんです。特に成人になったばかりの18〜20歳といった年齢の子たちはだましやすく、かつ消費者金融でローンも組めます。それで借金させられてしまうといったパターンが多いです。
続きを読む 1/2
「SNSで知り合った人に会いたい」と言われたら親はどう答えるべき?
「SNSで知り合った人に会いたい」と言われたら親はどう答えるべき?
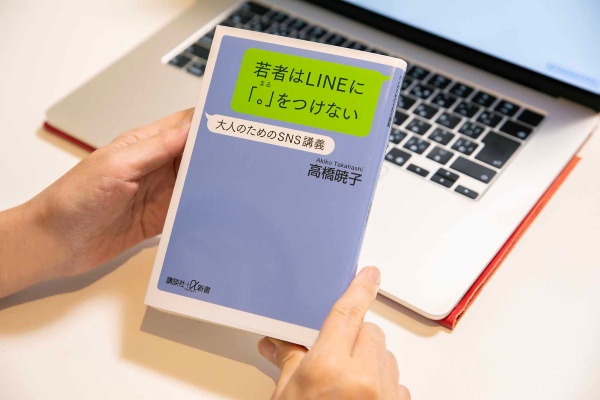
『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』(高橋暁子著、講談社+α新書)/画像クリックでAmazonリンクへ
高橋 子どもの場合は、犯罪に巻き込まれたり、性的な搾取をされたりする心配もあります。絶対やってはいけないこととしては、まず個人情報を出さない、本名を使わない、SNSも顔は出さない。そして裸の写真は、信頼できる人であっても絶対に送ってはダメで、これは一生インターネット上に残り、自分がゆくゆく苦しむということを、反面教師の事例も含め、最初に教えてあげてほしいです。
それから「ネットで知り合った人と勝手に会わない」ことも大切です。ただ、今はそれもある程度は仕方がないんですよ。ある調査で渋谷で女子高生に聞いたら、100%が「ネットで知り合った人と会ったことがある」と答える時代ですから。ゲームは課金したくなるようにできているし、YouTuberには投げ銭したくなるようにできています。ネットで気の合う人には、会いたくなるようになっているものなんです。
そこは絶対に禁止ということではないんですね。
高橋 禁止にしても、子どもはかいくぐる方法はいくらでも知っているので、隠れて会ってしまいます。それよりは、しっかり子どもと話し合いながら決めていくほうがいいですね。
会うにしても、安全なやり方があります。いつどこで誰と会うか親に告げてから行く。夜ではなく日中に、こちらが指定した場所、公共の場所か人が多い場所で会う。会う前に親がビデオ通話で相手の身元を確認するなどし、送り迎えもさせてもらう。できれば一人ではなく友達と一緒に行く。こうした注意をしておけば、犯罪に巻き込まれたり、いきなり殺されたりといったことにはなりづらいとは思います。
そこまでしっかり手順を教えながら危険を回避する理由を教えてあげると「あ、そんな怖いこともあるんだ、なら親の言う通りにしようかな」という感じになりますね。
そのバイト本当に大丈夫? 闇バイトの見分け方
闇バイトもSNSやネットで募集しています。普通のバイトとの見分け方はありますか。
高橋 SNSでバイトを探したほうが、履歴書を書いて送ったりする必要がないので「コスパがいい」と考えている子が多いようです。でも実際に本当にちゃんとした会社なのか自分で調べる手間を考えたら「専門の大手サイトのほうがずっとコスパがいい」ということを親からも教えてあげてほしいです。
今は中高生でも闇バイトに関わってしまう子が増えています。もしも子どもが、お小遣いが足りなくなって「やべ、金欠でバイトしなくちゃ」なんて言っていたら、すぐにでも「あなた、闇バイトしてない? こういう募集は危ないわよ」と見分け方や危険性について教えてあげてください。高校生まで、遅くとも大学生になるまでには、闇バイトや詐欺などについてしっかり教えてあげられると、ひっかかる可能性も低くなるのかなと思います。
増田 詐欺や犯罪の場合、シニア世代も闇バイトの逮捕者が出ていますが、「ちょっとお金が欲しい」という気持ちだけで相手の話に乗ってしまうのは、待ってほしいですね。やはり相手に言われたまま「ネットで見た」というだけで信用せずに、自分で検索してみる、そこがどんな会社なのかを調べるという姿勢はどんなことにおいても大切で、それがネットリテラシーですよね。デマが広がるのも、言われたままを信じてしまうから。「本当なのかな?」と疑う気持ち、それが、子どもであっても大人であっても、いろんな犯罪から身を守ることになると思います。
高橋 もしお金を支払ってしまうと、相手は身元が特定できないように不正に入手したスマホ等を使って詐欺を行うため、そのお金はほぼ100%戻ってきません。消費生活センターに相談窓口がありますが、お金を取られた後だと、取り戻す方法がないんです。ただ、振り込む前ならば「詐欺ですよ」と教えてあげられると言います。見分けられないなど心配なときは、被害に遭う前に相談してみてください。

「親が詐欺の被害に遭っても、感情的に怒らないで」(増田さん)
画像のクリックで拡大表示
増田 詐欺犯罪に遭うと、まず精神的なショックが大きいですが、遭った後の処理も大変です。口座やクレジットカードは使えなくなると、すべて発行し直しの手続きになります。シニアの場合自分だけではできず、家族の付き添いも必要になりますし、周囲も本当にクタクタになります。
それだけでなく、驚いたお子さんから「何でこんなのにだまされたの!」と感情的に怒られることもあり、それが精神的にかなりのダメージになるそうです。そういう方は「怒られるから、子どもには聞けない」とおっしゃいます。
この種の詐欺被害は、家族にひとこと相談してくれれば防ぐことができたかもしれません。そういう意味で、何より「気軽に相談しやすい環境をつくってあげる」ことです。もしも詐欺に遭われたという方がいれば、怒らないで「お母さん、お父さんの身が無事で安心したよ」と声をかけてあげることで、親御さんも救われ、癒やされるのではないでしょうか。
「相談しやすい環境づくり」はシニアでも子どもでも共通ですね。そのために、中間世代である私たちの役割が重要なのだということをあらためて感じました。
取材・文/宮崎綾子 構成/西 倫英(第二編集部)、市川史樹(日経BOOKプラス編集) 写真/小野さやか

