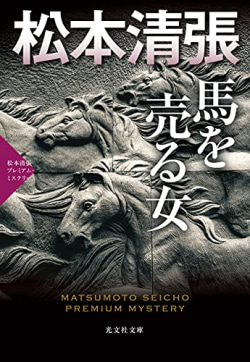名著には、印象的な一節がある。
そんな一節をテーマにあわせて書評家が紹介する『週刊新潮』の名物連載、「読書会の付箋(ふせん)」。
今回のテーマは「毒薬」です。選ばれた名著は…?
***
ミステリに毒薬はつきもの。無論、殺人に使う。
アガサ・クリスティの場合、全長篇六十六冊中三十四冊が毒殺だという(数藤康雄編『アガサ・クリスティー百科事典』ハヤカワ文庫)。
これは女史が第一次世界大戦のとき薬局で薬剤師の助手の仕事をしていて毒薬に詳しくなったためらしい。
ミステリと毒薬は相性がいい。わが松本清張には変わった毒薬(毒草といったほうがいいか)を使った殺人を描く短篇ミステリ「駆ける男」(短篇集『馬を売る女』所収)がある。
六十二歳の実業家が、三十六歳の妻と瀬戸内海の景勝地にある老舗旅館に泊る。
年齢が離れているのは実業家が妻を亡くし後妻をもらったため。彼は心臓が弱いという欠陥がある。
旅館に泊った夫婦は旅館と長い渡り廊下でつながっている海に面した料亭へ食事に行く。
食事中、実業家は突然、狂ったようになって渡り廊下を駆けあがり出す。心臓の弱い身。たちまち発作を起して死んでしまう。医者は心臓麻痺と診断する。
それにしても夫はなぜ突然、走り出したのか。疑問に思った刑事が調べると、夫婦の部屋にある球根がころがっていたのを知る。
見なれぬ球根だが検査するとハシリドコロという植物だと分かる。
「この根を食べると中枢神経がたちまち冒され、無茶苦茶に走り出す」という症状が出る。犯人はどうもこれを使ったらしい。
こんな毒草を知っていたとは犯人の知識は凄い。
![]()
2025年10月30日 掲載
※この記事の内容は掲載当時のものです
![]()