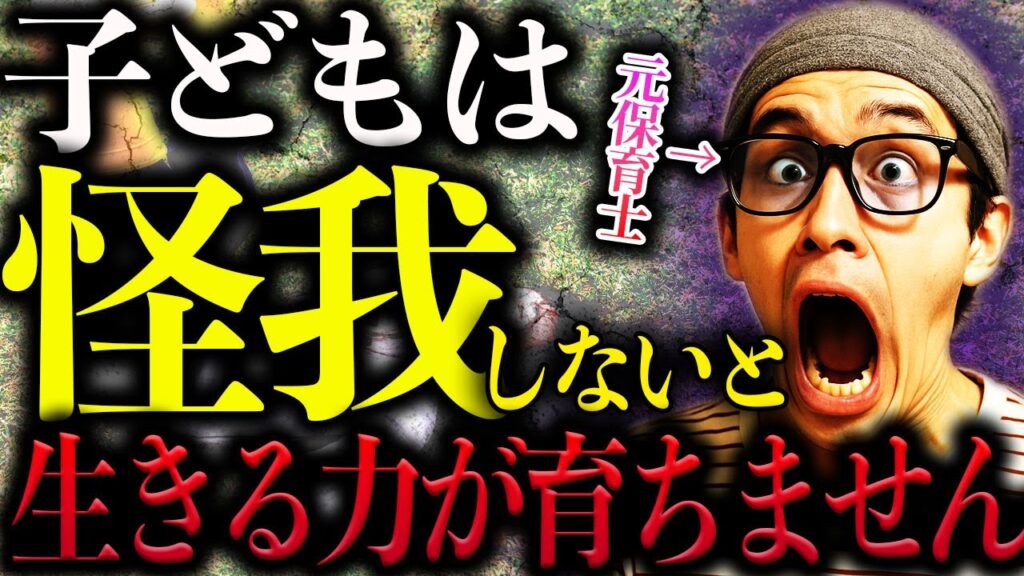【見逃さないで】小さな怪我は成長のサイン!元保育士いけちゃんが語る子どもの生きる力を育むための魔法の声かけ
毎度あけみおばちゃんです。今日のテーマはなんやのイけちゃん。 はい、どうも皆さんこんにちは。え、今日扱うのは子育ての永遠のテーマ。子供の生きる力を育むに庭にというテーマでお話ししていきたいと思います。 生きる力か。なんか体操な話やね。うちの子朝なかなか起きへんねんけどそれも生きる力がないってことなん? [音楽] はい。そうですね。ま、それも無関係じゃないかもしれないですけども。ま、じゃあこの具体的に生きる力って何なのか。 ま、ここを一緒に掘り下げていけたらなと 思います。まず、え、文部科学省が提唱 するこの生きる力の、ま、3つの要素で なってるんですね。ま、1つ目が確かな 学力で、2つ目が豊かな人間で3つ目が 健すやかな体ですね。学力と体は分かる けどな人間なんてかな学僚っていう事言 なんか偏差値主義みたいでねんけど。はい 。ここすごく大事なポイントなんですけど も、この確かな学力っていうのは、単なる 知識の量とかテストの点数ではないんです ね。ま、重要なのは得た知識を実生活とか こうなんか問題が起きた時にそれを活用 する力であったりその知識を元に何かを 深く考える力のことを、え、ここでは学力 っていう風に言っています。 豊かな人間性ってのは最近よく聞く非妊能力ってやつと関係あるん? はい。まさにその通りですね。 え、教育分野とか心理学の分野では 非妊認知能力っていう風に、ま、最近言わ れたりするんですけども、これ要するに、 え、自分を信じる力、自己肯定感であっ たり問題を乗り越えようとする力、 いわゆる自己解決能力のことを、ま、 細かくは分類すると色々あるんですけども 、非妊認っていう風に言います。 で、これが将来社会に出て人間関係を気づく力であったり、ま、仕事でこう良性トラブルにあった時にそれを乗り越えようとする、ま、そういう心の根感になっていくものですね。 つまり手外の転数じゃなくて使いこなせる力ってことね。親が先に答えを出しすぎたらこの根っこが育たへんってことか。 この根っこを育てるためには日常の選択と決定がとても大切になってきます。 え、じゃ、次のパートで、え、すぐに実践 できるこの選択と決定についてお話しして いきたいと思います。この生きる力を育む ための、ま、1番最初の簡単なステップと しては、もうその名前の通り子供に選ば せることですね。日常のほんの些細なこと 。ま、例えば今日は赤色の服と青色の服 どっち選ぶとか、今日は靴で行くとか、ま 、もっと言うと例えば靴下、今日は右足と 左足どっちから履くとかでもいいわけです 。ま、他にも例えば片付けの場面では、 じゃあおもちゃ今日はどれから片付け るっておもちゃを片付けるっていうゴール は一緒なんだけども、じゃそのおもちゃを じゃどれから片付けんのかっていう、こう 段取りを子供自身が選ぶっていう、これが 子供に選ばせるっていうとても大切な ステップになるんですね。だから保育園に 行く前にこう靴を吐くっていうことをとっ ても靴を履くっていうゴールは変わらない けれどもじゃあ右足から吐くのか左足から 履くのかじゃ例えば靴下を履いてから吐く のか靴下を履かずに今日は吐くのかって いうゴールは変わらないけどもそこに たどり着くまでのえステップを子供が選ぶ ことがま大切なんですねえ 感なんか戦場や でパパッと決めて履かせたい はい。その気持ちほんまに分かります。でも、ま、この小さな選択の積み重ねっていうのが、ま、将来的にはこう子供があ、自分の人生は自分で決めていいんやっていう風に思えたり、こう自己肯定感を養うことにつがっていくわけなんですね。 ま、とは言ってもやっぱこう朝のすごい もうバタバタしてる時間帯なんかでは、ま 、そうやって選択肢を与えてあげ るってことが、ま、どうしても難しい場面 ってもたくさんあったりするんで、ま、 ここで意識しておいたら、ま、ちょっと気 が楽になるかなって思うのが、親、ま、 大人が80%を決めて子供が20%を 決めるるっていう風に考えておくと、 ほとんどはもう服も靴も朝ご飯の食べる 時間も、ま、もうほとんどもう決めちゃう けども、子供がじゃ靴下今日は何色で 履こうかな?何色履こっかなとかもう ほんの20%の部分を子供が選ぶっていう 風にするだけでも選ぶ選択と決定はそこで 保証してあげられるっていうことですね。 やっぱ朝の時間なんかで言うとこう時間が やっぱりかけられてたり、こう大人も仕事 に遅れちゃいけないとかいうのがあったり するんであかじめじゃあこれはあの年齢 時期にもよるんですけども時計の長い針り がここ4になるまでにはお片付けしてねと か靴下履いておいてねとかいう風にタイム リミットを設けるっていうこともま1つ手 としてはとても有効になってきます。ま、 ここでちょっとやっちゃいけないのが、ま 、カウントダウン形式にして、じゃああと 10秒で決めてなみたいな風に、こう 切まった、こうタイムリミットをしちゃう と、こう、子供も急に決めて、え、そんな 中で選ぶのちょっとできひんわってなっ たり、大人も家も10秒で決めてって言っ たやんでわーってなったりするんで、ま、 ここはあかじめちょっと余裕のある、もう タイミングにもう先に言っておく。できる だけ冷静に言っておくと、ま、そこの決め たじゃあ4までに決めてなって言ったん やったら、ま、4までは大人も、ま、冷静 に待てるしみたいな。で、そこまでに決め へんかったり、そこまでに決めたものが 後々子供の納得いくもんじゃなかったとし ても、でもそれはもうそこまでに決めて 言ってたよねとか、ま、そん時うんて言っ たよなっていう風に、ま、子供も大人も こう余裕を持ったタイミングでそれを 伝えるっていうことが、ま、大切な ポイントになってきます。なるほど。親が イライラせためのテクニックでもあったん やね。変なで保育園に行ってもそれもいい 子ってことなんやな。はい、その通りです 。え、失敗もまあ経験なんで。経験、ま、 すなわち学びなんで、ま、こういう小さな 心配っていうのは、ま、他にもいろんな ことで言えるんで、ま、こういう時に じゃあどんな関わりがあるかっていうのを 、ま、次お話ししていきたいと思います。 はい。じゃあ、ま、大切な、え、重要な大 前提なんですけども、この生きる力が強い 子っていうのは失敗を恐れないんですね。 で、失敗っていうのは怪我も含まれるん ですね。でもこの怪我も恐れない子ほど 生きる力が強いんです。 なので、ま、親御さんにはできるだけ小さな失敗、小さな怪我っていうのをたくさん経験させてあげられる、ま、そういう勇気をどうか持って欲しいなっていう風に思います。 親としては危ないことさせるのは怖いんよな。 SNS とか見てったらちょっとした怪我でも親は何してたのって言われそうで はい。お気持ちはね、すごく分かります。 現代だと特にね、こう安全への意識って いうのがとても高くて、親御さん自身が どうしてもプレッシャーを感じちゃったり 、か、子供が怪我した時に、いや、親は何 してたんやって言われることってやっぱ どうしても多い世の中になってきてるんで 、先回りして怪我になりそうなことって いうのはもうあらかじめやめさしたりとか 、ま、止めるっていうことがま、ありがち やなっていう風には思いますね。でもこの 怪我にも大きな怪我はやっぱ防ぐべきもの なんですけども、この小さな怪我までを 制限してしまうと、こう子供はその危険を まだ自分ではなん、なんか止められたって いうことが先に来てしまって、何が 危なかったやろっていうことは経験して ない以上、やっぱりどうしても大人以上に こう分かることがないんで、大人よりも そこは理解できないんで、危険予測をする 機会っていうのを奪っちゃうことになるん ですよね。で、この小さな怪我を防いで しまうともうその危険予測ができないから いざこう大人が見れないような時に子供 だけで何かをしてるっていう時にそれが 大きな怪我に繋がってしまったりするん ですね。これちっちゃい怪我をいっぱい 経験しているとそこで危険予測っていうの を経験の中でどんどん積んでいくんで 小っさい怪我はするけどもそれがこう 大きい怪我には繋がりにくくなるっていう ことになるんですね。ま、例えばこう走っ てて転んで膝すり向いた。じゃあそれ時 おもちゃ持ってたやったらおもちゃ持って たから危なかったんかなっていうのも子供 自身がおもちゃ持って走って転ばないと 学べないんですよね。これ言われたら一見 なんか分かったような表情とかはするん ですけども子供の中にはただ責められ たっていうことしか残らないですね。子供 自身がそれを自分で学ぶには転んで おもちゃ持ってたから底王をこう上手に前 につけなかったっていうのを自分自身で 気づく必要があるんですね。でもこの 小さな怪我の話の中には自分でじゃ例えば 転んで怪我するっていうことだけじゃ なくって、え、例えば保育園ペンだとじゃ との喧嘩とか衝突もその小さな怪我とか そこでこう関わり方でこう起こって相手 叩いちゃったとか感じじゃったとかま、 そういうことも含まれるんですけども、ま 、ちょっとここ噛みつきとか叩くとかいう のはちょっとまた別の機会でお話ししたい なと思います。ま、大切なのはこう子供が 転んだ時とか子供がなんか失敗した時に親 大人がすぐにこう解決策を出さないって いうことですね。こ解決策とかこう原因を すぐに大人が言わないっていうことが、ま 、とても大切になってきます。ま、大切な 、え、ポイントが3つあって、まず1つ目 が、え、まず共感する。じゃ、例えば走っ てて転んだんやったら、え、じゃ、 おもちゃ持ってて走ってて転んだとし ましょう。こん時に、ま、転んだら、ま、 痛いですわな。そしたらまあ泣くんです けども、まずはここに対してああ、走って て転んだんか痛かったな。これだけでいい です。もうこの共感がまず1つ大事。で、 2つ目がなんでそうなったんかっていうの を、ま、明確にすることですね。ま、これ を大人がするんじゃなくって、そっかなん でこのんじゃったんやろうなとか、ま、 例えばおもちゃをじゃ、例えばブロック 積んでて、それが崩れちゃった。もう悔し いってあんなに頑張って積んだのに崩れ ちゃった。なんで崩れちゃったんやろう なっていうのを、ま、大人が答え出すん じゃなくて、ま、一緒に考える。ま、3つ 目がじゃ、なんで転んじゃった、なんで 崩れちゃったんやろってのが、ま、出 にくい時にもしかしたらこうこうやった からかな、おもちゃ持ってたからかなとか 、ちょっと斜めになってたからちゃうとか 、ま、そういう風にちょっとヒントを出す ことですね。これを断定せずにヒントを 出すことが、ま、大切っていうことですね 。 はい、ありがとうございます。ま、それは ね、本当に全然親御さんに限らず保育師で もよく言いがちな言葉ではあるんですけど も、ま、そうやって大人が先に断定して ほらおもちゃ持ってたからやんとかほら こうしてたからやっていう風に言って しまうと子供がこう自分で考える機会って いうのをそこで奪っちゃってもう子供は そのなんでこうなったんやろうっていうの 考える必要がなくなったらもうあとはそこ からこう責められたっていうこう ネガティブな感情だけが残っちゃうわけな んですよね。避けた方がいいとできるだけ ね。ま、大切なのはこう責めることじゃ なくて、じゃあなんでこうなったんやろ うっていうのを、ま、子供自身が自分で 考えて、じゃあそれを次、じゃあそうなら へんためにはどうしたらいいんかなって いうことを考えるそのプロセスが大事って いうことですね。同じことにならへんため にはどうしたらいいかっていうのを考える 上でさらに大人がじゃそこにどう関わって いったらいいかっていうことなんですけど も、じゃ子供がうん、じゃおもちゃ持って たからやと思うとこここうしたらブロック 崩れへんかったんちゃうかなっていうのを 子供自身が考えた時にあ、なるほどなって 自分でそうやって気づいたんやっていう その気づきに対してそれが合ってるとか 間違ってるとかいう大人の主観は置いて おいて子供がなんか自分で考えて気づい たっていうことにまずはこうそこを認める 、転んだりとかなんかおもちゃ崩しちゃっ て失敗したことをもう1回や るっていうこの立ち上がるっていう最長に 対してまたもう1回諦めずにもう1回やる んやっていう風に言うていうことが ちょっと難しい言葉になるんですけども 立ち直る力えンス って言うんですけどもを育組むことに つがるんですね。偉いばっかり 言ってたけどもう1回やってみる勇気を 褒めるって小さな怪我を恐れない心を育む こととつがってるんやね。はい。そうです 。だから、ま、生きる力っていうのは、ま 、こう自分は愛されてるんやなっていうの をまず思うことと自分はなんか分からん けどこのでっかい壁乗り越えられる気が するなって思えるような根拠のない自信、 この2つがばっちりあることで生きる力 っていうのはどんどん育っていくんですね 。根拠のない自信っていうのはやっぱり 例えば周りの大人のこう失敗してもその 失敗こと全部受け止めてもらえるような 環境とか自分自身がたくさん失敗できた 小さい失敗とか怪我をたくさんできたって いう経験がそれらを作っていくことですね 。失敗してもええやんて笑える大人の余裕 が子供の生きる力を支えるんやね。うちも もうちょっと肩の力抜いて子育てみるわ。 はい。ありがとうございます。え、じゃあ まとめきたいんですけども、ま、今日はね 、生きる力について、ま、まず大人が、ま 、先に答えを出すんじゃなくって、ま、 子供が自分で考えてこう気づけるように するっていうのと子供が自分でこう選べる 、それは、ま、時間がない時であっても、 ま、ちょっとでもいいから子供が自分で選 ぶっていう経験ができ るっていうことですね。その中では小さな 怪我とか失敗っていうのもあるんですけど も、ま、そういう中でこうその小さな怪我 とか失敗につがるような挑戦もできるよう な環境を作るってことが大事です。ま、 この環境を作るっていうのはこう物理的に なんか作るんじゃなくって、ま、そういう 失敗もいいんやでっていう風にこう見守 るっていうこう大人の心が構えっていうの がま、大事だよっていうお話でしたね。 毎回毎回ね、こう前向きな言葉ができると は限らないし、やっぱどうしても ネガティブな言葉を言ってしまったりする ことはもちろんあるんで、ま、そこは完璧 を目指さなくて大丈夫なので、ま、それも 踏まえて、ま、経験というか大人も失敗し ていいかなっていう風には思います。はい 、じゃあ今回の動画は以上にあります。 この動画が参考になったわ人は高評価と チャンネル登録頼むで、次は子供の噛つき についてお話しするやで。じゃあ、また 次回の動画でお会いしましょう。え、ご 視聴ありがとうございました。それでは さよなら。 最後まで見てくれてありがとう。コメント もどんどんちょうだいや。おばっちゃん 喜ぶで。
【小さな怪我や失敗こそ最高の先生!】
今回の動画では、元保育士いけちゃんが、「小さな失敗や怪我こそが生きる力を育む栄養剤」であることを、
保育のプロ視点から分かりやすく解説します。
大切なのは、転んだ後の親のたった一言!
子どもが自分で立ち直る力=レジリエンスを育むための具体的な関わり方と、つい言ってしまいがちなNGな声かけまで、徹底解説します。
✨自分で考えて行動する子に育てるための永久保存版です。
✅ 動画内容(目次)
00:33 生きる力を構成する3つの要素
01:27 『非認知能力』
02:08 『選択と決定』
06:03 『ケガと失敗させる勇気」』
10:12 つい言いがち!内省を止めるNGな声かけ
11:07 【魔法の声かけ3選】レジリエンスを育む方法
12:54 まとめと次回予告
✅ 今回のポイント
・確かな学力=知識の活用力と深く考える思考力のこと。
偏差値じゃない!
・小さな怪我は、危険を察知する脳と体の**「予行演習」**です。
・失敗した時こそ「自分で気づいたね、すごい!」と過程を
肯定してあげましょう。
✅ 次回予告
「噛みつき」「喧嘩」など、他者との関わりで起こるトラブルへの関わり方を解説します!お楽しみに!
#子育て #育児の悩み #非認知能力 #レジリエンス #生きる力 #失敗 #怪我 #自己肯定感 #保育士