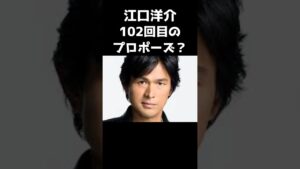快進撃を続ける映画『国宝』が、ついに興行収入150億円、観客動員数1,066万人を突破した。
邦画実写作品としては22年ぶりの100億円突破で、邦画歴代興行収入ランキングでは『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(173.5億円)に次ぐ2位を記録。6月6日の公開から110日以上経った今も勢いは止まらず、どこまで記録を伸ばすか注目を集めている。
また第98回米アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表に選出され、2026年に北米での公開が決定している。
『国宝』がなぜここまでの歴史的な大ヒットとなったのか、その理由と魅力に迫っていく。
映画『国宝』あらすじ
 映画『国宝』李監督、吉沢亮、横浜流星、渡辺謙がカンヌ入り ⓒKazuko Wakayama
映画『国宝』李監督、吉沢亮、横浜流星、渡辺謙がカンヌ入り ⓒKazuko Wakayama
本作は吉田修一の小説『国宝』を、『フラガール』(2006)『悪人』(2010)を手がけた李相日監督が映画化した。
上方歌舞伎の名家に引き取られた任侠の息子が才能を開花させ、その家の御曹司とライバルとして芸を磨き、人間国宝を目指していく激動の人生が描かれる。
任侠の一門に生まれた喜久雄は、15歳の時に抗争で父を亡くし、上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎に引き取られ歌舞伎の世界へ飛び込む。そこで、生まれながらに将来を約束された御曹司・俊介と出会う。正反対の血筋を受け継ぎ、生い立ちの才能も異なる2人。ライバルとして互いに高め合い、芸に青春をささげていくが、多くの出会いと別れが運命を大きく狂わせていく。
主人公の喜久雄を吉沢亮、ライバルの御曹司・俊介を横浜流星、花井半二郎を渡辺謙が演じる。永瀬正敏、田中泯、寺島しのぶら実力派俳優が脇を固める。
口コミで広がり社会現象に
公開初週の興行収入ランキングは3位のスタートだった。重厚な歌舞伎がテーマであることに加え、上映時間2時間55分という長尺ながら、SNSを中心に口コミで人気が広がり、公開3週目には首位を獲得した。そこから右肩上がりに記録を伸ばし、公開から73日間で100億円を突破し快進撃が続いている。
公開初週の劇場はシニア層が大半だったという。公開から2ヶ月後に筆者が映画館へ足を運んだときは、歌舞伎に馴染みのない10代、20代の若年層が多く来場しており、幅広い層にまで人気が浸透している印象を受けた。また、その映画館では400人以上収容する2つのスクリーンで上映していたにもかかわらず、朝の上映回からチケットが全て完売。
また映画館にめったに行かない友人たちが「『国宝』を観に行った」という話を耳にし、口コミの広がりの凄さと『国宝』が社会現象化しているのを肌で感じた。
吉沢亮と横浜流星の美しさと演技力
 吉沢亮、映画『国宝』より ©吉田修一/朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会
吉沢亮、映画『国宝』より ©吉田修一/朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会
口コミやSNSで多く目にしたのは主演2人に関してだ。やはりなんといっても『国宝』の大きな魅力の一つは、主演の吉沢亮と横浜流星の圧倒的な演技力にある。2人の妖艶な美しさと感情を揺さぶられる演技に、3時間の長編作品でも飽きることなく見入ってしまう。Xでも「美しすぎる」「演技が凄まじい」という投稿を多く見かけた。
吉沢と横浜は、1年半をかけて歌舞伎の所作や舞踊の稽古を積んだという。「1年半を一つの役に込められることはなかなかない。これまでの役者人生の全てを懸けた」と吉沢は語る。
主演2人の演技力だけではない。歌舞伎初心者でも楽しめる作品であり、さらに歌舞伎の持つ“華“を3時間存分に味わえる贅沢さも口コミが広がった要因に挙げられる。
歌舞伎界は、「家」を重んじる世界で芸名を先人から子孫へ代々受け継いでいく。そのため、敷居が高く閉ざされたイメージがあり、舞台裏を知る機会もなかなかない。それゆえ歌舞伎を知らない人でも楽しめるストーリーに加え、原作者の吉田修一が3年間にわたり歌舞伎の“黒衣”として楽屋に入った経験を元に描かれていることで、普段は知ることのない歌舞伎の世界に触れたいという好奇心に繋がったと考える。
 横浜流星、映画『国宝』より ©吉田修一/朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会
横浜流星、映画『国宝』より ©吉田修一/朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会
400年以上の歴史を誇る歌舞伎
整った顔立ちに確かな演技力で、国民的な人気を誇る吉沢と横浜。日本を代表する旬の俳優2人が、日本の伝統芸能である歌舞伎役者をどう演じるのか、そんな興味から映画館に足を運んだ人も多いだろう。
歌舞伎は400年以上の歴史を誇る日本の伝統芸能だ。1603年(慶長8年)に京都で出雲阿国が「かぶき踊り」を踊ったのが始まりと言われている。その過程で、女性たちによる『女歌舞伎』が生まれるが、風紀の乱れを理由に幕府によって女性の出演が禁止された。これにより、男性が女性を演じる「女形」が生まれ現在の歌舞伎の基礎が形成された。
歌舞伎で先人の名前を継ぐことを襲名という。名前とともに芸と心を、親から子へ、子から孫へと代々受け継いでいく。以前は芸養子が継ぐことも多かったが、現在は実子への世襲がほとんどだという。
「血筋」か「才能」か
『国宝』の中心となるテーマは、「血筋か才能か」だ。上方歌舞伎の名門の血筋を持つ俊介(演:横浜)と、任侠の息子で才能を開花させていく喜久雄(演:吉沢)がライバルという構図も対照的で分かりやすい。
一見するとこのテーマは遠い世界のことのように感じる。しかし才能を情熱に置き換え「一つのことに人生をかける」という視点から喜久雄を見ると、命をかけて打ち込むことへの羨望や何かに情熱を燃やしたい衝動がわいてくる。いつのまにか喜久雄を自分に投影し、まるで現実の出来事のように「血筋」か「才能」かというテーマに引き込まれていく。
また同時に、吉沢亮と横浜流星が生々しいまでの熱量で歌舞伎役者の半生を演じる姿が、人生を芸にささげる俊介と喜久雄に重なる。まるで4人の運命を見ているような壮大な体感が、観る者の心を惹きつけて離さないのではないだろうか。
公開から3ヶ月以上経った9月末の週間興行収入で、『国宝』はいまだ5位にランクインしている。『国宝』の快進撃はまだまだ続きそうだ。
【関連記事】