劇場公開日:2025年9月26日
解説・あらすじ
1990年代のアメリカ郊外を舞台に、自分のアイデンティティにもがく若者たちが深夜番組の登場人物に自らを重ねる姿を、不穏かつ幻想的に描いたスリラー映画。
冴えない毎日を過ごすティーンエイジャーのオーウェンにとって、毎週土曜日の22時30分から放送される謎めいたテレビ番組「ピンク・オペーク」は、生きづらい現実を忘れさせてくれる唯一の居場所だった。オーウェンは同じくこの番組に夢中なマディとともに、番組の登場人物と自分たちを重ね合わせるようになっていく。しかしある日、マディはオーウェンの前から姿を消してしまう。ひとり残されたオーウェンは、自分はいったい何者なのか、知りたい気持ちとそれを知ることの怖さとの間で身動きが取れないまま、時間だけが過ぎていく。
「名探偵ピカチュウ」のジャスティス・スミスがオーウェン、「ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!」のジャック・ヘブンがマディを演じ、「ショップリフターズ・オブ・ザ・ワールド」のヘレナ・ハワード、ミュージシャンのスネイル・メイルことリーンジー・ジョーダン、「ティル」のダニエル・デッドワイラー、ロックバンド「リンプ・ビズキット」のボーカルで映画監督としても活動するフレッド・ダーストが共演。
2024年製作/102分/PG12/アメリカ
原題または英題:I Saw the TV Glow
配給:ハピネットファントム・スタジオ
劇場公開日:2025年9月26日
オフィシャルサイト スタッフ・キャスト
全てのスタッフ・キャストを見る
テレビの中に入りたい の関連作を観る
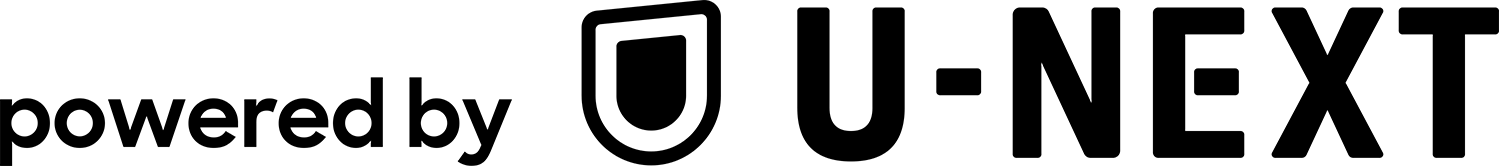
関連ニュースをもっと読む
(C)2023 PINK OPAQUE RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
4.0 繊細で大胆で生々しい表現力。刺さる人には刺さるはず
2025年9月26日
PCから投稿
鑑賞方法:試写会
本作に触れた瞬間、なぜか胸が震えた。と同時に、子供の頃のノスタルジーやあの頃の漠然とした不安がこみ上げ、正直、恐ろしくもなった。優しい顔をした亡霊のような、はたまた一向に醒めない夢のような一作だ。手掛けた監督はトランスジェンダーなのだそうで、おそらくあの少年少女は、閉ざされた町で自分に違和感を抱え続ける、かつての監督の分身とも言うべき存在だろう。しかしたとえその状況や心情が重ならなくとも、思春期における「俺はおかしいのか?正常なのか?」という自問は誰もが少なからず共感可能なものではないだろうか。逃げ出したい。でも逃げ出せない。正気が保てなくなる。叫び出したい。そして気がつくと、最近あまりにも年月が経つのが早すぎるーー。A24作品はいつも言語化不能の感情を豊かに提示してくれる。酷評する人もいるはず。意味不明に思える人もいて当然。だが私は繊細かつ大胆なタッチで世界を彩った才能に拍手を送りたい。
 1.5 シーズン5で1000話超え!?
1.5 シーズン5で1000話超え!?
2025年9月28日
Androidアプリから投稿
アメリカの郊外で暮らす中学生の男の子が、同級生の女の子に教えてもらったTV番組「ピンク・オペーク」にハマって行く話。
マディの家にお泊りに行って、毎週土曜日22:30から放送されるヒーロードラマ?「ピンク・オペーク」をオペークを教えて貰ったけれど、オーウェンの就寝時間は22:15と決められており観られません!ってことで、録画して貰ったビデオで鑑賞!となって行くけれど、見る順番はぐちゃぐちゃなので?そして良くわからないけれど初回はPILOT?
なんだか不思議な女子2人組ドラマのピンク・オペークを観続けたけれど、環境が変わってマディは引っ越してしまい、取り残されたオーウェン君ががるぐるぐるぐるぐる…そしてマディが現れこいつマジか!?
現実とドラマが交錯しなんだか良くわからないことになっているけれど、アイデンティティ云々ってそういうこと?
スリラーといえばそうなのか?
どういうことはなんとなくは分かったつもりだけれど、ちょっと自分には理解できない話しだった。
 3.0 「自分」とは?
3.0 「自分」とは?
2025年9月28日
iPhoneアプリから投稿
鑑賞方法:映画館
家庭での居場所や性的アイデンティティについての自分探しをする若者達の右往左往を独特の映像美(と言っていいのか否かわからんが)で描く、いかにもA24な作品。
TV番組と現実との区別が曖昧になっていく描写を通じて、物事を認識する主体としての「自分」がいったい何処に居るのか、さらに、その「自分」の知覚が実際に目の前で起こっている出来事の忠実な反映なのが、脳内の神経回路で生じたそれっぽい情報伝達が生んだだけのバーチャルなイメージなのかも分からなくなっていく。
自分の内側を覗いて空っぽだったら怖い、みたいな台詞が象徴的なのだか、そもそも「自分」なるものが存在する、という前提で考えるから出口が見つからない訳で、仏門に入って、自分なんて「空」だぜ、と悟ってしまえばOKじゃないのかな、というのは意地悪かな。
主役2人の、様々な場面での居心地の悪さの描き方が独特で面白かったのだが、監督もこの2人も性的アイデンティティについて少数者に属するらしい事と関係してるかどうかはわからない。
 4.0 徹底して「出口がない」表現が痛々しい。
4.0 徹底して「出口がない」表現が痛々しい。
2025年9月28日
Androidアプリから投稿
鑑賞方法:映画館
予想していた内容とは違っていた。ジェーン・シェーンブルン監督はトランス女性でノンバイナリーである。90年代中頃のアメリカの田舎町ではキュアな指向をカミングアウトするのはとても難しかった、その体験を作品として取り上げマイノリティを勇気づけるというようなことをインタビューで話していたのだが。
主役のオーウェンは母親を病気でなくし、父親とも血の通った関係性にない、おそらくはほとんど友達もいない孤独な少年である。「どれだけ掘り下げても自分が見つからない」というようなことを言っているので広い意味ではキュアな傾向にあるのかもしれない。一方、彼に「ピンク・オペーク」の存在を教えるマディは同性愛者であると自分で述べているし「ピンク・オペーク」の内容(少なくともオーウェンの目に映る限り)は性的に規範外である匂いはする。でもこの映画は性自認や性指向は主題ではないのかも。
1996年が起点で、その2年後、その8年後、さらに20年後と時制が進んでいく。この間、オーウェンは多分、一度たりとも町を出ていないのである。両親の残した家に住み、最初は映画館に、その後はゲームセンターに勤める。家族を持ったとのモノローグがあるがその姿は示されない。
徹底的に地元暮らしなのである。閉じ込められているといっても良いかもしれない。彼が外界と接したのは、「ピンク・オペーク」とマディだけ。でも「ピンク・オペーク」は10年後、配信で見直してみたら全く違う印象の作品だったし、マディについては2回も裏切ったという罪悪感が残る。ひょっとしたら「ピンク・オペーク」もマディも彼の心が見せるまぼろしだったのかも。それならば彼の人生は一体、何だったのか?映画は最後、おそらく喘息の新薬の副作用でフラフラになった彼が、ゲームセンターの中で誰彼構わず「すいません、すいません」と謝って回る痛々しいシーンで終わる。(マディには謝らないよう言われていたのに)
生きることの徒労感、出口が見えない不安感が、オーウェンと同じ世代(日本で言えば氷河期)の人たちに共有化されたことがこの映画がアメリカで拡散され支持された理由じゃないだろうか?







