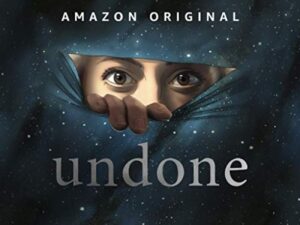「チカキサダ」2026年春夏コレクションから PHOTO:KO TSUCHIYA
2025年はジャパン・ファッション・ウィーク(JFW、通称「東京コレクション」)が20周年を迎える年だ。これまで、東コレは日本のファッション産業の発展を目指してさまざまな取り組みを行ってきた。メルセデス・ベンツ日本やアマゾン ジャパンのスポンサーシップを得て、「メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク東京」「アマゾン ファッション ウィーク東京」と正式名称を変えながら、現在は楽天の支援のもと「楽天 ファッション ウィーク東京」と呼ばれている。
私はそのうちの約10年間、東コレに通い続けてきた。「東京のファッション・ウイークは盛り上がっている!」と言いたいところだが、以前ほどの熱狂を維持できているとは言い難い。10年前は約40ブランドが参加し、多い日には1日6〜7ブランドがショーを開催していたし、会期外を含めるとさらに多くのブランドが独自でコレクション発表する場を設けていた。それと比較すると、今季の2026年春夏は23ブランドにまで減ってしまった。「私の大好きなファッション・ウイークにはもっと盛り上がってほしい!」というのが率直な思いで、そのためにファッションはより“開かれたもの”になる必要がある。このコラムでは、今後の期待を込め、これまでの東京の節目を振り返りながら今季感じたことを記したい。
東コレの転換点①
2011年:「バーサス トーキョー」

「エムエスエムエル」2026年春夏コレクションから
私は2011年、上京した。東日本大震災が起きた年だ。日本全体に「TVを含めたエンターテインメントは不謹慎」という風潮が広がり、外へ出て友人と食事をしたり、お酒を飲んだりすることさえ“軽はずみな行為”と見なされていた。ファッション・ウイークも例外ではない。「(復興への)祈り」をテーマにして単独でショーを開催したブランドもあったが、3月に開催を控えていたブランドのショーはほとんどが中止になった。
それでも、新しいファッションショーの形を示すと同時に、復興と街の彩りを取り戻し、生活に潤いを与えるためでもあったのではないかと感じるイベントもあった。同年11月に開催された特別イベント「バーサス トーキョー(VERSUS TOKYO)」だ。ファッション・ウイーク最終日に「フェノメノン(PHENOMENON)」「ディスカバード(DISCOVERED)」「ウィズリミテッド(WHIZLIMITED)」「ファセッタズム(FACETASM)」といった気鋭ブランドが合同でショーを行うこのプロジェクトで、入場券を購入すれば誰でも観覧できた点が新しかった。当時、ファッションショーはジャーナリストやバイヤーなど限られた人にしか開かれていなかったが、その閉じた場に「一般の観客」という新しい層を引き込んだ。また、当時はファッション・ウイークの中にストリート文化を受け入れ難いムードがあったが、上述のブランドが参加することで、これを起点にファッションをストリートの文化として共有した。ここから飛躍したのが、のちにパリ・ファッション・ウイーク常連となる「ファセッタズム」だ。今振り返って見て、イベント「バーサス トーキョー」は東京ファッションの実験精神を象徴していたと思う(売上は、東日本大震災の復興のため日本赤十字社に寄付された)。
東コレの転換点②
2015年:「東京ニューエイジ」

「ケイスケヨシダ」2026年春夏コレクションから PHOTO:YOKO KUSANO
次の節目は、私がファッションライターとして参加するようになった15年のプロジェクト「東京ニューエイジ」である。渋谷パルコ協賛のもと、自主開催が難しい若手ブランドにもチャンスが与えられ、「ここのがっこう」の卒業生を中心に若手デザイナーたちが合同ショーを行った。参加したのは「アキコアオキ(AKIKOAOKI)」「コトハヨコザワ(KOTOHAYOKOZAWA)」「ケイスケヨシダ(KEISUKEYOSHIDA)」「リョウタムラカミ(RYOTAMURAKAMI)」など、後に東京の新世代を代表する存在となるブランド群。まだ資金も経験も十分ではなかった彼らが、集団として東コレに登場したことは大きなインパクトを残した。
この時期から東コレには「一般招待枠」が設けられ、メディアと連携して募集告知を打ち、より大々的に一般客を呼び込むようになる。特に忘れがたいのは、「ケイスケヨシダ」のショーで、300人収容の会場に対して約1000人の応募が殺到したエピソードだ。会場外でスクリーン越しにショーを見守るファンも出た。もちろん安全面を考慮した上で収容人数に制限をかけているため、1000人を「ブランドの集客実績」と認めるのは難しいが、これほどまでにファッションに熱を注ぐ若者が集まったという事実は、いま振り返れば忘れ難い光景である。
加えて、当時は若手ブランドに加えてベテランブランドが継続的に参加し、「今期の大トリはどこだ?」と期待されるムードがあった。「アンリアレイジ(ANREALAGE)」「ケイタマルヤマ(KEITAMARUYAMA)」「ドレスキャンプ(DRESSCAMP)」「ミハラヤスヒロ(MIHARAYASUHIRO、現在はMAISON MIHARA YASUHIRO)」などの会場には著名人や若手デザイナー、そして個性的なファッションに身を包んだ学生たちが集まっていた。
東コレの転換点③
2020年:新型コロナウイルス感染拡大

「フェティコ」2026年春夏コレクションから PHOTO:KO TSUCHIYA
しかし、その盛り上がりを断ち切ったのがコロナ禍である。20年は全ての発表形式がYouTubeを介したデジタル配信に変更。翌年からはフィジカル発表が再開したが、ブランドが来場ゲストの人数を絞ったことで、“閉じられた”形式に舞い戻ってしまった。
その後、「アンダーカバー(UNDERCOVER)」や「ア・ベイシング・エイプ(A BATHING APE)」といった著名ブランドの参加で活気を取り戻したかに思われたものの、参加ブランド数は一時に比べ戻る気配もなく、現在の姿に落ち着いている。背景には、メンズブランドの多くが東コレから離脱してしまった現象があるだろう。パリ・メンズ・ファッション・ウイークの時期に合わせるため、「カミヤ(KAMIYA)」「M A S U」「シンヤコヅカ(SHINYAKOZUKA)」「ダイリク(DAIRIKU)」「シュガーヒル(SUGARHILL)」が先駆けて単独ショーを開催するようになった。
近年は「フェティコ(FETICO)」「ハルノブムラタ(HARUNOBUMURATA)」「ピリングス(PILLINGS)」「ヴィヴィアーノ(VIVIANO)」「チカ キサダ(CHIKA KISADA)」「ヨシオクボ(YOSHIOKUBO)」といった実力派が継続的に参加し、ファッション・ウイークを支えている。特に「チカ キサダ」のモノ作りの姿勢は素晴らしいので是非体感してほしいのだが、今回は人数を絞っての開催であった。
ファッションが“開かれたもの”になるには
体感することの重要性

「アンセルム」2026年春夏コレクションから PHOTO:KOJI HIRANO
ここまでファッションショーの一般開放や若手ブランドの参加、ベテランブランドによる話題作りを鍵に、東コレの転換点をおさらいしてきた。中でも私が重要視するのは、ショーの一般開放による観覧者数の増加である。ファッション・ウイークの盛り上がりが停滞している要因として、世界情勢や環境問題、何より若者がファッションにお金を使わなくなった事実も無視できない。だが、本質的な問題は、ファッションがまだ「文化的に開かれた場」として機能していないことにある。ここで、アートの建築・空間を生業にする、ある先輩が語った「アートはパブリックなものにするべきだ」という言葉を引用したい。街に作品が開かれ、誰もが偶然にアートに触れられる環境は、人々の感受性を育てる。ファッションも同じで、特権的なイベントに閉じるのではなく、都市全体で共有される文化へと進化すべきなのだ。多くの人がファッションショーを文化として体験することが刺激となり、業界の新たな才能を発掘し、次世代のファンを育てる土壌となる。
今季は東コレ初参加の「アンセルム(ANCELLM)」、前シーズンから参加の「エムエスエムエル(MSML)」が約800人を招待し、会場に活気を取り戻していた。私はファッションショーを“都市の祭り”として、市民に開かれた文化にすることに可能性を感じる。なお、「ヨシオクボ」がブレイキンとのダンスコラボショーで話題を呼んだが、野外で通りすがりの人も興味を持てるように開けていれば、もっと渋谷の街や人を巻き込んだ特別なショーになったと思う。

「ヨシオクボ」2026年春夏コレクションから PHOTO:RYAN CHAN
ショーはあくまでビジネス戦略の一環であり、規模や招待人数をコントロールするのは当然のことだ。しかし、東コレに参加する以上「祭典を盛り上げる一員」としての役割を担ってほしい。ショーでなによりも尊いのは、デザイナーらが半年かけて作り上げたコレクションのみならず、彼らのファッションに向き合う姿勢や、観客が新作に対面するときの緊張感だ。情報が氾濫する時代だからこそ、実際に体感することの価値は大きい。
日本の祭りが地域の人々にとって、誰もが参加し、祝う行事であるように、もう少しパブリックな空間での発表が増えれば、ファッションは「共有する文化体験」へと変わるはずだ。東コレが人々にとって“開かれた文化行事”として認識されていない以上、われわれメディアを含めた関係者が裾野を広げる努力が必要だ。デザイナーやブランドだけでなく、主催者、行政、メディアが一体となって、ビジネスと文化を両輪で育む。その先に、私がかつて体験した熱狂を再び味わえるファッション・ウイークが生まれるはずだ。