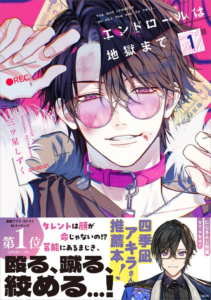映画ならではの魅力とは
2025年9月17日 午前7時00分

映画「国宝」より(c)吉田修一/朝日新聞出版(c)2025映画「国宝」製作委員会

映画「国宝」より(c)吉田修一/朝日新聞出版(c)2025映画「国宝」製作委員会

映画「国宝」より(c)吉田修一/朝日新聞出版(c)2025映画「国宝」製作委員会

映画「アイム・スティル・ヒア」より(c)2024 VideoFilmes/RT Features/Globoplay/Conspira☆(セディラ付きC小文字)☆(チルド付きA小文字)o/MACT Productions/ARTE France Cin☆(アキュートアクセント付きE小文字)ma

映画「アイム・スティル・ヒア」より(c)2024 VideoFilmes/RT Features/Globoplay/Conspira☆(セディラ付きC小文字)☆(チルド付きA小文字)o/MACT Productions/ARTE France Cin☆(アキュートアクセント付きE小文字)ma
「国宝」の勢いが止まらない。6月6日の公開から約3カ月、興行収入は124億円(8月末時点)を突破、邦画の実写映画としては「南極物語」を超えて「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」(173億円)に次ぐ2位となった。米アカデミー賞国際長編映画賞部門の日本代表にも選ばれ、世界をも視野に入れている。
今回の快進撃は通常のヒットの法則には当てはまらないのが特徴だ。まず、若い観客に受ける漫画やアニメの実写化ではない。「踊る大捜査線」のような人気ドラマの映画化でもない。「南極物語」ほどの大々的なメディアミックス戦略があったわけでもない。そしてタイパ時代に逆行する2時間55分という上映時間の長さ。これらの悪条件を乗り越えて観客の支持を集めたのは、やはり作品の力ということに尽きる。
吉田修一の同名小説を「悪人」の李相日監督が映画化。任☆(人ベンに峡の旧字体のツクリ)の家に生まれ、抗争で父を失った喜久雄(吉沢亮)は、上方歌舞伎の名手・花井半二郎(渡辺謙)に引き取られ、花井家の御曹司である俊介(横浜流星)とともに切磋琢磨しながら女形として芸の道を歩む。めきめきと頭角を現す喜久雄だが、歌舞伎は絶対的な世襲の世界。ところが、けがをした半二郎が代役に選んだのは息子ではない喜久雄だった―。
物語の軸となるのは、芸道における血筋と才能の相克だ。代役の本番直前、喜久雄は緊張で震えながら「俊ぼんの血をコップに入れてがぶがぶ飲みたい」と言う。これに対し俊介は「おまえには芸があるやないか」と応える。互いに自分にはないものを持っている相手への嫉妬と渇望を抱え、なおかつ相手があったからこその自分であることが身に染みて分かっている。この葛藤と、2人が歩む道の残酷な対比が、壮絶な人間絵巻となって繰り広げられる。
物語の魅力に加え、この作品が多くの人を引きつけたのは、何より吉沢、横浜をはじめとする俳優の演技、そして映像の力だろう。通常、観客にとって歌舞伎は舞台の上で披露されるものが全て。血筋も才能も目で見ることはできず、それらは芸という形で現れる。「国宝」でも「二人藤娘」「二人道成寺」などの演目をじっくりと、華やかに見せるが、板の上に立つ者だけが見ることができる世界をも存分に見せてくれる。
舞台に出る直前、「ほんなら花道で」と言い合って奈落で別れる2人。舞いながらタイミングを合わせる密やかなアイコンタクト。せりから登場したときに目の前に広がる客席の風景。「曽根崎心中」では、徳兵衛を演じた喜久雄がほほを寄せる、お初役の俊介の足がクローズアップに。物語と呼応して落涙を誘う名場面となった。
見たことのない世界に連れて行ってくれた映画は最後に、喜久雄自身が探していた景色を観客に見せてくれる。感情を揺さぶる梨園のドラマ、骨から鍛えたかのような俳優たちの奮闘、きらびやかな舞台とその裏側。なんともぜいたくな映画である。
反対に、見せないことによって強い印象を残す映画もある。「アイム・スティル・ヒア」は名匠ウォルター・サレス監督が母国ブラジルで起きた実話をもとにした作品。米アカデミー賞国際長編映画賞、ベネチア国際映画祭脚本賞を受賞した。
軍事独裁政権下にあった1970年代のリオデジャネイロ。元国会議員のルーベンス(セルトン・メロ)と妻エウニセ(フェルナンダ・トーレス)は海沿いの家で子どもたちと平和に暮らしていた。スイス大使誘拐事件で世の中が動揺していたある日、突然訪れた男たちによってルーベンスが理由も告げられず連行される。夫の行方を捜すエウニセだが、自身と娘も拘束されて尋問を受ける。程なく釈放されるが、夫の消息は分からないまま時が流れる。
映画は終始エウニセの視点で描かれ、ルーベンスがどうなっているのか、権力側が何をもくろんでいるのかなどは一切分からない。子どもたちにどう説明すればいいのか、このまま待ち続けているだけでいいのか。観客はエウニセと一緒に不安を募らせることになる。分からないということは恐怖だ。
まばゆい陽光の下、海岸で戯れる一家の姿を収めたホームビデオの映像が印象的だ。事件が起きる前の家族の明るい日常が、独裁政権の闇の深さを際立たせる。派手な絵になる事件の全貌を描かず、声高に権力を糾弾するわけでもないが、そのことがかえって暴力的なまでの理不尽さを強調している。強い意志と信念で静かな抵抗の姿勢を示したエウニセをトーレスが好演。
見ることができないものを見せる。見せないことで見せる。タイプが異なる2作品から、映画の魅力にはさまざまなかたちがあることをあらためて知った。(加藤義久・共同通信記者)
かとう・よしひさ 文化部で映画や文芸を担当しました。「国宝」は物語と映像に没入し、息をするのも忘れるほどでした。これからもそんな映画と出合うため、映画館に通います。
(おわり)