今夏はひどい猛暑が続いたが、その要因の一つが食べ物を無駄に捨てていることにあるという。コメ不足と言われながら米飯は大量廃棄され、日本全体で食品ロスのため年間4兆円が失われている。毎日の暮らしの中にある大きな社会課題を本書は教えてくれる。
コメ不足の中でも大量廃棄
2024年8月、国内のスーパーからコメが消えた。主食だけに多くの国民があわて、ようやく入荷した新米がそれまでの倍近くに跳ね上がっていたのにまた驚いた。ところが、「令和の米騒動」が深刻化する中で、まだ食べられるコメが大量に捨てられていた。
首都圏の百貨店、スーパー、コンビニなどの小売りや食品工場から出る食品ロスを、1日約40トン受け入れ、豚の飼料に加工している施設には、食品ロスの2割に当たる約8トンの米飯が運び込まれていた。ここだけで毎日、5万3000杯(茶わん)に相当するご飯が捨てられていた計算になる。
食品表示を定めた日本農林規格(JAS)法などで精米は「生鮮食品」として扱われ、スーパーには精米後1カ月強で商品棚から撤去する商慣習がある。撤去されたコメは、「従業員販売で安く売る」「フードバンクに寄付される」こともあるが、廃棄に回されてしまうことも少なくないようだ。
食品ロス問題ジャーナリストの著者はこう提言する。
「精米後2カ月以上たったコメを、値下げして販売する選択肢があってもいいのではないか。消費者の優先順位は味とは限らない。コメの供給を安定させるためにすべきは、まずコメの食品ロスを減らすことではないだろうか」
恵方巻で毎年10億円以上が…
恵方巻の大量廃棄も近年、問題になっている。豆まきに代わる節分の風物詩になりつつあるが、著者の調査によると恵方巻に関して、大手コンビニ3社の完売店舗率がここ数年激減し、23年の大量廃棄の損失額は全国で約12億8000万円。処分された恵方巻があれば256万人が1本ずつ食べることができたという。
「毎年10億円以上が食べられることなく廃棄される恵方巻が、はたして福を招くだろうか」と著者は嘆く。大量の売れ残りと廃棄を前提としたビジネスの典型で、コメ不足が続く中、実にもったいない。
コロナ禍でも日本は大量の食品ロスを重ねた。20年3月から全国の小・中・高校が休校となると、牛乳やパンなど給食用の食材は食品ロスに。翌月の第1回緊急事態宣言で大手百貨店が休業を始めると、デパ地下向けの食材も行き場を失った。
1年延期されて開催された21年の東京五輪では、ボランティア用弁当の約2割に当たる30万食が食品ロスとなった。無観客開催でボランティアの人数が減ったのに、弁当の発注数量を減らしていなかったというお粗末さだった。
自分の五感を信じて
各家庭で、おいしく食べられる目安を示す「賞味期限」が気になりがちなのが牛乳と卵だ。メーカーはあらゆるリスクを考慮して、ここまでなら大丈夫という期限を短めに設定している。だから保管方法を間違えない限り、賞味期限を過ぎたらすぐに悪くなるわけではない。
特に卵は生で食べられる期間として賞味期限が示されているので、「賞味期限が過ぎたら捨てるのではなく、早めに加熱調理して」、つまり安易に日付だけで食品ロスにすべきではないのだ。
外国では「賞味期限の啓発」が進んでいる。5年間で25%の食品ロスを減らしたデンマークでは、牛乳パックの側面一面を使い、自分の五感を信じて「目で見て、においをかいで、味を確かめてみて、食べても大丈夫かどうかを自分で判断しましょう」と呼びかけたメーカーもある。また英国の大手スーパー各社が22年、「期限表示は食品ロスを助長している」として、乳製品や青果物などの期限表示の変更や撤廃を表明した。
食品ロスが地球温暖化の“主犯格”
世界が食品ロスに取り組む姿勢を強めているのは、「もったいない」だけではない。深刻な地球温暖化、気候変動の“主犯格”に食品ロスが挙げられるようになったからである。ごみ処理場で食品ロスを多く含む生ごみを焼却処分するのに膨大なコストを使い、気候変動に悪影響を与える温室効果ガスを大量に出しているのだ。
ごみの回収が進んでいる日本には、焼却施設が1016カ所(24年)あり、実に世界の焼却炉の半分以上にもなる。焼却率は約80%と、経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で最も高い。生ごみの重量の80%は水分で燃えにくいため大量の燃料を使い、「日本は生ごみを燃やすことで気候変動に加担している」と著者は厳しく指摘する。
温室効果ガスの排出量が多い国順は、中米印露の4国に次いで日本。国連食糧農業機関(FAO)によれば、世界中の食品ロス合計を国に見立てると、中、米に次ぎ世界3位の排出源になる。
食品ロスは気候変動に大きな影響を及ぼしているにもかかわらず、これまで気候変動の問題を考えるとき、食品ロスの問題は見過ごされてきた。
国内の大手コンビニには年末や新春セールの売れ残り食品廃棄の費用に、上限3万円まで、本部が負担しているところもある。「売れ残っても廃棄費用は本部が出すから、加盟店は安心して発注しなさいということなのだろう」
労働・生活相談に関わるNPOの調査によると、食品を捨てることがストレスで退職する人が4割もいたという。大手コンビニの1店舗が捨てる食品は年間468万円。在日外国人が多く働いているが、まだ食べられる食品を粗末に扱う日本を、どう感じているだろうか。
「そもそも日本で食品に期限表示が入れられるようになったのは、ほんの50年ほど前のことだ。それまでは自分の五感に頼って、その食品が食べられるかどうか、判断するしかなかった」。腐ったものを無理に食べて体調を崩してはいけないが、大勢の人の苦労と貴重な資源やエネルギーを無駄にして、食べ物を粗末にするのは日本の文化に反する。
「食品ロスを削減することは、私たち一人ひとりが今日から始められる気候変動対策」。著者のこの提言も、日本をはじめ地球上の人たちが肝に銘じるべきである。
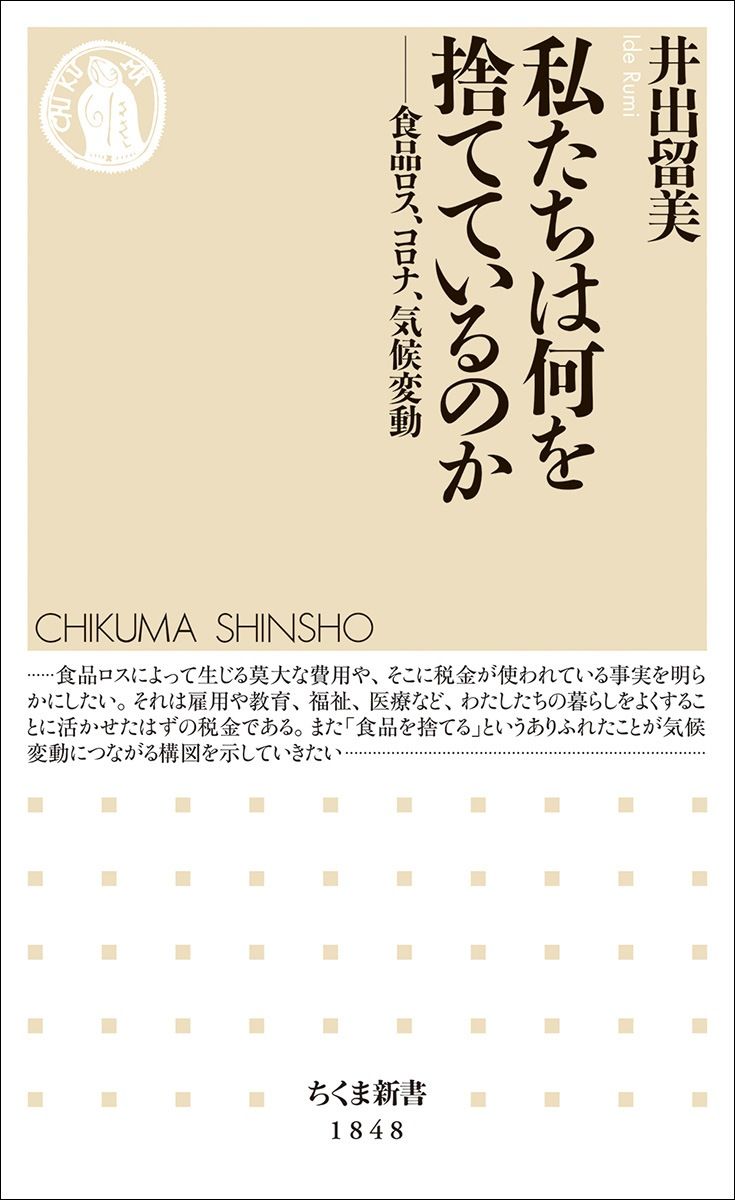
『私たちは何を捨てているのか―食品ロス、コロナ、気候変動』
発行日:2025年3月10日
ちくま新書:243ページ
価格:1012円(税込み)
ISBN:978-4-480-07677-9

