仙台で『BOOK TURN SENDAI』という少し大規模なブックイベントを企画した。
いわゆる、『文学フリマ』や『ZINEフェス』、歴史の長いもので言えば『コミックマーケット』や『デザインフェスタ』。そんなイメージだろうか。とにかく仙台、宮城、東北を中心に、全国各地からZINEの作り手や版元さん、ブックショップなど、紙の本に魅せられた人たちがたくさん出店してくれる。
そもそも僕は、20年以上編集者として本を作り続けてきたけれど、世の同業者のみなさんに比べて、作ってきた本の数が圧倒的に少ない。それは、僕がいわゆる出版社に所属するサラリーマン編集者ではなく、フリーランスの野良編集者だからということに加えて、出した本を自ら売りに行くところまでやろうとする癖があるからだと気づいた。
そもそも編集・デザインしたフリーペーパーを街中に配り歩いていたところから始まり、値段のついた本を自費出版的に作り始め、自ら書店営業をしながら本を売っていた20代。そして30歳を超え、いよいよ商業出版を経験したのはいあから約20年前のこと。それがリトルモアから発刊していた『Re:S(りす)』という雑誌だった。人生初の商業出版に、出版社から本を出していただくということは、こんなにもありがたいものかと、感動した。
具体的な恩恵はいろいろあるが、もっともありがたかったのは、流通のこと。つまり、僕が売ってくださいと頭を下げて店をまわらなくても、作った雑誌が書店に並ぶ。そのありがたさったらなかった。取次さんと言われる、本を版元から本屋さんに取り次いでくれる会社のおかげで、僕が自分で書店まわりをしなくても、雑誌『Re:S』を全国の書店さんに並べてもらえるのだ。そんな素晴らしいことはないと思った。
しかし、僕というやつはどうしてこんなに厄介な生き物なのか。ただそれを素直に喜んでいればいいのに、そのうち、流通を委託するから読者の反応がわからないんだとか、どこで売られているか把握しきれないとか、そういったことを考え始め、最初こそ浮かれていたけれど次第にモヤモヤが広がり、挙げ句の果てに「すなおに売る」という一体誰に向けてるんだか謎すぎるタイトルの、行商特集号を作った。
当時未踏だった鹿児島で『Re:S』を行商をする模様を記事にしたその特集は、いま読み返してもなお、得られるものが多いから、若いときの勢いとは素晴らしいもんだと我ながら感心する。50を超えたいまでは、到底作れない一冊。

とにかく僕はずっと、そうやって作った本を自ら売ることにこだわってきた。いやこだわったのではない。自分で売りたいと思ってきた。それはなぜか? 答えは簡単。楽しいからだ。本を作りたいと思うのは「読んでもらいたい」「届けたい」という気持ちの現れだ。いまはわざわざ本など作らなくても、SNSやブログ、YouTubeなどでいくらでも発信できる時代だけれど、短文ゆえのすれ違いから炎上したり、意図せぬ人に届いてしまうことに気を揉むばかりのネットの世界とは違って、紙の本は、作るまでのプロセスの長さや面倒さが、かえってさまざまな自制を生むからか、炎上リスクも低い。特に商業出版ではないZINEは、売るところまでしっかり把握しやすいので、互いに顔が見える安心感がある。現代においてはそのことがZINEブームを加速させているようにも感じる。
そんなふうに、身の丈や、適度な規模感をベースにした本づくりは、地域編集の文脈においてとても有効で、ZINEづくりをとおして何かをPR したり、物事を推し進めたり、関係性を作り出したりする地域編集者たちがいまやたくさんいらっしゃって、そのなかでも僕が特に面白いなあと感じたり、そのクオリティの高さに驚いたりした人たちに声をかけていたら、主催者特権で用意していたディレクションブース50ほどが一気に埋まってしまった。あくまでも呼びかけただけなのだが、ほぼ全員が出たいと言ってくれて、交通宿泊費も自腹で仙台までやってきてくれるこの現象はいったいどういうことだろうと思う。
なかには、熊本の編集者・福永あずさや、長崎県佐世保のREPORT SASEBOチーム、福岡久留米のグッチョなど、このミシマガ連載でも記事にさせてもらってきた人たちもいて、まさに地域編集者の祭典な意味合いも強まってきた。いまから楽しみで仕方がない。
そして最後に書いておきたいのが、そもそもなんで仙台なのか? という問いへの答え。それは東日本大震災直後の2012年頃に遡る。兵庫県に住んでいる僕を、当時、仙台に呼んでくれた『BOOK BOOK SENDAI』というイベントがあった。そのスタッフのみなさんのおかげで、それまでは、リトル東京な支店経済の象徴だった仙台のイメージがガラリと変わった。アテンドしてくださる人が変わると街の見え方はこんなにも変化するものかと思い知った僕は、その経験をもとに、ずっと地方を旅し続けている。旅する編集者として活動を続ける僕にとって、仙台のまちはとても大きな存在だったのだ。
しかしこの10年ほどのあいだ、かつての『BOOK BOOK SENDAI』のような大きなブックイベントを仙台で見ることがなくなってしまっていた。時代の流れもあって、ブックイベントをやるなら仙台のような大きな街ではなく、ちょっと外れの趣のある街で小さく始めるほうが、いまの時代の空気にフィットする。そのことはとてもよく理解できる。しかし僕にとっては仙台という大きな街だからこそやれることがあって、しかもそれを何かのフォーマットではなく、一からこの街で立ち上げることの必要性を感じていた。
かつて『BOOK BOOK SENDAI』に関わっておられた方が僕にギフトしてくれたように、一見、都会的で地方色の見みえづらい仙台の、一本向こうの路地の魅力や、足元にある深い歴史の地層に気づく、そんなきっかけとなるイベントを立ち上げたい。それが僕の思いだった。
地方と都会の二極化が拡大するなかで、仙台のような、地方と都会のあわいのような存在が果たすべき役割があると信じている。中世日本、蝦夷たちを侵略した宮城多賀城の歴史からもわかるように、宮城はさまざまな意味で東北の入り口であり、中央と地方の境界の街でもある。東北を愛するものとして、その風土を感じ取ってもらう入り口としては、仙台ほど間口の広い土地はない。そんな気持ちで僕は、遠く仙台での開催を決めた。
なにはともあれ、『BOOK TURN SENDAI』は、とてもエポックなイベントになるに違いない。おそらく抽選になってしまうけれど、一般公募枠の締め切りが9月15日にせまっているので、我こそはという方はぜひ申し込みをしてほしい。
BOOK TURN SENDAI

1974 年兵庫県生まれ。編集者。有限会社りす代表。雑誌「Re:S」編集長を経て、秋田県発行フリーマガジン「のんびり」、webマガジン「なんも大学」の編集長に。
自著に『風と土の秋田』『ほんとうのニッポンに出会う旅』(共に、リトルモア)。イラストレーターの福田利之氏との共著に『いまからノート』(青幻舎)、編著として『池田修三木版画集 センチメンタルの青い旗』(ナナロク社)などがある。
編集・原稿執筆した『るろうにほん 熊本へ』(ワニブックス)、『ニッポンの嵐』(KADOKAWA)ほか、手がけた書籍多数。
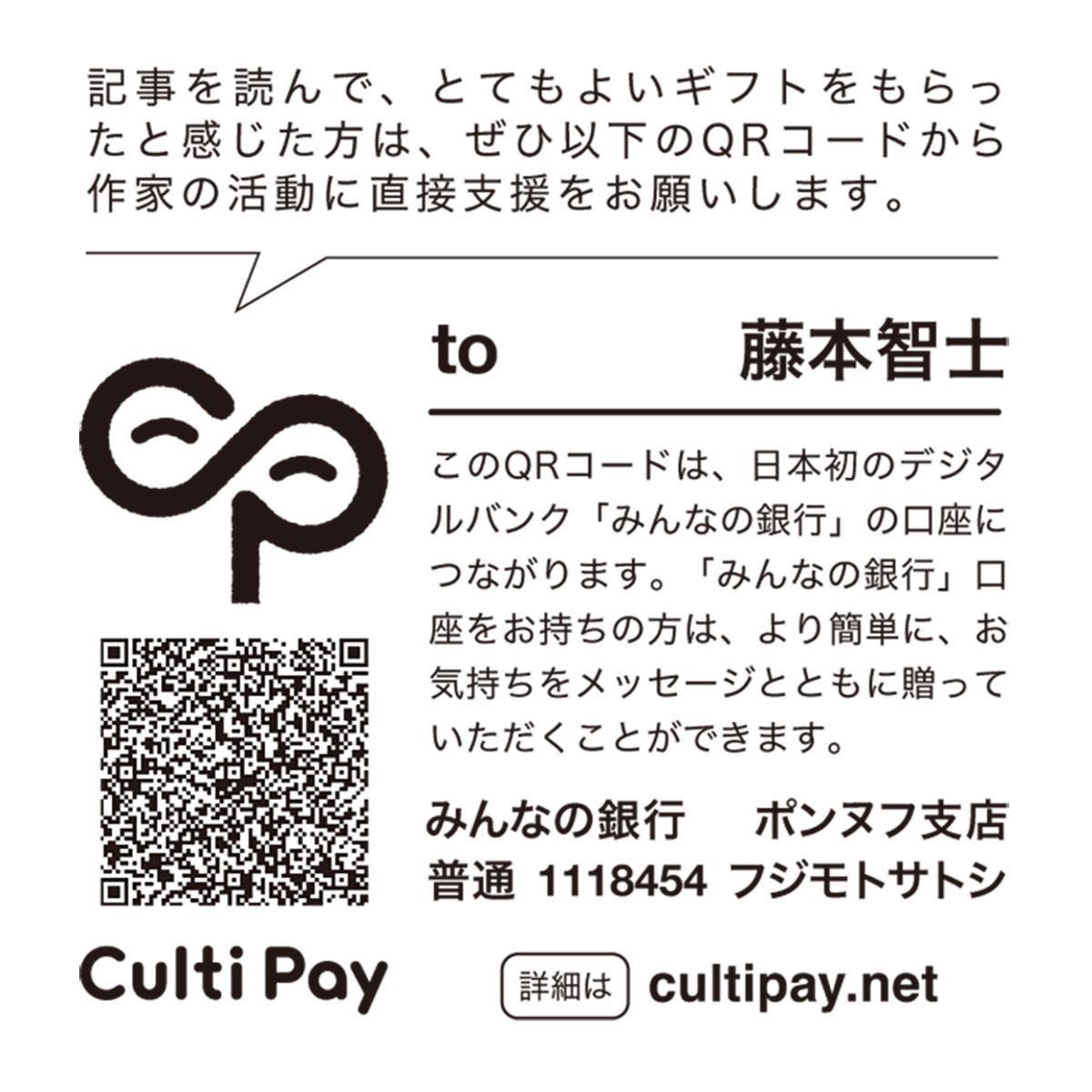
編集部からのお知らせ
【藤本智士さん出演】新著『日々是編集』
出版記念トークが続々!
『日々是編集』の出版記念トーク予定です!
9/10(水)18時半〜
福島県福島市『ブックカフェコトウ』9/11(木)19時〜
群馬県高崎市『REBEL BOOKS』9/17(水)19時〜
鹿児島県鹿児島市『ライカワークラウンジ』9/23(火・祝)17時〜
岩手県紫波町『YOKOSAWA CAMPUS』お近くのかたぜひ???? pic.twitter.com/ZqvW5hm9jc
— 藤本智士 (@Re_Satoshi_F) September 6, 2025
『日々是編集』

