「サッカーファンのための読書案内」は、サッカーにまつわるニュースや話題とともに、一冊の本を取り上げる連載だ。本を“補助線”として、サッカー界のトピックを多角的に読み解いていく。
シーズン途中、監督交代のニュースが各地で聞こえる時期がやってきた。監督交代に「ブースト」は存在するのか。では、そのブーストを引き起こすには何が必要なのか。今回は、ある一冊を通してこの問いを考えていく。
コンフォートゾーンとモチベーションの「罠」
6月、Jリーグ各カテゴリで複数のクラブが監督交代を発表した。J2のレノファ山口もそのひとつだ。志垣良監督との契約を解除し、クラブOBの中山元気コーチが新監督に就任した。このニュースを受けて書かれた住田優さんのnoteが非常に興味深い。
監督交代(あるいは監督解任)ブーストという言葉がある。監督を代えることで成績が上向いたり、チームが立ち直ることを指す。住田さんのnoteが特徴的なのは、このブーストの「有無」ではなく、それを起こすには何が必要かを、認知科学の観点から掘り下げている点にある。
※住田さんのX:
https://x.com/MasaruSumida
※住田さんのnote記事:
https://note.com/sports_life_lab/n/n2f552557e23c?sub_rt=share_b
記事を読んで、強く結びつきを感じた本がある。組織心理学者アダム・グラントの『THINK AGAIN』だ。思い込みを手放し、再考し、発想を転換する「知的柔軟性」について論じた本である。
冒頭では、山火事を食い止め切れず炎が迫る中、とっさに周囲の草を燃やし、その場にかがみ込んで生き延びたレスキュー隊長と、その判断に逆らい逃げようとして命を落とした隊員の話が紹介される。
極限のストレス下では、人は経験や訓練に基づいた直感に頼る。たとえば、レスキュー隊員にとって火は「つけるものではなく消すもの」であり、「向かうものではなく逃げるもの」である。その常識に逆らうことは難しい。迫り来る炎の前では、思考を再考したり他者と話し合ったりする余裕は一切ないのだ。
ここまでの極限状態ではないにせよ、サッカーの試合もまた「思考の余白」がほとんどない。ピッチ上でいちいち判断を話し合っていられない。選手がとっさに下す判断の多くは、すでに身体に染みついた習慣に基づいている。だが、その習慣が現状に合っていなければ、良い結果にはつながらない。
住田さんは「コンフォートゾーン」という言葉を紹介している。人が安心して活動できる心理的領域のことだ。この「慣れ親しんだ領域」が、実は「現状が変わらない」原因になっている恐れがある。
また、「モチベーション」という言葉にも注意がいる。多くの場合、モチベーションはコンフォートゾーンに引き戻す力として働く。つまり、「やる気」を高めることが、かえって現状維持を強めてしまう可能性があるのだ。
柔軟性を呼び覚ます「科学者モード」
監督交代とは、コンフォートゾーンの外にチームを強制的に押し出す行為なのではないか。チームに適度な刺激を与え、リセットを促す。つまり「現状を維持させないよう環境から働きかける」行為が、監督交代なのである。
だが、環境が変わったからといって、チームが変わるとは限らない。真に重要なのは、環境の変化がチームの思考を変えられるかどうか。選手やスタッフが、自らの思考を再考し、発想を変えられるかにかかっている。
人は無意識に「牧師・検察官・政治家」の3モードを切り替えながら考え、語っているという。信念が揺らぐと「牧師」となり、それを守ろうと説教を始める。他者の矛盾を見つければ「検察官」となり、反論を構築する。支持を得たいときには「政治家」となり、都合の良い言葉を並べる。
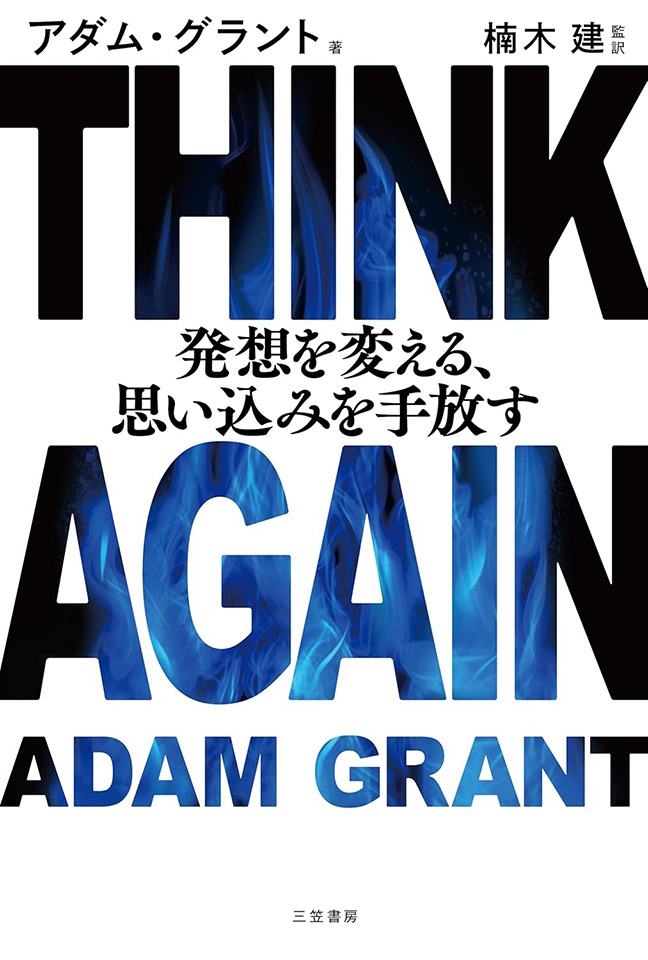
この3つのモードは人間に備わった自然な機能で、なくすことはできない。本が強調するのは、この3つに加えて「科学者モード」を持つことの重要性だ。科学者のモードとは、自らの知識を疑い、知らないことに仮説を立てて深掘りする姿勢である。ここで必要なのは「偏見を持たないこと」ではない。「意識的に偏見を持たないよう努めること」だ。
脳の処理速度が速い人は「頭が切れる」とされるが、それだけでは柔軟な思考はできない。重要なのは、思考の敏捷性(メンタル・アジリティ)だ。
慣れた環境に固執しすぎると、組織内の人間は牧師・検察官・政治家モードで現状維持に動きがちだ。監督交代という外的環境の変化によって、メンバーの中にある「科学者の側面」が呼び覚まされ、固定観念への疑問が生まれるのではないか。
本書には、再考できる人とはどんな人か、相手に再考を促すにはどうすればよいか、再考が根付いた組織とはどのようなものか──そうしたヒントが多く含まれている。これは、サッカークラブが柔軟な対応力を持つ組織へと進化していくうえで、大いに参考になるはずだ。ただし「長い目で見たときには」だが。
交代前からブーストの結果は決まっている??
監督交代ブーストに求められるのは、目先の結果である。数年単位で文化を築く余裕は、ほとんどのクラブにはない。監督交代があると、僕らはつい新監督に期待を寄せてしまう。そして、うまくいけば監督の功績、失敗すれば監督の責任という構図が強調される。
だが冷静に考えてみると、代わったばかりの監督が短期間でできることは、サポーターが想像しているよりもずっと限られているのではないか。ブーストがかかるかどうかは、交代する前から実は決まっているのかもしれない。本当に重要なのは「どんな監督か」ではなく、「どんな選手がいるか」だ。「科学者モード」を潜在的に持ち合わせている選手がどれくらいいるかが、ブーストに一番影響するのではないだろうか。
コンフォートゾーンに固執した環境では、それらを守る方に働き、疑い再考する方に働かない。だからこそ、監督交代は一時的にでもコンフォートゾーンを壊し、選手の中に眠っていた「科学者モード」を呼び覚ます効果を持つ。その結果として、チームが柔軟な発想を取り戻し、新たなアイデアを受け入れる組織へと変化する。これこそが、監督交代ブーストの仕組みなのではないか。
そう考えたときに気になるのは、監督交代での「内部昇格」という選択だ。冒頭で話題にあげたレノファ山口や、今季最も監督人事で揺れたであろう横浜F・マリノスなどはその道を選んでいる。
前任者が作ってきたカラーや環境を変えるという意味では、内部昇格であろうが外部招聘であろうが大差ない場合もある。ただ、広い視点で見れば、内部昇格の監督は「クラブの環境に慣れ親しんだ人」である。クラブの常識に知らず知らずのうちに縛られ、本人自身がコンフォートゾーンを抜け出せていない可能性もある。
だからといって内部昇格がブーストに不向きというわけではない。監督という立場に変わること自体が、当人にとっては環境の変化だ。その変化を通じて、監督自身の柔軟性が呼び覚まされるならば、チームに変革をもたらす存在になり得る。
山口に前後して、アルビレックス新潟やFC岐阜が監督を交代し、モンテディオ山形が暫定監督を挟んで新監督を招聘している。当のクラブを応援しているサポーターに向けて伝えられるのは「新監督がすべてを変えてくれるなんて、あり得ない」ということだ。
新監督が主にもたらせるのは、リセットしてコンフォートゾーンを抜け出す「きっかけ」だ。そのきっかけをつかめるかは、交代前からチームにいる選手にかかっている。現状維持から変化へのチャレンジを後押しする応援や見守りが胃の痛い思いをしているサポーターにできることかもしれない。
【取り上げた本】アダム・グラント『THINK AGAIN』
https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100581200
【取り上げたニュース】
【中山元気監督就任】レノファ山口の「困難」を「飛躍の機会」に変える科学的アプローチ
https://note.com/sports_life_lab/n/n2f552557e23c?sub_rt=share_b
【プロフィール】辻井凌(つじー)
書評家・文筆家。北海道コンサドーレ札幌とアダナ・デミルスポル(トルコ)を応援している。キタノステラにコラム『日常からコンサドーレ』を連載中。
◎note:https://note.com/nega9clecle
◎X(Twitter):https://twitter.com/nega9_clecle

