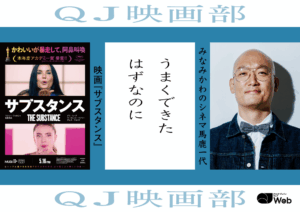音楽ライターの松永良平が、さまざまなアーティストに“デビュー”をテーマに話を聞く「あの人に聞くデビューの話」。この連載では多種多様なデビューの形と、それにまつわる物語をじっくりと掘り下げていく。前回に引き続きBialystocksの甫木元空(Vo)をゲストに迎えお届けする。美大入学を機に映像の世界にのめりこむようになった甫木元。そんな彼が音楽制作を本格的に始めるきっかけとなったのは、誰あろう恩師・青山真治監督からの、ふとしたひと言だった。ほどなくして甫木元はBialystocksを結成。音楽制作を通じて、自らの表現者としての核心に、はからずも向き合うこととなっていく。
取材・文 / 松永良平 撮影 / 小財美香子
自分の中では「残す」という行為自体に意味がある
──インタビュー前半は音楽ナタリーではなく、映画ナタリーなんじゃないかと思うほど、映画監督・甫木元空のデビュー前的な内容でしたけど、最後にようやく音楽の話が入ってきました。ここからは甫木元さんの音楽デビューにもフォーカスしていきます。オリジナル曲はいつぐらいから書き始めたんですか?
高校生の後半ぐらいです。The Beatlesの「Hey Jude」をギターで弾いてみよう、みたいな音楽の授業があったんですけど、それがきっかけで徐々にコードを覚えて、誰に聴かせるともなく曲を作るようになりました。ちゃんと人に聴かせたという意味では、多摩美の卒業制作で作った映像に曲を乗せたときですね。それがあったから「はるねこ」(2016年)の音楽を作るときに、ちゃんと曲を作って歌ってみようということになったので。
──そこまで、この声をほぼ誰にも知られずにとっておいた、ということですよね。そもそも人前で歌うつもりがなかった?
そうですね。特段、音楽の成績がよかったわけでもないですし、カラオケに行って歌ったりしても別にそれほどいいリアクションがなかったんですよ。「フツーかな」ぐらいの反応でした。
──けれども青山真治監督は「その声を残しておいたほうがいい」と言った。
いや、「記録に残しておいてもいいんじゃないか」ぐらいの感じだったと思います。

甫木元空(Bialystocks)
──でも、そう言われた時点で、歌詞も含めて、すでに甫木元さんのオリジナル曲がいくつかできていたんですね。
それまで自分の中で、何かを表現するうえで核になるようなものが何もないなと思ってたんです。ゼミの人たちは、映像作品を作るうえで物語を作ることができたり、表現の核になるものをちゃんと持っていた。でも自分には何もない。大学時代は「何を表現したらいいんだろう?」とずっと思っていました。特に実験映画という手法では視覚的な面白さは追求できても、核がないとすごく空虚な感じがした。表現において自分の中で大きな転機になったのは、父親が亡くなったことだと思うんです。父に対して自分は何も残せなかったなと思っていたんですが、僕が生まれるときから記録として残されていた膨大な映像を再編集しながら、その記録へのリアクションとして曲ができた。そのときに「あ、こういうことだったらできるかもしれない」と思ったんです。映画でも音楽でも小説でも、自分の中では「残す」という行為自体に意味がある。誰かといた痕跡を残すみたいな行程です。僕の場合は、父親が残したホームビデオを編集して、作品として残すことが音楽制作の原点にもなった。
──そこからBialystocksが生まれたわけですもんね。
でも、それをちゃんとやるためには自分のバックボーンみたいなものを見つめないとダメだとも思いました。それで、母に病気が見つかったこともあって、「はるねこ」がひと段落したぐらいで療養のために母の実家のある高知の四万十に移住したんです。そもそも自分のルーツというか、自分の足元にあるものはなんなんだろうというのを調査する目的もありました。民俗学者、宮本常一の本「忘れられた日本人」(1960年刊行。日本の地方社会に根付く伝承を、市井の人々の語りを蒐集することで克明に書き留めた労作)を踏襲したわけじゃないですけど、地元に住んでいる僕のおじいちゃんをはじめ、いろんな人にそれまでの人生を聞いて回りました。自分のルーツである高知という街はどんなところなのかを調べるフィールドワークみたいなことをして。その中で、高知にもビキニ環礁での水爆実験で被ばくした人たちがいたと知りました。そんなふうに残されていたものから立ち上がってきたものが、Bialystocksのミニアルバム「Tide Pool」(2022年)やメジャー1stアルバム「Quicksand」(2022年)収録曲の歌詞には反映されています。高知県須崎市にある「すさきまちかどギャラリー」の人たちと仲よくなって、そこで出会った画家の竹崎和征さんが「Tide Pool」「Quicksand」のジャケットを描いてくれました。そういうことも、その後の活動につながっていきましたね。

高知で行った映画「はだかのゆめ」撮影時の様子。
Bialystocks「Tide Pool」
Bialystocks「Quicksand」
ある歌を誰かが道端で歌ったら、それはその人の歌になる
──僕がBialystocksの存在を知ったのが、まさに甫木元さんが高知にいた頃です。VIDEOTAPEMUSIC、浮と港の3組が出演していた洲崎市のライブイベントだったと記憶してます(2021年11月27日開催の「すきま たゆたう」)。ライブは観に行けなかったけど、甫木元さんは高知で映画を撮ったりしている、すごく才能がある人だと人づてに聞きました。その時点ですでに自主制作したアルバム「ビアリストックス」(2021年)は出ていて、そこからあれよあれよという間に翌22年にはメジャーデビューを果たして。
僕も驚きました。最初にポニーキャニオンから連絡が来たときは詐欺メールかと思いましたし(笑)。あの頃はまだコロナ禍でライブもほとんどできてなかったけど、1stアルバムの音源で判断してくれたんだと思います。

甫木元空(Bialystocks)
──契約にあたって何か条件は出しました? 映画の製作は続けたいとか?
特にないですね。最初から自由にやらせてもらってます。メジャーレーベルに対して抵抗感があったわけではないですし、むしろ自主制作で作品をリリースして、制作費や宣伝の面で限界を感じていましたから。単純に今までやったことないことをやれたら面白いなと思いました。これからマスを狙っていこう、みたいな感じでもない。とりあえず、やってみようということですね。
──インディペンデント映画や舞台の世界を知ってるから、見てきた世界のレンジは広いかも。
メジャーとインディーズの境界線みたいなものは曖昧になっているなとは思います。特に、音楽を聴いてる側の人は、もはやそういう線引きに全然興味がないでしょう。映画の世界もそうですよ。昔は商業作品とミニシアター系とか棲み分けがあったと思うんです。低予算でも「これはミニシアター系の映画だよね」と作品のよさを見つけてもらえた。でも今は、発表する場が平等に設けられた分、かなり残酷な世の中になっていて、単純に「この映画、予算がなかったんだろうな」で片付けられてしまう。自分が作った音楽も「音圧が低い音楽だな」で片付けられちゃうかもしれない。
──とはいえ、Bialystocksの音楽は最初からインディー / メジャーの垣根を越える強度があったと思います。
音楽に関しては、強度の部分も菊池(剛)さんが作るアレンジで保たれているところがあると思います。僕が作るメロディと歌詞に関して言えば、出たとこ勝負ですから(笑)。小学生のときからそうなんですけど、頭で考えて何かをやるというより、とにかくやってみる、みたいな感じ。崖から突き落とされる感じというか。
──でも、そこにはちゃんと構築性がありますよ。
そういう意味では、映画の現場で、いろんな人の作品で助監督をやれてよかったなと思います。単なる自己流ではなく、いろんな監督の現場を見ることによって、映画が作り上げられていく過程を学ぶことができました。Bialystocksの場合で言うと、菊池さんがいろんな要素を整理整頓してくれるおかげで、音楽が僕の自己満足ではなく、すごく開かれたものになっていく。共同作業という点では映画も音楽もすごく似ているなと思います。自分の視点だけを鋭利にすれば、それはそれですごいものが生まれるのかもしれない。でも他者と共同作業することで、もっといろんな人の視点を作品に入れられると思うんです。例えば、歌に関して言えば、ある歌を誰かが道端で歌ったら、それはその人の歌になる。いろんな人がかき混ぜてくれることによって、自分が思ってもいないところに話が転がっていくという表現の開かれ方が絶対にあるし、そういうことがすごく楽しい。いつかは職人みたいにずっと何かを研ぎ続けるみたいなすごさも追求してみたいんですけど、今の自分の興味としては、核となるものはブレさせずに、いろんな要素を乗せつつも、引き算でできあがってるものに面白さを感じていますね。

Bialystocks「Kids」ミュージックビデオ撮影中の様子。

Bialystocks「Kids」ミュージックビデオ撮影中の様子。
青山真治監督から受け継いだバトン
──自分ではない誰かにかき回されたり、引き算される表現を求めたりしているというのは興味深いですね。甫木元さんが監督を務めた新作映画「BAUS 映画から船出した映画館」にも、そういう世界観が反映されていたように感じます。
ありがとうございます。
──あの映画は、もともと生前に青山真治さんが残していた脚本があって、そこから甫木元さんがバトンを受けてリレーで完成させた作品でした。
青山さんが考えていた脚本がどこに着地するかを、生前にちゃんと聞く機会がなかったんです。ただ、大河ドラマとか朝ドラ的な、長い歴史の伝記映画を青山真治がやるんだということに単純に驚きました。あれほどのキャリアがあっても、まだ自分の型を壊して破壊と構築を続けていこうとしていた。そういう実験的な意思は引き継いで作品に入れられたらと思っていました。とはいえ、青山さんのビジョンを受け継いだだけの作品になってしまってはいけないし、中途半端にしたくなかった。自分だったら何ができるんだろうと考えましたね。

「BAUS 映画から船出した映画館」撮影現場のオフショット。 ©︎本田プロモーションBAUS / boid
──ある意味、青山真治+甫木元空という連名映画作家のデビュー作になっていると思いました。デュエットというか。
青山さんの原稿には「90年にわたって映画館に住み続けた家族3代にわたる物語を、世界中の映画を愛する人たちに語りかけるように映画化したい」と書いてあったんです。そもそも、この映画の原作は、2014年まで吉祥寺で営業していたバウスシアターの館主の方が、おじいさんやお父さんから口頭で伝えられた話が元になっている。でも口で伝えられたことって、たかが100年前の話だけど話が盛られたりとかする。歴史ってこうやって間違ったりしながら作られていくんだなと思いました。だけど、それが面白いんですよね。僕も、青山さんからバトンを受け継いだと言ったら大袈裟ですけど、青山さんの脚本を読んで、その物語、曖昧な記憶を他人に伝えていく──口伝された物語を僕が友達に伝えるように、映画化するのが一番いい姿勢なのかなと思いました。それは映画作りを通じて現実的なものと向き合うことでもあるというか。
──その話って、卒業制作でお父さんのホームビデオをひたすら編集していた甫木元さんと近いですね。
ある1人の撮影者、語り部が残した者が家族の中で受け継がれていくという部分では同じかもしれないですね。ホームビデオって撮影者は出てこないんですよ。でも、編集を始めたらカメラを向けている父親の視線を感じるようになって、そしたら全然違う映像に見えるようになりました。自分の中で意味合いが変わっていった。「BAUS」ではどういう視点で物語を見つけるのかすごく悩みました。井の頭公園のベンチに座って音を聴いたり、動画を撮影しても、ケンカしてるおじいちゃんとおばあちゃんがいたり、カップルがアヒルボートを漕いでいたり、路上ミュージシャンが謎のフォークを歌ったりしている現実というのは混沌なんです。そうすると、ひっちゃかめっちゃかなんですよね(笑)。
──なるほど。
でも、普段生活している中でカメラを回すということは、カオス、混沌の中で何かを選択して切り取るということなので。僕が映っていたホームビデオでも、どういうまなざしで撮影しているのかを感じる。父が何を撮っているかが明確だったから、僕も膨大な映像を編集できたと思うんです。
──もしかしたら甫木元さんの作る曲に関しても、ある種そういう部分が大きいかも。「出たとこ勝負」とおっしゃってましたけど、それは出てきてしまった言葉とメロディで、自分がそのとき何を感じていたかを知るということでもある。
そうですね。
──普通とは逆なのかも。こういうことを感じたから、言いたいから、曲を書くというプロセスではなく。
僕の場合、映画も曲もきっかけは同じかもしれないですね。とりあえず歌ってみる、みたいなところからしか曲を作ってきてない。たまたま出てきた言葉から歌詞を書いたり。できあがって「こういうことだったのか」というのを改めて知る、みたいなところがある。
──ある意味、映画や曲を作るたびに、ずっと表現デビューを繰り返しているという。
自分の中に決まった型があるわけでもなく、できあがったものから教えてもらうということをずっと繰り返している気がします。
──改めてお聞きします。甫木元さんは自分の中で、デビューという線をどこに引きます?
難しいですね。何をもってデビューなのか? でも、青山さんがプロデュースしてくれた「はるねこ」で音楽と映画を同時に形にできたし、菊池さんとも出会えた。自分の中では、やっぱりそこが出発点なんじゃないかと思います。

甫木元空(Bialystocks)
甫木元空(ホキモトソラ)
菊池剛(Key)との2人組バンドBialystocksのボーカリスト。Bialystocksは映画監督でもある甫木元の初監督作品「はるねこ」の生演奏上映をきっかけに、2019年に結成された。フォーキーで温かみのあるメロディと、ジャズをベースに持ちながら自由にジャンルを横断するサウンドの組み合わせは、普遍的であると同時に先鋭的と評される。2021年にインディーズ1stアルバム「ビアリストックス」を発表。2022年11月にメジャー1stアルバム「Quicksand」をポニーキャニオン内のレーベルIRORI Recordsよりリリースした。音楽家と映画監督としての活動を併行して行っており、2025年3月には、青山真治の企画を引き継ぐ形で脚本・監督を担った映画「BAUS 映画から船出した映画館」が公開された。
Bialystocksオフィシャルサイト
Bialystocks(@bialymusic) | X
Bialystocks(@bialystocks) | Instagram
松永良平
1968年、熊本県生まれの音楽ライター。大学時代よりレコード店に勤務し、大学卒業後、友人たちと立ち上げた音楽雑誌「リズム&ペンシル」がきっかけで執筆活動を開始。現在もレコード店勤務の傍ら、雑誌 / Webを中心に執筆活動を行っている。著書に「20世紀グレーテスト・ヒッツ」(音楽出版社)、「僕の平成パンツ・ソックス・シューズ・ソングブック」(晶文社)がある。
この記事の画像・音声(全11件)
読者の反応
コメントを読む(9件)
Bialystocksのほかの記事