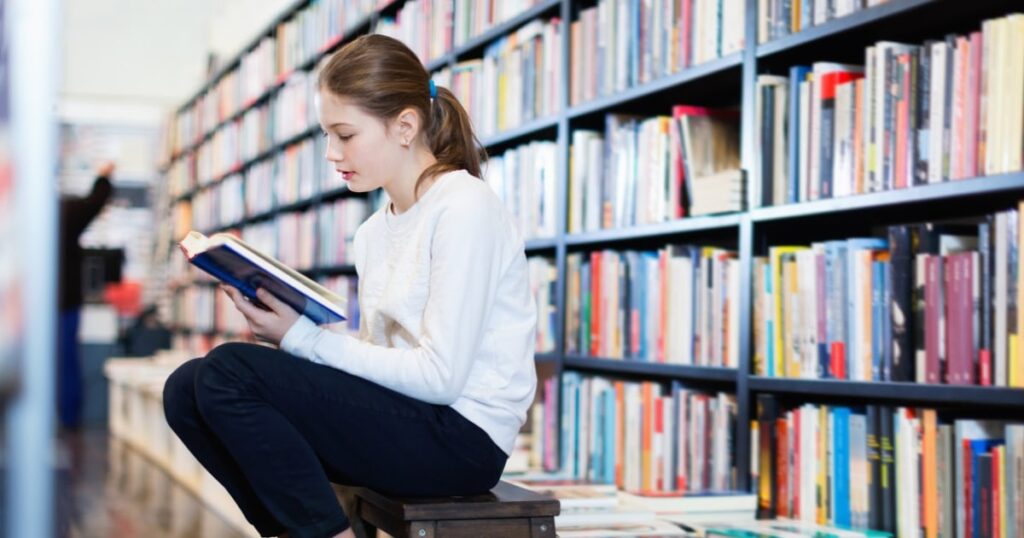人気歌人・木下龍也さんの新刊『すごい短歌部』(講談社)が話題を集めています。
文芸誌「群像」に連載された本書は、毎月読者からの短歌を募り、木下さんが選んだ短歌の「面白さ」を分かりやすく講評するとともに、木下さん自身が短歌を作っていく過程をまるごと明かした、注目の短歌エッセイ。
本書の刊行を機に、三省堂書店神保町本店の書店員である纐纈 望(こうけつ・のぞみ)さんに、木下龍也さんの短歌のどこが「すごい!」のか、その魅力を読み解いていただきました。

私は普段から詩歌というジャンルの敷居を下げたいと思いながら、書店でできることはないか日々模索している。その世界を専門としていない“いち読者”だからこそ、詩歌の入口で迷っている人たちに寄り添える方法があるのではないかと思っている。
ある時、書店で詩歌の棚に向かう人は、もともとそのジャンルに関心のある人だけであることに気が付いた。世の中には素晴らしい詩歌の本が存在しているにもかかわらず、そのジャンルの棚に行かない人たちにとっては、その本は存在していないも同然なのである。
詩歌のジャンルに限った話ではないが、本を届けたい人に届けられないもどかしさを常日頃から感じていた。そこである時、カプセルトイを見かけるとついまわしてしまう(私自身がそうである)心理を利用して、歌集を集めたコーナーに無料の「短歌ガチャ」を設置してみたことがあった。カプセルの中に一つずつ、私の好きな木下龍也さんの短歌を入れて、おみくじのように楽しんでもらう仕掛けだ。
するとどうだろう、通りかかる8割くらいの人がガチャをまわしてくれる。そうして出会った短歌を入口に、そのうちの6割くらいの人は歌集を手に取るまでに至っていた。歌集はまったく読まないという元コミック担当スタッフも、
「読み終えて漫画の外にいるきみもだれかを救う主人公だよ」
という木下さんの歌に心惹かれ、この一首が収録されている『あなたのための短歌集』(ナナロク社)を購入したのだと教えてくれた。木下さんの短歌には一瞬にして人の心を奪う力があるのだと、身をもって感じた瞬間であった。
31音で「世界を変える」短歌の力
木下さんの短歌にはその一首だけで、見た人の世界を変えてしまう力がある。世界が広がる、という表現よりも、そこにたしかにあったのに見えていなかったものたち、それまでただ通り過ぎていたものたちにスッと驚くようにピントが合い、それらに輪郭を持たせてくれる、そして世界がよりクリアに見える、というたとえのほうがしっくりくるだろうか。
木下さんという他者の目を通したほうが、自分の世界の解像度が上がるというのもおかしな話である。でも木下さんの短歌は、見たはずなのに見えていなかった風景も、あの感情も、自分で思い出すよりも鮮やかに蘇らせてくれる。知っているはずの感情も、改めて短歌として差し出されるとなぜか心を打つ。「ことば」の持つ力が31音の中に濃密に詰まっているように感じてたまに恐ろしくなるほどだ。
以前、木下さんの短歌について以下のように書いたことがある。
「本を読んでいると、大切な誰かや自分のために贈りたいと思う、お守りのような「ことば」と出会うことがあります。(中略)大切な誰かや自分に贈りたいと思う「ことば」を、と考えた際に真っ先に思い浮かんだのは歌人・木下龍也さんの短歌でした。実際に木下さんの歌をお守りのように抱えて、日々を過ごしています。きっとそうして心に小さな灯りをともして生きている人はたくさんいると思うのです。」
あなたの短歌を心の支えにして生きています、とはいまだ一度も木下さんにお伝えすることはできていないのだが、私にとって日々の一部となっている歌がある。(いくつかあるのだが)あえて一首選ぶとするならば、
「読み終えてややふっくらとした本にあなたの日々が挟まれている」(『オールアラウンドユー』ナナロク社)
学生時代から何度も何度も繰り返し読み返している本は、形が崩れて空気を孕みもう綺麗に閉じることすらできない。あぁ、大切に読んであげられなくてごめん、と感じていた罪悪感をこの歌が少し軽くしてくれたように思う。この歌はこの先も本を開く度に、私の胸をあたたかくしてくれるのだと思う。
「短歌の読み方」を教えてくれる一冊
そんな木下さんが、文芸誌「群像」で連載してきた「群像短歌部」が一冊にまとまり、『すごい短歌部』として刊行された。この連載では、毎月読者の方から一つのお題で短歌を募集し、その中から木下さんが短歌を選び、選んだ歌の魅力や自分はどう読んだかを丁寧に言葉をつくして説明してくれている。そのおかげで読者は、短歌のひとつの読み方を知ることができる。
普段から自身でも短歌を作っている人、歌集をたくさん読んでいる人たちにとっても、いち歌人が(批評や添削をするわけではなく)どのように他人が作った短歌を読んでいるのかを知ることができるのはとても良い機会だと思う。そして私のような、自分で短歌を作るわけでもない、歌集を好きで読みはするけれどその世界に詳しいわけではない、そんな読者にとっても、この『すごい短歌部』は大変ありがたい存在だ。
ただ一首の短歌だけを読むよりも、木下さんの評とあわせて読むことで、選ばれた短歌たちの魅力がより一層際立つように思う。ふと、これはどういう意味だろう、と立ち止まって考えてしまうような歌であっても、「こんな解釈の仕方もあるのだ」と知ることで自身の世界がぐっと広がっていくのだ。「短歌の読み方がわからない」そんな人にこそ、手に取ってほしい本だと思う。
さらに本書では、木下さん自身がどのようにして一首を詠んでいるのか、についてもその詳細が記されている。正直ここまで書いてしまって良いの?と心配になるほど、推敲から完成までの過程が事細かに書かれている。普段はすでに完成された短歌をただ受け取るしかない私たちには、天才(あえてこの表現をつかわせてほしい)の生みの苦しみはわからない。木下さんの丁寧な解説を読むと、こんなにも誠実に「ことば」に向き合っている方だからこそ、ここまで多くの人がこの人の短歌に心動かされるのだと改めて思う。こんな本を読んだら、私の平坦になってしまった心も耕されるに決まっている。本書を読んで、なんだか短歌をつくりたくなってきたぞという方は、ぜひ今も連載中の「群像短歌部」に応募してみてほしい。
2025年4月1日~4月末まで、三省堂書店神保町本店(小川町仮店舗)にて、『すごい短歌部』のパネル展が開催されています。「群像」5月号の木下龍也さんの連載に掲載された読者の短歌と木下さん自身の短歌をパネル化して店内に掲出していますので、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。