【水歴講座】新発見の軍忠状と尼崎の戦乱
[音楽] こたあの今回の水曜歴史講座ですけども 付けとしましては第11回の企画店ですね えこちらの展覧会え将軍尼崎出陣というえ 南北長内乱と尼崎という展覧会のええま 関連事業というけでさせていただいており ますもえ中世にはですね大規模な戦乱がま 続いた時代でありましたでとりわけその 全国的な規模の内乱と言いますといわゆる その原平活線え学術的にはあ言語をとり まして自称自衛の内乱という言方が多いよ ですけどもから南北町内乱から戦国相談 戦国ソラはあの戦国時代がどこまでだと いう議論も色々あるんですけどまア桃山 時代まで含めちゃっていう意見もあるよう ですけどもえとにかくその中世の始まりと 中頃と終わりに大規模な戦乱があるとで むしろその川倉幕府なんていうのはその 古代末期の大規模な内乱うんこの自称自衛 内乱のを経た結果生まれていきまた室町 幕府体制っていうのも南北町内乱を経て 出きて上がっていきまた江戸自体の爆反性 社会というのも基本的にはあ桃時代戦国乱 時代相談を克服した後出来上がってくって いうまその結果として体制が出来上がって くっていうことにあるんですけどもまあの 以前し中世というとこう内乱戦乱という イメージが多い時代かと思いますその中で 今回はあその中世の前と後ろを確する南北 町内乱ですね尼崎特に中世の尼崎の中で この当時の南北町の頃の尼崎っていうと もう鎌倉時代頃からすでに瀬戸内有数の 公安都市という位置付けになっておりまし たまそういった関係でえそのこ戦乱の中で もですねえそのまいわゆる大規模戦乱の 主戦場という形にはあまりならなかったの かもしれないですけどもその余波あるいは あ小規模の戦乱あるいは大規模戦乱の余波 というのは様々に受けている歴史があると いうことになってまいり ますでえそのおさいそのにですけどもまず 南北町内乱と尼崎の関係についてえ少し 触れていきたいなという風に思っており ます書的に言いますとま14世紀の第2 市販期っていう方も日をしましたがから末 にかけて約60年間続いた全国的な戦乱で ありますでこれを大3つの時期に分けると いう考え方がありましてえレジメにも書い てるんですけどもま第1期第2期第3期と いう風にあるわけですけども全子甲子も 含めますばこういう風な概ね時代区分かな という風になってまいりますでただあの こういったあの歴史的な出来事っていうの は例えばこれあの第1期はま1335年 っていうのはこれは あのこの年の末に芦川高内が あま半期を広すというところからあの 始まっていくわけですけども例えば第2期 第3期がこの1348年あるいは1368 年をきっかけに大きくたということでも ないわけなんですけど大こういう事態区分 からということですね例えば前子としまし てはあ5大子天皇によるまカバ幕府の東博 計画まこれ結局失敗に終わり終わるんです けども現行のラです ねでやがてそれがきっかけとなったかの ように全国各地で氾濫の日の出がって最終 的に鎌倉バが滅亡する滅亡した後務申請と いうのができあるわけですがこれもわずか 数年でえまあ解体をしてくとで始まったの はえまいわゆる県務の乱というんですかね 足高が五代5天皇に対してえ半期を返すと で一旦は高はあ九州へえま川倉めできて 九州へ逃げていくわけですけどもすぐ戻っ てってま港が有名な港側の戦いでえ靴のを 打ち取った後京都奪還をしてで五代天皇は 年間2度も比山にげるわけですけども最終 的にま和木というですね幸福する形で京都 へ戻ってきてえっと天皇のま象徴である 三種の神義をえ時の新たに建てられた公病 天皇というねえ天皇に引き渡して丸くわる かなと思ったらその年の暮れにご大子天皇 が密かに都を脱出してよの行くとで渡した 三種人はリセであって自分が本物を持っ てるんだということで南北町内乱が始まっ ていくということになってまりますでただ その後ご象徴通り北町型の優勢に進んで いきますえ団長型を支えていた一た吉良さ であるとかあ楠木正典であっとかえ北畑 秋江とあえ北畑秋江 楠木正典のイさんですねえがみんなですね えまなくなっていくという中で期になり ますと今度は芦川市北町型芦川市の方で 内行が始まりますこれは年号を取りまして 観能の常談という言い方をいたしますがあ これでその芦川内部で対立をして対立して え片方がまそのの方便ではないんですがあ 南朝型に幸福をするとでそれに常時て南朝 型が一気に京都一時的に回復をするといっ たようなことがありましたでまた地方の方 を転じてみると例えば九州であるとか あるいは東北地方である関東から東北に かけてえまですから金半島えを中心に南朝 勢力はまだしも勢力を持っていた時期に なってまいりますそれが第3期も芦川三大 将軍義光の頃になってまいりますとえこの 幕府権力は次第に確立をしていってえ全国 の体制が整っていくという中でえ内乱とは 言いながら実際的にはもう戦乱がこの方に あんまりなくなっていって水星に向かって いくとでむしろお北町型と言いますかマ 幕府内部の方でえ強力になり過ぎた守護 大名ですね山名とか大内と討伐しなけば いけないな事態になってくるわけですけど もま結局そういったとこでえ義光の方が 進めて両地合一ということで南北町内乱は 終わるわけですがあこの南北町内乱のその 合一のま条件としてはえっと後に系図を 出しますけれども元々のその 北長瀬本町 [音楽] [音楽] の行員ですねえ子孫たちがまやっぱ ちょっとっとしたも持ってる中で室町幕府 の内部でえなんか氾濫事件を受けた時には 羽に建てられる有名な話ではえっと六大 将軍吉典が暗殺されるカキのラというのが ありますでこれあの張間の赤松氏が氾濫を 起こすわけですけどもそん時に南長の行員 を担ぎ出してるというのがありますまそれ が結局オリのランの頃にはもう終わって しまうわけなんですけども結局その南北町 内乱というのは鎌倉末期からえなえ室町 初期にかけての大規模な戦乱であったと いうことになってくるわけです ねさてそれではえ尼崎ではどうだったのか というあごめんなさいえさっきすませ南朝 南北町天皇経です前に出しますあのお手元 にはございませんえっとあの え小坂天皇以降の流れですねえこのご学系 の天皇以降が寿命委党というねえ等になり ますから神山天皇以降が大閣自党で寿命院 党が北町型大閣自島が南朝型という風に なっていき ますでこの系図を見てきますとですねま あの最初御坂天皇から息子のご不格天皇 なって次にですね弟の神山天皇に行為へ 行くわけですねで次にじゃあ上山天皇の後 誰が通うかなった時にえ結局神山天皇の 子供の五天皇になるちゃったんですねで そうするとえご不活天皇は自分の子供が声 につかなかったと非常に悔しがあってえ 色々運動した結果五天皇の後はこの伏天皇 はなるとえこうなると逆画然伏見天皇の後 はですね見ていただく通り次は極みての 自分の息子に行ったわけですねでそうする とゴダ天皇もやっぱ次は自分の息子にして もらないかんっていうんでご伏の後には 5二条で5二条の後には花園という風に ですね交代合体これは領と手立と言うん ですけどもえ結局こういうあの高等の分裂 がですねこの寿命引頭大角児島という 大きな分裂に加えて内部でも分裂をして くっていう非常に複雑な情勢が鎌倉時代 末期に起こってくるんですね単にその寿命 院党と大学児党の対立というだけではない という背景があり ますでそういった中でえ52条天皇はあま [音楽] 国は新のという方に行為が次の次の天皇 なるはずなんですけども比較的この5人長 さんを額してなくなっちゃうんですねで そうするとまピンチヒッターとしてえ5代 5天皇が次の天皇ま花園天皇の次の天皇だ よっていうにまなるわけですねで花の天皇 がしばらくした後こう大学党からもう ぼちぼち在位が何年か過ぎてますからあ 大学児党天皇にしてくださいよってな話に なって5代5天皇が即義するとでなんで じゃあその五大5天のはじゃあの東博に 走ったのかっていうことなってくると結局 ですねこのえ大閣島内でも高等の分裂が あって要は五日町天皇の後は国吉新のって おるわけですねで5代5っていうのはある 種ピンチヒッターでそうすると自分の子供 に行為が伝えられないっていうことになっ てくるでえそこでこう絡んでくんのは鎌倉 幕のでして黄金天皇ということになります でこれはご存知の通り沖に夜ことわずか数 年のうちにまま代表的な楠木の立とか あるいはあの川高寺のりとかいうことも あって鎌倉バが滅んでしまいますでそん時 に皇天皇はどうなったかっていうと結局 その六原京都の鎌倉幕の出張所の六原丹内 これが芦川高内とか赤松によって攻められ てもう陥落をしますえどうしたかていうと 時の台のえ北上市はですねえ天皇天皇え 国交天皇を連れてえ鎌倉に言えようとする わけですねで最終的に大江の国のババと いうとこまで行ってえ結局そこでもうもう こっから行けないということ悟ってそこで え鎌倉バの六川大型の人々はみんなえそこ で自害をしてしまうでえ中ほどの道にこの 天皇始め何人かがわずかにこう生き残って いてはったというねえ結構ねあの地獄を 見張った方んですねで五代5天皇によって どうされたかていうと公言天皇そのものの 在位そのものが否定をされますなかった ことですねで公言点の時代にみんな簡易に ついたいとか感触についたいしてのも全部 取り消されてなかったことにするなかった ことにはするんだけれども一応はその点の の隠し議これあのま変な言い方ですけど罪 はしてないけどもま今でいう条項さね条項 の扱いをしようということで一応はそのえ 地位を保ってあげてたんですね在位はして ないけどもま在位してたみたいな天皇とで それで生き残っていかはるわけですけども ご存の通り5代5天皇は今度は破れてよし と去っていく中でえにの店のま皇上皇さ ですね上皇さが国を集め 足が高に対して日吉に対するま討伐の陰を 下すとでこれで持って高は反逆者で なくなるとでさらには京都へ帰ってきた高 は5代5点の吉野一ちゃても以内え当時は 冷え冷に出てていないとで天皇がいないで 困るんでえ河本天皇の弟の公明天皇という 方を即してもらうですねそん時にどうやっ て即したかていうとこの条項の前でもって えまいやば意させるって割とあの トリッキーなあり方でえ即位をさせると いう形になりますので変そのまだ南朝北長 分裂する前に天皇でなくなってる方ですね なんですけれども一応学術長は副長の初代 はこの高言天皇という形になり ますでほど通り明人になりましてえ南部長 どっちが政党やというま あの私に言わせるとは割と不毛な議論が あってえ政治的な決着の結果南朝が正当と いうことになりましたんでこの北条以下の 天皇はあ皇漢公明からあ都行ご皇軍ご遠の 天皇は罪が否定をされてまして北長初代北 長2代っていう形になりますでただ現え 皇室に決別的に繋がってくのはこの公言 天皇の系統ですね5大5天皇の系統では ないわけですねしかもこの河本天皇その うち南北町内なが激しくなってくとなんと あろうことか あ公明当時は女皇弟の公明条項から息子の ス天皇がその交代使の直人新のえこれら 丸々南朝にさわれてえ しばらく宮子から帰ってこれなかったと いうねえ悲劇的な人生を相でくるんです けども最終的にまた帰ってきてえ出血され ますただ天皇天皇さとしては珍しく前週に 経営をされた方でえ丹波の亀山ですかね あのえ上昇工事というテでま最後オートと いう方ですねまそういう方なんですでえ この間の尼崎の戦乱なんですけどもまこれ につきましてはあの現在開催中の企画店の でもご紹介をしてますのでえピックアップ で重もんだけここでご紹介をします えっと鎌倉幕が倒れる前え1333年あ っとあのこれもあの展覧会の方でも断りを してるんですけどもえ南朝北町の頃は元号 が2種類ありますでえっと 例えば北町型の出来事は北町年号を変えて でかこ南朝年号西暦と書く何でとは何年で 書くっていうやり方もあるんですけども 両方は戦ってるのどっちかの年号で書くっ てもなかなか難しいものがありますのでえ 一応西暦で統一をさせていただいてでかこ の最初の年号がこれはこの場合小胸という のがま厳密と北上じゃないですけど北中型 の年号え現行が何兆型とそういう風な書き 方にさせていただいておりますえ1333 年のウルー2月から3月にかけてえ国坂部 から尼崎にもあるんですけども赤松勢と 六原短大勢の合戦がございました でまたこれ第2期に属するんですかねえ 1351年る観能の常談というのは起こっ た時にはこの芦川高型正型の軍勢が神崎で 戦うでまたそれから10数年なった後 1363年常時2年小平18年この小平と いう年号がね南朝では結構続くんですよだ から結構楽なんですけどもねえ北は結構 コロコロ変わりますえここでは崎でも戦い がありましたということなんですねであの これらの活線っていうのはおそらくそのま 教科書に乗るような大きな活線というわけ ではないのですけども例えばその最初の方 のえ坂部の活線も結局これでえっと赤松市 は六原台勢に買って京都まで攻めのって いくとで一旦六原台まで攻め込んでいくん ですけどもまちょっと反撃を受けて撤退を してで走行してるうちに丹波の方でえま 半期を被した滋高内が合流をしてあけなく 6単体陥落するというねそういうま前哨戦 的な戦いにもなりますねこちら太平器図と いうね資料がございますえこれ少しあのこ 注釈はいるんですけどもえっと太平器と いう南北町内を描いた軍旗物語平物と並ん でえ非常に有名な太兵器というのはござい ますで今回の展覧会でも半本江戸時代の半 本ですけど太平器をかなり対応をさせて いただいておりますでえその太平器これ あの非常に江戸時代以前はこういうあの 日本は活文化木板の文化が発達しますので えま教養書と言うんですかね歴史書ま今の 教科書的な感じで多くの人々に需要されて いきましたなのでえっと太平器に書いて ある出来事があ当時の人とってみれば歴史 イコル歴史なんだという風な理解にも 近かったようですねでえっとこの太兵器は 当初はま公爵語りもでもあるんですけども 街かどに立った人は太兵器の公爵をという ことでも人々に知られていくようになり ますでその中で太兵器には様々な活線の 状況が具体的に書かれてることは場面が 多いですでそういったものをピックアップ して当時のその活線のえ状況はこうここう だったよとでこれがあ軍学的に言ばこっち の失敗あったねとかねこっちが良かったね 的なことをまば江戸時代になって平和な 時代になってこう注釈を加えた本とま かなり大胆な言い方をしますけどねそう いった本がございますでえ上下2冊なん ですけど太平教というね えまあの他の太兵利人頭とかいろんな名前 あるんですけど太平図という風なえ代に なってる本なんですけどこれにその福坂部 の合戦のすというのがねえ図範囲で紹介を されてるんですねでこれ あのこれカソリ今出てますよねこの川ここ に瀬川てこれが箕面ですねでここが口赤松 とありますのでまこっちが来たこっちが南 という南北はあの反対しておりますけども この瀬川まで来た六原大勢に向かって赤松 がどんな風な夫人をしたかというねそう いうことを書いてある本になりますえっと 木半本でえ色がついてますので多食なんで 非常にあの えっとま分かりやすい資料ということま ちっちゃな本なんですけどもこれ展示会場 に出しておりますのでまたおかの時見て いただければと思っておますでこの時の 活線の関連にもなるんですけどもえイサ 神社というお宮さんにございますけども そちらの経済にはですねま赤松延伸の墓と 伝わる石道が経済の車線のえ右手の方に ありますでもちろん赤松延伸は春馬の人で なくなってなくなった後はま針までホムら れてるのでえ尼崎にあるわけはないのです けどもあの特にこの手前のこの石とですね えよく見ていただくとゴリ等ではあるん ですけども完全ではないんですねえっと上 の2つで下まとも違う感じがしていわば あの五輪島の団結ででえ赤物の年代判断 からすると赤松延伸よりは時期はくだる らしいですのであの直接的に赤松延伸に 関係するものでないという風には考え られるんですけども伝承としてえ赤松 ゆかりがあるということがあま指跡として 残ってるということです ねそれからもう1つこれは神裂ですね えっと神崎橋を今あのえっと堤防の上を 超えていくま橋の下のとこですねにえ神崎 一新地蔵というのがありましてえそちらに ですねえこういうお祭りをされてる正面に この石碑がありまして石碑にこの由来が 書いてあるんですけどどういう石碑かと いうとこれは鹿賀高がえっと鎌倉と持っ てって京都一旦占領した後え北畑秋に追わ れてえ一旦丹波に逃れてでさらに京都を 攻めていこうとしたところ結局楠木正に日 に破れでえ九州へ去っていくという時に この神崎で戦ってえこの一に一心に戦った という風なね楠のが戦ったという伝承が 伝っててこういう一新地蔵というのが作ら れたという風に言われており ますからこちらはま楠木正さんですねあの ま有名な画像はもちろんあるんですけども こちらは江戸時代末期のえ吉さん歌川国吉 という割と有名な昨今有名なあの浮さんが いらっしゃいますあの猫の絵なんかをね 解体したとかあ非常にあの武者絵とかを 得意されてる方ですけどもえどうもこの タイトルからして100人の武勇の人々を こう連続問で出したシリーズ問のようなん ですねでえ楠のを取り上げてるんですが もちろんこれは江戸時代末期の江戸の向 さんが自らのイマジネーションで書かれた もんですので実際の姿とはだいぶ違うと 思うんですねでえなんかこう星大門の姿で えっと出してますけども手元にですね ラシマみたいな持ってるんですねで横に あんのはどうも天球技のようなんですねで クソまげと新板天球義って何の関係がある んかなと色々考えてみたんですがあのま 太平器なんかによると楠正は例えば視点時 で産労して確か小徳大使のお未来機をこう 見てで未来の出来事を知ってたみたいな ことは書いてあるということから連想して こう未来を見通す力を持ってたという風な イメージをこう助けるためにこういうラシ 版みたいなものを置いてるのかなってこれ はまあのほとんど思いつきなんでえ論とも 言えないんですけどもなんでこういうのを こ国師さんが持ってたのかなっていうのは ちょっと興深いとこですけどね でこれが今回特別出品をしていただいて ます高言条項の陰Womanというですね え先ほど長々とお話をしましたあの僧侶姿 の公言さんですねえもちろんこれ隠然です のでえこうえま出血はまされてないと思う んですけども天皇を辞められた後条項の時 に え観能元年というちょうどあの芦川市の 内分がこう始まっている頃ですねえこの時 にに家紋のことま家のことですね家家家の ことはえこナフそいなき内大臣の まそもそもの思いから ああなたがちゃんと支配をしなさいよと いうことをおこの子孫である大井門自重に 当てたえま隠然というねえ文章でござい ますでもちろんこれはあのもちろんとです かねあの公言条項自身がおかきになった ものではないんですね公言条項の命令をえ 側近ではるクがえ聞き取ってでそれをこう ま下達したというまそういう文章になるん ですけど文助名としてはあ公言条項隠然と いう風に言っておりますでこれはあの尼崎 市内の個人像ということで伝わっており ましてえっとこれはもう何年か前 にま当間統合する前のあのえ地域研究使用 官が出しておれる地域市研究にも口で紹介 をされてますのでえ存在そのものはよく 知られてるんですがえ今回あの南北長の 展覧会ということでできれば写真なんか 出していただければいいかなと思ってお話 をお聞きしに行った時にまひんなことから ま公開してもいいでって話にご理解を賜り ましたのでえお借りをしまして今回特別 出費という形で電磁会場で出しております でこれは あのお聞きしますと こういう形でえ博物館等で展示さるのは おそらく初めてだろうという風に思われ ますただですね内容的に尼崎の南北町内乱 の戦乱とはほとんど関係がないんですね 大門っていうふの家打ちの話になってくる だからえその主導者さんは別に大かけのご 子孫でもないと思いますのでどうやって これが伝来したのかっていうところよく 分からないところはございますそれとあの これ画像で見ていただいてもちょっと茶色 かってるのはお分かりいただけると思い ます現物見てくとかなり茶色っぽい感じが しますでこういった時期のあの天皇 あるいは上光の陰線というのはえ薄墨神 って言ってあえてその色をつけた輪ですね えを使って書かれることが多いんですが これはどうも薄墨よりもさらにこの茶色に なってますので経年劣化つてるところが 焼ける焼けてるということからま年来の 家庭で何らかの自動でそういう風な状態に なってるのかなという風に思いますま今回 あのえ尼崎将軍尼崎人とあまり関係はない んですけど同じ南北町時代の顧紋所で個人 像で市内の持ちのものということでえご 理解を賜りご出品させていただいてる ところでござい ますでそれと市内とはちょっと外れるん ですけどもあの天法線のと171号線が 交差するところ伊市池尻のとこの小の北家 に諸直すかというのがありますこれあの 観能の常談っていうのは高内対田牛です けども初期の段階で高内型の質であった モナがえ負けちゃってで内浜の活線で破れ て負けてえ京都へ連行される途中にですね 向こう側辺りでま敵であった上杉にま斬殺 を抑えるという事件がありましたでえま それをまあ とらうっていうんですかねためにこの 171号線ちょこれ西国街道通ってるとこ ですのでその辺りに日が立てられていてで それがまいつしかこう道路整備の形で色々 動いてえ大正年間建てられた日なんです けども現在はあちょっとそのえ池尻の交差 点のところの西北の角のちょっと入った とこにある諸塚で伊丹教育委員会さんが こちらの説明分を立おれ ますそれではですね え非常に大雑把な話でこれで南北町内と何 が分かったかっていう話もあるんですけど もえあまりここばっかり見てると冒頭話し たえ昔の恩師の事業を思い出してしまい ますのでえ次の新八の軍中場の方に移って いきたいと思いますえこれ何かと自書的な 説明ですねえ活性に参加したものが自身の 先行をその活線の指者に提出する文助と いうことになりますでえ鎌倉時代の分営 公安の駅にどうも作られたのが最初でで 以降南北長期に盛に作られ ますで提出を受けた指揮者はあその文助の 袖袖というのはあ文助の右端ですねから奥 え左端どちらかに犯と言いましてえにあり ます通り書はけで一見しワヌと書いて自身 の顔あるいは受けたりワヌで顔というね こういうのを全て返却をするというのが 一般的になっており ますでこれはあの例えば活線の場所とか ですね日付なんかが分かりますのでこの どこでどんな活線があったかっていうのが ですね具体的に分かる非常に貴重な文献 資料ということになるんですがただ厄介な ことにですねこれねしばしば疑問所の場合 があるんだそうですねでなぜ疑問所がある のかというのはですねこれは色々あると 思うんですけどもま1つはあ公生その武士 の子孫の方が先祖がどんな活躍をしたのか というのをこうすごく活躍をしたんだと いうことをその残したいたためにですねえ その捏造してしまうっていうことも しばしばあるようなんですねなのでえで しかもそのやはりあの基本的に自己申告の 世界ですのでまあの持ってる可能性もある ということでえ表見内にも例えば表見士の 資料編なんていうのはありますけどもあら の方でえ例えばえっと有馬軍の方有馬軍の 方のとあるなんたら門上ってあるんです けども え軍中上あるんですねでところは軍中場の 後にこの文助検討用するってただ格脇に 書いてあるんですねでこれはどういうこと かというと若干疑わしいところがあると いうことなんですねなのでえ神眼の見極め が非常に重要になってくるということに なってきますえさてえ今回ですねえご紹介 するのは無よつ軍中上というものになり ますま今回の展覧会のまえば主要資料と いう形になってるんですねでこれについて はちょっとあの冒頭で申し上げるべきだっ たんですですけど言い訳めくんですけども あの展覧会のテーマはあ将軍尼崎出陣と これは2大将軍芦川吉明があま大軍を率い て尼崎に半年間も罪人をしてで去っていく という出来事が南北町時代にありましたで え前後に見てもですね将軍が長期間経って 尼崎に滞在したってことないわけですから 南北町時代の尼崎の代表的な事例という ことで南北長の内乱機の尼崎を紹介する 展覧会のテーマとしてやはり将軍尼崎大臣 というのこう取り上げるべきだなと思って タイトルににしようかなと去年の秋ぐらい に考えてたんですねえところがですねこの 無寄つ軍中場というのはその後存在が 明らかになりましてでえ幸いですねえどう にかこうにかあ入手することができた資料 ですねなんですねなのでもっと早く入手し てればひしたら天覧会にタイトルは変わっ てたかもしれないなということもあるん ですけどもえっとまずですねどういった ものかあのまずあのこちらの方で概要をご 紹介しますと年月日は公案2年の8月と いう年です公案ってね我々公案と聞くと あの現行の公案のね広い弓編のむの考案を 思い浮かべますよねこれは南北町時代の 北町年号に公案っていう年があるんですね たった2年なんですけど確かえこれがあの 南朝年号では小平17年という年です西暦 1362年ということになりますで作成し たのはムセ黒門の城寄つという方でえ法量 縦がですね31.3cm横が45.2CM でえ形状は縦っていうまいわゆるその普通 の神1枚分でえ軸装にもなっておらず乾燥 にはなっておりませんがえ一応裏打ちはし てありましたけど若干ですねえごく小さな 虫食いなっですかねだけは残っております がま比較的保存状態はいいものでござい ましたで数量は1通でございますで付属品 としましてえっと縦18cm横5cmの紙 の札がありましたなんて書いてあるかって いうと消費正しい筆えム黒門え門よりつら 先行申し とどうもこの紙切れはあこの文助の端裏の 部分ですね右のえ隅の上の部分に貼って あった元々は内容的にはこの年の8月10 地のに上皇寺に3これも上皇寺という地名 が出てき ますから16日17日に神崎でえ戦いがあ てそん時にどんな活躍をしたかということ を上をしましてでえそん時の指揮官のま 代表者が後に説明します佐々木高秀という 大江の出身の武士ですけどもだったので この高秀が犯を加えてるとそういう文章に なります年代なんですけどもこのものその ものの年来はよくわかりませんえっとどこ で入手したんかていうはあのえいわゆる コビ市長から購入をいたしまし たえただ美行としましてえ文というのは 稲川町にありますえっとこれがですねあの 画像の方になり ます三科にあるさな神札がさっきの消費と 書いてあんですねえ無よりつら軍中場で えっと軽く読んでみますと課員後人無黒 大門城よつもうす軍中のことということで え多後人であるブセ黒大門城リラが軍中を 申し上げますというので始まっております で以下軍中の内容ですねで右今月15日 今月というのは後に年号のとこに8月と ありますので8月ですね8月15日上皇 寺人5人に馳3時え尼崎に関連するところ は あなんて言うですかねえ四角で囲っており ます上高時午前に発散時え立地や活線をの 中節をいたし終わんと で同16日神崎の西橋を警護し警護するの 間あ恩船 に船に取りのりよせたるのところえつまり 神崎の橋詰めでえ警護してたところを敵が 船に乗ってやってきたとので えっと散々活線をすの刻みその時は戦をし たわけですねそうするとそのつど 若恩三国の川を打ち渡り三国というのは この上流の方にあります大阪市の方の現 大阪市の三国ですね三国の私を超えてえ 加島から倉橋の在家を 焼き払いでえ彼より大勢寄せきたるの間え 四国合戦いの城ご存知の上はあご飯を賜り い交互の器形に備えがためあらあら言上 九段の年とえ公安2年8月2日8月日で 一見しわぬ顔とでこのようにですねえ内容 的にはあこの上皇寺に山人をして神崎で 合戦をしましたとでいうことは結構ね 詳しく書かれてるわけですねこれがですね 全く同文の文助ががあ稲川町の平文助に あるということから一応この文助の背景的 なものを少し探っていきたいなということ で えっと以下ちょっと画像等で比較しながら 見ていきたいと思いますがこれが改めてえ 今回の文助の全容でございますえっとお 分かりいただけますかね あのちょっとこの 辺こう色変わってますよねこれ裏打があり ますここはちょっと紙切れてますからここ とかこことかここにちょっと虫食いやな この辺に若干ありますけどもそれ以外はあ ほぼほぼ完璧に残ってる文章になってき ますでえ当初あの裏打ちも何もなくうな 状態かなと思ったで一応裏打ちはしてあっ たようですえこちらがそのちっちゃな方 ですねの方になりますえっと消失でえ性質 まあのいわゆる正門であるということです ねで物苦労左門の上入ら先行申し踏みとで これがですねあの平文助という文助今回 ですねあのこの資料をま入手するにあたっ て色々調べる中でえ稲川町北部の旧瀬村あ まかつてはムなと言われた地域のえ島地区 に平尾地下さんていうタがありまして そちらのうちに伝わる顧問所がございます でそん中に中世南北長期と戦国期の年号の あるえうと将門の文助これあのカス巻き物 になって3巻あります南北長期のう10通 5通ずつ関数2巻から戦国期の小本の文助 とそのうそれぞれを関数にしたものは1巻 合計3巻これが稲川町に現存するんですね でこれはあの川部軍稲川町における多委 後人に関する調査研究その3平資料調査と いう非常に長い名前のえ調査記録があり ますえっと2017年平成29年3月の 稲川町歴史文化遺産活性化実行委員会と いうところがされてるもんですが報告書に なりますのでえ最終的に文化庁提出され てるはずなんですけどもまそれに結構詳細 な調査記録がありますでその中の南北長期 の移し10通の中の1通が今回の え文助のがその原法にあたるんではないか ということになるですねこれはねえっと 現在の平家ですえ稲川町のかなり奥深い ところになりますあのどこ変化と言います と稲川町のさらに奥まほとんどあの丹波 佐山野瀬に近いところにむせというところ があの稲川町の北部地域はかつてム浦って いう村でさらにその奥のに平がございます こんな感じの佇まいですえなんか武器や 四風で非常にいい感じのお住まい こういうねかぶきですね実はこれお住まい なんですけど も宣伝ではないですけどこの里の家って いうねあの いりいりジアということでねこちらでお 食事ができるようなってましたであのこれ もですね今回この顧問所が稲川町さんに あるとで報告書のデータもいだいたので あのま画像をですねえ今回展覧会実物が出 てるのでそのうしのものをこなでっってお 話ししたいなと思って稲川町さんの文化大 担当の方と連絡を取ってえ所動者様と連絡 を取らせていただいた結果あの実物を拝見 したいってことで実はお伺いしましたで そん時のこれ写真です写真だけお借り できればいいなって話だったんですがあ いいですよもうあのお貸ししますよってね 言っていただいたんですね実はこれがもう なんと4月に入ってからということでえ 展覧会がですねも始まってそうやという時 にもう急遽こちらを越出品出ことになり まし たでえ実際行ってえお借りをしてえ現在 展示室の方に実物を出ししてるわけなん です ねでえこのムセラレという人なんですけど もこのこちらの小文と南房長期のうちの 10の文助の中にこの寄つの活動っては 結構ね詳しく出てくるんですねでそれに よりますと活動機の上限は348年から 133083年という時期で主に北町型と して活躍をしておりました1番盛のでは その河野諸冬という人に従って天王寺は川 長野で合戦したりとかあるいはあ当時あの 大将軍吉明鎌倉におったんですけども観能 の常談でえ正義が失客した後そのま代りを 努める感じでえ上陸をしますでそん時に 大江の国まで出迎えに行ってるとというの がこの顧問所の中に出てくるんですねで これ今知られてなかった事実ではあるん ですけどもでこのたごけ人ということでえ このどうも鎌倉時代からたご人として活動 してる人物がいるんですねえっと法条を やす時方書というやつですね6番えこちら 見ていただきますと全治入道土の恩地アモ とありますのでこれはあの時期はちょっと 未確認なんですけどもえ正文ではなくって 多員住所というねいわば控えの顧問所の中 のえに入ってるもんですけどもえ冒頭から 多大員5人瀬羽根証言幸博以下のやかと いうこういうのが出てきますえ家庭3年と いうえこれは1237年ですからあ鎌倉 時代の前期ですかねもこの頃には多大員 後人としてムセ氏が活躍をしていたという ことは分かり ますでた人た人という多員ごけにてなん やっていう話ですけどもこれは多員って いうのは現在ただ神社とおっしゃってます があ事の三中をお祭りをしてましてま港の 三中から川源子ですねが流れができてき まして南本よりともになってきますそれは 現地の訴ということで非常に尊崇されたあ ま施設でありましてでそこの多をこに奉仕 する武士団として鎌倉幕府から員人という のが設定をされてますでその中に鬼カーデ 軍を中心とした武士がその中に参加をして てただ時期によってこの多大員国人の活動 っては変わってくるようなんですけどもえ 戦国時代までえま語人というのはま唯一 正しい武士であるというねえ誇りを持ち だったと思うんですけどもそういう一族の 1人にムセがいるとで 実際ま図も実はお持ちなんでですけどもえ 今回経を会しなかったんですがこの無羽根 証言幸博 と今回のムセよ面直系かどうかっていうの はよく分かりませんけどもえただえこの ムセムセという名前をなる人物がいたこと は間違いがないですね北町型がま結構切の 国を支配した時期が多いのでえそういった 北町型の物資の指揮化でえいろんな活性に 参加してるそのうちの1人が無よりつで その無よらがこの尼崎の神崎での活性にも 参加してるということが軍軍中条を残して いるわけですねで他の合戦は例えばあ 1353年に え萩のトマですかね荻野友につって丹波 国内で戦っていますえこの荻野市というの は丹波のえ黒人でありますしえ真島市って いうのは節の守護代節の黒人でありますの でま時々によってえこの立地的にこの地図 見ていても分かる通り丹波にも非常に近い ですよねでそういうとこでこう軍勢最速を 受けて参加をしてるということは分かる です ねでえ1362年今回のもですねえ高に 従って神崎で活線でこれが その平尾健文城の中のムセ立の軍中場のう になり ますまこれをねパッと見ていただいかと 言ってさっきの画像を記憶にってないで どこが違うんやと分からないということも あると思いますのでえあえてちょっと並べ てみたのはで下の方がえ今回お借りする ことができましたあ平文助のうしの文助を 並べてみましたでえっとちょっとねこれで はなかなか分かりづらいのですけれどもお まこういう映しを作る時にやり方あるよう ですけどもあの例えばあの顧問で打つ時に 左右においてえこう映しとるやり方とか から上に紙を置いてこう映しとるやり方と 色あるようですけども見ての通りこれあの ま行間も違いますしあのまちょっと今回 あのご職もありましたけども業務送り文字 の送りがですねこちらとこちら違うんです ねなのだから行数が違います見てる通りね 終わり方がここで終わってあの原本は こっち終わってますけどこちら下まで来 てるとう違いがありますよねだそういう 意味ではあの文字の配りまで厳密に というわけではなかったえただこの一見 シワの顔というのはですねここは結構です ねきっちりねえ原本に忠実に映そう映し とろうという意欲は割と見えるのではない かなという感じがするんですね本文だけを こうね比べてみましたあのま言ったさっき 言った通りその行数もやっぱ違いますので 全くこれをそのまま映そうと思ったわけで はないただあの書かれてるはもうほぼほぼ あの文字は一致しますで一部あの平尾門は ここは文字読めてないところはあるんです けどもうの方はね原本にはちゃんと文字が あるということでえまあの忠実なうである ということは確認ができるですねでそれ からこちらがこの日付と一見案ですね とにかくあの群は何が重要かていうとこれ があることが重要なんですねでこれを持っ て えあの一見シヌというね犯をいいたものを 持っておいてで後日音象請求時にこれを 証拠とし出すわけですねだからこれが必要 なんですねでこの瀬さんですけども他の 文字によるとレジメも書いてあります通り 軍港の賞としてですね音をえてますえ2 ページの中ほどですねうんと 48年の8月に芦川吉明が鎌倉谷村を当っ ておりますが次1352年今度はまたあの 10月が抜けております10月と書き ください橋川吉明が多野の自式をこれ当て 行ってましてこれあの1人ではなくって それぞれのこう配分をして当てを行う ちょっとあの変わった形になり ますで最後に川がですね永徳3年え 1383年に多野商内の初村と鎌倉谷村ま これはどうも新たに与えたのではなくって えま統治業アドっていうんですかねあの 実際支配してたところをアンドしたという 文が残っており ますまムセラレについては以上のとこと しか確認はできないんですけれどもなより も注目するのはやはり崎の高安での神崎の 活線にこう活躍をしてるというのがですね え分かるということですねじゃその神崎の 活線というのは何かということになって くるわけですねで以下ですねこの無より 軍中上の廃棄を考える上で神崎の工房を 少し振り返ってみてえこの文助の歴史的な 価値についてのえ話につげていきたいと 思っており ますでまずですねえこの神崎の工房なん ですまあの実は神崎の工房はあの冒頭に あの尼崎の活線でこんなあったよう中に 観能の常談の時にも神崎で活線があったま 結構ですね神崎はあ争奪線になった地域で はあるんですけどもとりはこの南北町時代 の1360年前後の時期というのはあドか この神崎での攻防があ割と集中してる時期 ですねえ記憶によるとでまず1つはあこの 芦川吉明がですねえま今回展覧会のメイン テーマにしておりますえ吉明のあの尼崎 出陣というのが1359年の12月のにま 前年に将軍に就任したばか市の吉明が やはりあの将軍就任を景気に自身のえ軍事 的権威を高めようというともあったの でしょうけども関東から畑国を引きいる 待遇を呼びせてえ南朝型に大構成をかける わけですねで気持ちとしてはここでえ南朝 の生を飛べたかったということなん でしょうがあその時にどこに本人を置いた かっていうと太平器によりますとえ尼崎に やってありますでえ太平器はあのえ歴史 物語ですので真実ではない部分はあるにし ても他の文献資料などからえ吉明が尼崎に 半年間いたことはこれは確認がされてます ただ生い軍勢というのはあ太平均の傷って 大体あの軍勢の数があかなり割り増しに なってますのでそのま信用はできないん ですけどもえっと尼崎本人をおいて大島と か東は大阪の渡辺西は西宮鳴尾あたりまで え北町軍は夫人をしてで今風に考えると そのなんで尼崎に来て南朝の方を攻めて いく本人になるんやっていうじはします けどもこれはですねあり当時の地的な条件 から考えてまあの実は絡め群として畑ま清 勢があ現在の京阪炎線沿の方進んでますの でえ本軍の方はいわゆる旧の最後海道を こう下ってって尼崎目でやってきてで今度 神崎川からあま当時は中津川って言った川 からあ淀側ですねえこれを超えて川地の方 へ攻めていくとあるいは木の方へ攻めて いくというそういう手だったですねでこれ に対して南中型はあ最初は抵抗のを示すん ですけどもこれはやっぱり大軍なのでいか んっていうんでえ上客を構えてえしいて いくとでえ北町軍はあもう軽軽と神崎川を 越えてえ渡辺天王寺住吉あたりまで攻め てってさらに小田林あたりまで軍勢を 伸ばしてまた木の方にも攻めてくという ことを行うんですけども 将軍総大将の将軍はずっと尼崎にいたん ですね自らは出陣しなくってでえっとこれ はあの大学さんの顧問所からあ吉田は その間大閣を人種にしていたということは あ言われてますで結果ですねえ木の国とか 川の国の南朝勢やっぱ一旦赤坂城とかあ木 の方の城とかをこう攻めとったりをしてえ ま一定の成果を上げるんですけども結局 南朝勢はあいわば撤退をしてさらに奥の方 へ行っただけということでま決定的な勝利 は得られずに翌年5月に起業いたしますで むしろその間に味方の北町税の中に大名感 でえ不強和音が起こってまりますで結果2 期吉永あるいは続いて細川清子といった 大名が あ没落をしてであろうことが南張型に片を してでえその結果一時的ではありますけど も翌翌年にはですねなんとその京都一時 没落をしてざるを得ないという風なことも 起こったりもしてるんですねでこのように あの吉明の長崎出陣というのはあ結果的に 大きな成果は残念ながら得られなかったん ですけれどもえっとまその間結果的に大名 間の不興ワをこうきたしてえ北上型のま ある程度その混乱をきしたでその完結を ついて南朝型が川地の方から節方面へ攻め てくるというのが続いていくわけです ねでえこれがえ今回ま尼崎吉明が尼崎に 出用したということでえ当間所蔵の芦川 吉明の所場あこれま将軍に就任する以前え す観能の男観能の常談頃に出した文助でえ クの その元高に対してえこの度の中節をま 称するという文章になってまいります えっとこちらが吉明の顔ですねまこの文助 そのものは尼崎の歴史にあの直接関係はし ないわけですけどもえっと尼崎に半年間も 在任をしたという吉のもちろん所場とは 言いながらあ多分全文はあのゆる 初期間というですかね誘が書いたもので 自身はここのサインをしてるだけという ことやと思いますでえこういう文字を今回 出しておりますのでまたご覧いただければ と思いますがえっとこの吉さん結局帰った 後さっきも言いました通り不安定化が 起こってきましてそのえ原因のもう1つは え切通の国の守護はですねえこの時期赤松 市から大江の佐々市へこう変わるというね えそういうねがありましたでこれは結構 あの地域にとっては非常に混乱をもたらし た大きな原因なったようですねであの守護 というのはあま鎌倉幕府以来の設置されて まして室町幕府になりますと守護の権限は かなり強まってえその国内の武士をこう 指揮をするとかあるいはえその地域の中で え無本人がってえ領地を没収されたらその 没収た領事のえま あ支配を代わりにあの誰かに与えるという 風なことをするっていう結構ねあの地域 権力として大きな力を持つようになって いきますただあのあくまで原則は守護と いうのはあ1代限りで本来交代すべき存在 だったようなんですけども室町幕の場合は やはり初期にはこういう南北町内乱という 戦いを勝ち抜きていかなければいけないと いうことで各大名に その国の包括的な権限ま死後として与えて で南城型にち打ちかたなければいけないっ ていうこともあったので結構有力大名が 各地の守護をこう獲得してでそこのま領域 国国内の武士をこう指揮をして家診断に 組み入れてったり的なことをねだんだん ししていくわけです ねでやがてそういう中で生き残っていった 大名が後に戦国大名につがっていく大名も 出てくるわけなんですけれどもえ切の国の 場合はあ室町幕府初期から赤松市のえ最初 あの鎌倉幕府打当に活躍した赤松円心の 長男の系統赤松のすという人があ守護に なってでえ以後そののすの子供え三が守護 を務めるとで赤松の本家の方はえ助の弟の 方の即という人が継ぐという形になって いくんですけどもえこの1360年段階に なってえまにわかにですねえ大江の佐々木 市これが佐々木同様というね強国同様とも 言われてるえこの人物のが結構幕で結構 大きな力を持つよなってきましてでえこの 佐々木市によって守護が交代になるという ことは起こるですねまそうするとま在地と しては結構混乱をするであろうということ を隙をついて南城型の和の機が攻めてくる とでえ川地から節へ攻めてくるのはあま さっきの逆のコースですよね えっと渡辺じゃないはあの淀川の本本流を 超えて長津が超えて神崎前攻めてきて みたいなことになってくるわけですねで これに対して え守護になったのは佐々木同って言われて ますけどもえ自身はあ京都におりますで 現地にはあ孫でありますえ秀明秀典とです けど兄弟があ現地に派遣をされるんです けどもあろうことがこの兄弟がこの和クの 時勢に破れて負けて死んでしまうという風 なことも起こったりはするわけですねただ あのだからといってえこの時期切の国一体 が南朝のえ型の安定的な支配下にあったの かていうと彼もそうではないんですけども 結構その南張型の勢力が入っていた時期に なってるということですね でまた翌年になりますとえ今度はあの北町 から南朝へこう基準した細川清児この人が まいわば四国でですねえ北町の動きを しようとしたら今度は一族の細川よきに ここで歌えてしまうんですねで太兵器の 記述によるとお示し合わせてでこう南城型 はあのやろうねっって言ったところは清子 は勝手に拒否して勝手に負けちゃったとで このまま行くと南中型自力になってしまう のでここはやっぱりちょっと南中型として はなんとかこうえ質地回復をせないかんと いうことで再びワの勢がえ神崎に攻め寄せ てくるとえそこでえ佐々木市の配下の守護 台の美浦沙市とから説の国州が応戦をする ということが起こってくるわけですねで それなんで分かるかと言うとえ太平駅の牧 の第38という中にえ1つの公文あります 和田楠木池田ですね和田楠木え美浦次郎 大門と おさのことですかねこれあの太平器では 美浦次郎左衛門になるんですけどもえっと 顧問女ではですねどうも次郎上門なんです けどもこの施設丸ことがあの次2ページ から3ページのあ2ページ1ぱまでこの時 の末戦いの末太平に詳しく述べられてい ますでこの時の合戦に参加したのがあ今回 ご紹介している無よつが参じしたという 神裂活線なわけですねなのでこの太兵器の 記述とこのムセライデンよの軍中上の内容 がどこまで一致するのかということを見て いかなければいけないわけなんですけども これでずっと呼んでくとねなかなかねえ 大変なんですなんでえ満で申し上げますと え公安2年え1360年公安2年小平17 年8月の神崎カテこれあの太平器の通を元 に書いてみましたまず北町税は大兵器で 言うところ500余でえ参加した武士は 美浦貞からえ同矢次郎以下のそれはこれは 大尾の武士ですね以下常談の方々はで下段 はその大の守護になりました佐々市によっ てえま呼び集めれた節の武苗字がしてそう ですねえ伊丹大和の神河原林男性左門 白田川上門城から中一期ってこれはあの よく分かっていないようですえこういった 物資たちが集められて合計500期でこれ があ方々が北上型一方攻めてきた南城型は 800余期でえのが64人と言われてます この辺りの数字がまちょっとね丸につをし なきばいけないかなっていうところもある んですが え何千がった和田正竹と楠木正典ですねで この後この尼崎での活線が終わった後今度 兵庫の方攻めていくんですけどもそん時に は南張型には石党寄りという方も入って後 3000期がえ兵庫の港側まで攻めていっ て焼き払うとでそん時にはあ再びさんにえ 神戸に再びさんてあ再びさんの後に赤松 兄弟が場してるっていう記述もありますが まその軍では今回入っておりませんで この治療編の1から2の内容を日付をって 表にしたのが次の警官になりますでまず ですねえさっきちっと言いましたように7 月24日に南朝型に下っていた細川清子が 打たれますでえ四国中国は だから南朝型はこれではまずいって言うん で大正挽回のため8月のこれ日付はよく 分かりません15日の可能性があると思う んですが神崎に進行をいたしますでこれに 対して国場型はどうしたかというとまず 神崎の橋を焼きおとしますということは つまりこの時は神裂に橋があったという ですね江戸時代には神裂には橋はなかった です中世のこの頃には橋がどうもあった ようですでそれを敵がえ進撃してこように 橋を焼き落としたと太兵は書いております で南型があこの橋詰に攻めてきたんで北町 型はあ神崎の初めとクにこうねえ付人を するわけ2箇所に不をするで北町型はクに はあ美浦あ矢次以下からえ守台は神崎 つまりクと神崎に北型はこう行って敵が攻 てくんのを待ち受けてるで神崎は橋をクに は元々橋がないのでえお互い対岸で 睨み合ってるという状態でヤハになります と大平均よると南朝型は不尽してることを 義兄をしましてえ密かにかりBを焚いて いかにも罪人してるぞと見せかけて え上流の神崎の私を渡ってえ大壁に書いて ある通りの文字表現ですけども小屋の戸松 川林進撃をしたとあるわけですねまこのま 伊ですねえから戸松崎ですね川林はこれ 西宮なんですけどちょっと川林はね ちょっと行き過ぎじゃないかなという風な 気はしてますあまりこの辺の治感が分かっ てない人間が書いてる可能性があるなと私 は思ってるんですけどもでえ進撃をしてえ 来るわけですけども密かにねでそうすると 神崎にる北町型にすれば背後をこう密かに 来てるわけですねでえ北上型は小屋のとか あ戸松の辺りにこう日が見えると煙上がっ てるの見えるとでただこれはあのまさか 敵軍が川を渡ってると思わないので味方が なんか間違ってやってんやろうと思って ほったらかしせて夜明けになると何のこと はない10数か所以上に敵がいてることが 見えたとでこれはまずいっていうねどうし たかというと上皇の用害に退却をするん ですねでところがその上皇寺から貸がが 聞こえたので味方のはずの節の黒人の中 イキらはこれはまずいって言うんで335 を消えていってしまうね自らは場所をよく 知ってるんなので結果的 に佐々木星ばっかしになってと一部の絶 国人だけなってしまうんですけれど も結果あその神崎の方に行ってたえ美浦さ とは東へ向かってでそこでえこう敵中突破 を測ってえま川林団大途中で内陣をして しまうで逃げようとした田川はえお前は 逃げるのは卑怯ねあっていうんで仕方ない でしぶしぶついてってこいつを案内にに さしてなんとか脱出をして京都へ逃げて いく とで一方木村これはクの方に行ってた方 ですねはですねえ城光寺の前ですね敵が もういっぱいいてるのでそのもう味方が2 つの分出るけど一生になれないとえさっき 言ったように美浦は東へ行ってしまってる とじゃ食せいる自分はどうするかて常高寺 まで来てどうするかっていうことで上皇寺 の前に敵軍がいっぱいいたのでえそこで ですねえ太平の気にるとも死のうと思っ たら生きるんやと生きようと思ったら死ぬ んやというわけの分からん論にを立てます ですねとにかくここは敵中突破をするんだ と敵中突破してもう死ぬんだったら仕が ないとでところがまそうだとすると敵も びっくりしてあま追かけてこないんだろう とかいうことを信じようというんで自ら こう敵に突入していってでえさらについて いくとあの敵もですねまさっとこう引いて え弓を追いかけるだけやったとで結果弓に いられてえこうドタに押したりとかあ馬を 失ってこうされそうになるんだけども たまたま逃げてった馬にこうパッと 飛び乗った木村兵庫をですねさらに道下で 苦していた味方のえアタがあ味方のミノ誰 かはですねこう引き上げて無事に尼崎へ 逃げてきてで人屋を道場で過ごして京都へ 帰ったていうことが太兵器に書いてあるん ですねでこれはまたですねあのこの太兵 器資料をねご覧いただければいいと思い ますがちょっと私これ引用する時にあの 岩波書店の古典文学体験の方から引用した んですがそちらにはですねえルビも売って あるんですねえこれちょっとルビが入れ られなかったので呼びにくい字が一部あり ますけども 大体ねあのもう送りがな通り一部こう12 点レ点が入ってるぐらいですのでえま比較 的見やすい文献資料だと思いますので是非 またトライをしていただきたいと思うん ですけども一応なれとしてはこういう活線 がありましたよということなんですねで さてえ今回ご紹介してるこの無寄つ軍中場 もう1度思い起こしますとやっぱりその 最初にですねえ上人3人しと出てくるわけ ですねただあの小女の上ではですね常と いう時になってますけどもえそこに15に 三神をしてで神崎の西の橋詰ですからばえ 現尼崎市側ですねこちらで待機をして警護 してたら敵が船に乗って攻めをせれたなぜ かって言うと太平でいうその川の橋を 落としてるので船に乗って敵が攻めてくる わけですねでこれをまあ防いで戦ってで 夜明けになると今度はやはりですねあの 書いてある通りと国の為替を超えて鏡島 この鹿島が場所分からないですあのひっし たら鹿島じゃないかという意見もあるん ですけどもえっと場所からするとちょっと 鹿島は少し違うのかなっていう感じもし ますし鹿島は鹿島にはならないんではない かという風思いますこれ場所不明ですで 倉橋はあります豊中とま戸内との境いとこ ですねまそこを焼き払って攻めをせてきた とありますので太平器ではえっとトマとか からあこれあの焼いてたけどもまこれは 少しちょっとあの地理感が少しあまりよく 分かってない人間が書いた可能性もあると まあの実際の敵は三国からこうねえ川沿い に川沿い三国がを超えてえ黒橋を超えて 神崎の方に攻めてきたんだなということは これから推測できるわけです ねで最終的にまどうなったかていうまこの 時の戦いあの軍にによってはですねあの他 の群長場なんかを見ますと例えばそのこの 時の活線で外それを内人したとかあるいは あのどっかに傷を受けたとかあいうことを 書かれてる軍中長もあるんですけどこれは 単に活性に参加したということだけし書か れてないですけどもえとにかくムよ立は この苦戦でま北中技として生き残ってえ 最終的に日付けは変えてないですけども8 月中に軍中上を提出してま敵の味方の対象 であった佐々木高秀太平紀には佐々高秀は 出てきませんけれども見な佐ですけどもま いわば美浦さの主君にあたるうこれえ高秀 というのは後に系図を出しますけども 佐々木同の息子ですかねに当たる人物で 侍いところも染めてた人物ですのでまその 現地の疾患というよりは自分の所属してた 軍団の親分みたいな人に犯を得てるという 風に理解ができるいうわけですねで一方 この戦いではですねあのこの今回見つかっ たム面え寄つ軍中場以外にも森本元長と いう人の軍中場というのもありますえっと 宇の内閣文庫所蔵の北川森本門上というね 伊森本はの城を元長が申す軍中のことと いうですねでえ右猿年12月人長寺におい て云々っていうのこれはあの少し前の頃 からもう軍に参加したよって話があったと 2行目次にえ今月8月17日神崎御活線の 時においてえ中節をいたし総来とあとで こん時に戦いましたよとちゃんと働きまし たよとでこらの主催美浦次郎上門の城ムの 上はえご称にそがためああごのしとでこの 時たことは美浦次郎上も佐年がちゃんと見 てるから見ておられますよとなのでえ今後 の証拠とするために言上申し上げましたと いうことで8月25日に軍中場を提出をし ててこれうしですので一見しわんのはこれ 誰が一見したかってちょっと分からないん ですね残念ながらえただ内容的にはこの 年号も一致しますのでこの神裂この時の 公安にでの関崎活性の時に ま伊森本元永も北長方として参加したと いうことが分かりますでまたこの活線その ものについても具期というこれはあの当時 の奥の小江さん小江道ぐさんと いうこの駅の投資であった方のえ自筆原本 の日記が残ってます用明文庫所蔵で勝本も 出ておりま勝本によりますとえこのま京都 にいるわけですけども8月の17日え行員 正員不定ということで晴れたり曇ったりで 時々雨は降ったと南方京都接収に打いると 云々とま特長型省をとってみると南朝税の ことはもう一般的に南方とか言い方をし ますでえ自分たちが政党ですからそれに 敵対する人間を災い出す人間ですから強度 ですねえ方の奴らが攻接収に攻めてっ たってことをね云々ということで前文情報 として接してるわけですねで45台一戦の 後引きしりとま45台がえちょっと戦った けどもその後もう知りといてきたでえ官軍 ら官軍というのはこの場合自分たちのこと です北町軍のことです南朝軍でありません え神軍なお発行接しべきのよし夫婦ま一旦 は引いたけども 味方はまたえ戦うつもりだよっていう風な ことが分として聞こえてきましたよという ことです ねこれでま守護台一戦というのが美浦佐敏 の合戦の様子をま京都にいてるクさんがあ おの方がそのえ情報として噂として聞いた のはこに書いてますで18日になりますと え接京え引のよしその季節ありということ でやはりそのどうも太平器ではその後 しばらく設にとまってえいたようであり ますけれども京都の人間からしてみると やはりま電文情報なんで間違いの可能性は あるんですけどもえ一旦この南朝型は引い てったっていう風な情報は京都に伝わって たようですね結果的に京都までえ及ぶ危機 には感じられてなかったんでしょうね ということが一応 この太兵器あるいは他の軍もあ軍中場から あ区の日記にもですね出てくるわけですね でそのいった内容と今回の新たに発見され た軍中上内容まほぼほぼ内容としてそは ありませんのでえ途中申し上げました通り 大あの軍中上は神眼が結構問題になること が多いという中ではあ これはあのえ別に疑問上と見る必要ないの ではないかそれとあの実際現物と称号は なかなかできなかったんですけども佐々木 高秀の顔についてもえほぼこれでいけるの ではないかという風なあ理解もありますの でえ特に疑う必要ないのかなという風には 思っており ますでまあの関連でですねこれがあの現在 の神裂の様子ですねえこの裂の場所場所で 今から700年前に激戦があったとは なかなかね感じられないのかな雰囲気の これ神崎の石道路あの神崎のコンビさんの 石道路から え東の方向いてますだからこれあの見え てるのは山陽新幹線の航からですね神崎が こえ てでこれがその堤防から今度少し神崎川の 方神崎橋の方を向いた様子この右手が右手 に神崎がありますでこの橋があまあの南北 町時代の橋がどこにかかってたのか分から ないですけれどもまあの2体のとこにある とするとここに橋があってこの対岸に南朝 勢が攻めてきて北川に北町勢がいてるとで え両方こう退治してる時に北南朝勢はこう 婦人シト見せかけて上流へ行って三国から こうねえ攻めてくるというそういう活線 だったよということは分かるですねで太平 器によると繰り返しになりますけども小野 とかトマとかね川林まで攻めていったで それがあいわば攻めていって今度は神崎 までこう攻めてきたっていうルートなるん ですけどもおそらく この今回のムセよつ軍中上に書いてある 通りそれほどうえではなくってえ肉リガを 超えてえすぐこのまあクラ殿内の方を超え て神崎まで攻めてきたというところが実際 とこなんじゃないかなという感じはしない でもないです えこれが江戸時代の説名所ずに描かれてる 神崎の様子になりますご覧の通りここが あの神崎がですねでもう等々とした大河で 船がこう流れあの通ってますけどここに あのえ江戸時代には中国街道という大阪と 尼崎西宮を結ぶそれからえ街道から有馬の 方へ向かう街道のこの私がこにました江戸 時代には私があったんです ねで現在もこの道のここのスコのところに ですねえT次の突き当たりに道しべ同表が 立っておりますでえ北の方に行きますと ちょっと曲がったとこに有道の同表があっ たりもしますしえまこの道の突端のところ ま先ほど神崎あのコンピラさんの一トール はもう少し上手の方になるんですけも えっとこの棒を超えてえ神崎が沿いに 出れるようになってますけども江戸時代の 要素はこういう風な要素だったんです ねでえっと53公までこれがあの赤松市の 系図になりますえ赤松村エですねえ張の国 のま土合出身ま村上源二の一部と言われて ますけれどもえっとま息子がの即がですね え5代天皇の第え大王やったかなえ森吉新 の大宮森吉新王のま側近になったりもして えま五代を天皇型とま早くから気脈を続い てたということと尼崎に関して言いますと 大閣文助の 火年間の気象門の中に この助と佐っていう名前がですねえ現地の の大館とかその現地の役人としてこのね のすさの名前があって顔があるんですよね でこれはもう昔からこののすサノという出 てくる大学自文字に鎌倉末期に出てくる のすサノは赤松の松のりすさりであろうと いう風に考えられてますでただですねこの そこに据えれてる顔はあるんですけども その顔があ後にそのえどこやったかな 広峰神社やったかどっか姫路の方の門上に 出てくる顔とあまり一致しないではない かっていうのもあるので一概に言えないん ですけどもただあの比較的その江戸時代の その厚生の記録であるんですけどもあの 赤松のすは早い時期にこの設の国に深層し てた的なことはね書かれてたりもしますま そういったことをベースにして昔呼んだ 北方健造さんかなんかの小説かなんかでは あのドイはもう設で活躍してるなんていう ね小説があったりもするですけどもまいれ にしろその室町バが成立した後はこののす が切守護になってなくなった後はみのりが 切守護を継いでいきますで以後そのまま 継いでいければ良かったんですけれども 一旦佐々木震と依頼られたりまたえ戻っ たりもして最終的に説の守護は誰になっ てくかていうと細川が獲得をしてくとで 赤松の本家の方はえ即の方に行くわけです けども吉典えさらに三助の段階でいわゆる 画の辺でこの一等は没落をしてでえ最終的 にはこの吉正の子孫正典が最を果たしたり とかあるいは戦国時代にはあこの春日部県 ってあこれえっとのすは京都の非常家と いううちになるんですけどもえこの佐のは 春日家という春日家のこの松江が戦国時代 に赤松吉村という風に投手になったりもし ていくわけなんですけども前しとその子に は説とあまり関わりがなくてくるんですが あこののすつのの一等は節と比較的ゆりが あった人物なので現在でも尼崎地域でも その先祖張から出たという風につげられ てるオタクは結構あると思いますおそらく ここに繋がってくるんじゃないかなという 風に思っており ますでこちらがえあまり馴染みがないかく 分かりませんが佐々木市の警になりますえ 佐々木市のどの子供にま六角と教とま六角 と教と分れていくわけですねでえ六角の この宇の宇の松江があ最終的にこの織田 信長に抵抗して破れていく六角上帝という ねあれにつがっていくうなんですけども 一方この強国の方はあこの高明以降の強国 士はあま一時期北臣の安市に勢力奪われて しまいますけど結局え生き残ってえ金星 大名として残って共ケなんですけどもえ 室町代の初期にはこの高う芦川高内と 名乗りがたまたま一致してるんですけども 先同様とま教同様と言われてる人物があ 結構その北上型の重要人物としてねよく 歴史書なんかにも出てきますしあの画像と してはあの相対法体ですごく合体のいい形 形であの報復をきた絵姿で有名なんです けどもえ太平器なんかではいわゆるその 当時の 寄付を表すバサ大名ですねえ非常に派手な 服を着たりとか生な生活をするけども権威 を結構否定するとでも知られてますし爆の 重要人物にもなっていきますこの市があ 結構ですねあのこのむ面が参加してあのっ てた家人のただただ神社とも非常に関わり をどうも思っていたようですねであのの国 はが細川がこう閉めていくんですけれども この川軍のの北部一体は佐々市の勢力は 残っていたようでえただ神社文助なんか見 てきますとえ佐々木高内東洋が出した小 文助とかも結構出てきますでその中にです ね佐々堂を書き下しです何を書き下してる かっていうと他本土上量として当商内財務 並び妊婦のこと自社本条可能の地を言わず 言わず支配めむえ洗礼に任せ叩いとすべき の普段のこということでえたりの本道の上 量をちゃんとこうね あの支払うように出会いをしてるという ことですねでこれは誰にやってるかという と守護代として活躍をしていた美浦上本の 城あてになりますでこの命令を受けたえ 美浦上物は何をしたかというといわゆる 巡業場という文を出してますこれく本来 ですと守護代としての役割が出すもんなん ですこの時は多分守護ではなかったと思う んですけども場合によったらあのえ川部軍 のこの北部一体は切の国とはちょっと分割 されたあ文群守護としてえ佐々木市がおっ たという可能性もあるんでしょうけども美 市はえただの本土上量のことはえ恩 書き下し書の早くさる胸に任せて平均支配 せしめえ勝浦戦に任せえ里いすべきの上団 のこということで同日付けでえ本神両番時 どのというねえたの現地のえ多野現地の 満所だと思うんですけども宛に佐敏の名前 でえ文字を出してるとなのであの太平器で はあの美浦上門城じゃなくて西門城と出て くるんですけども実際は上門の城ですね この右と左っていうのはちょっとね なかなか読みがあの空心すると見にづらい ところもありましてえ何とも言えないん ですけども ねなので太平器とかに出てくるこの神裂 活性に関する人物というのはですね いろんな資料からも明らかになってます けどもえ今回そういった関連治療を含めて より具体的に同時代の資料でその要素が 要素が明らかになってのは今回の文字と いうことになってくると思いますでちなみ にそん時のこの時の神崎の合戦で焼かれた というのが上皇寺さんになりますでその 上皇寺につる江戸時代前期に作成されたえ 絵画作品上皇寺演技図この部分ですねえ 上皇寺の本土を焼けてる部分これがこの 神崎活線で焼かれたという設定で描かれ てる絵でありますまこの絵自身が江戸時代 前期のもんですから江戸時代前期の人が 当時の様子をまいえば え想像しながら書いてるところはあるん ですねだからあの文字演技ではあのジ皇司 さんあの常皇司さんが あ別の文字の演技も上皇寺さん伝ってまし てそちらと上皇寺が廃絶をしていくのは 一旦絶していくのは荒木村の氾濫の時に 焼かれたという書いてあるんですけども これはどうもですねえ美浦佐ミノルがん たらて名前も出てきますし南北長内乱の 様子をして描かれてるもになると思います でただ江戸時代の人は書いてますので大平 にあのよ上図の溶岩溶岩ね溶岩に北上型は こう酔ったと書いてあるんですねでそれを 多分知ってる人間がこの絵を書いてる可能 性があるななぜかって言と城光寺の北川に なんかこうねお城が書いてあるのねでこれ が旦のお城やということなんですけども これはひょっとしたらあくまで推測なん ですけども太平均に出てくる上皇寺の要害 っていうのを上皇寺そのものを上客と 問えるんじゃなくって常子にあったお城と いう風に取られた絵さんがなんかこういう 江戸時代の金星風のお城こに書いちゃった んちゃうかなという気がするんですねあの 場所的にも上皇寺ともし尼崎の城やったら ちょっと位置関係もなんか微妙ですしま そう考えた方がいいのかなとまどこまでね あのこの絵画に抱えてる内容が実をを反映 してるのかっていうとはなかなかねあの 書いた人に聞かなければ分からないところ もありますのでね何とも言えないんです けども1つの則とそういうことを考え られるんじゃないかとまちなみにこの演技 非常にね面白い演技でしてご覧いただけ ますかねあの今カーソルのあるとこ にここにあの観音さんが焼けてるどから 飛び出してあるんですよねでこれあの本来 は2服で展示会場言ますけどこの観音さん があの天字から中国で飛んでってで中国で 盗とあの盗賊に盗まれようなったところを 海に流されて日本へたどり着いてで空海に 見出されてお寺ができてよかったねが第1 服目で第2目でここでいきなり焼けるん ですね焼けてどうなったかて言と仏さんは 水飛び出しあるんですで水飛び出したやっ たら安全な安全なとこ行けばいいんです けども えっとま事前によるとその後海に流れて いったりとかで海に流流れていってえ今度 は津波にあってまた流されていったりで 最終的に魚民の網にかかってでえ宝塚とこ あるのを人々が見つけてでこれはどこの あの仏さんやって上皇寺の仏さんやとじゃ これはやっぱり回せないいかんて言って 法令を作ってえホテルに持ってくていう そういう壮大なストーリーの中の人言です けどもこの燃えるシーンが結構有名なので え山崎指示の頃から戦乱の市では必ずここ 使ってますただまこれにはねさっき言った ようにこの江戸時代風のおしがるという 意味ではちょっとねなかなかねあの理解に くるしむところもある絵ではあるんです けどねでちなみにこれは現在の条項師 ですえちなみにこちらはですねあの今回お 借りしましたあ平文助の中のえ高野諸なの 当て行い場というやつの移しになりますで これは常和4年という年の無よつにこの 鎌倉ダニ村を与えますよっていうね文これ 非常にあのえっと顔はですねきっちりと 書かれてましてえっとこちらの文字は やっぱりねあの先ほどの軍中場よりも もっとねあの大事な門上特に領地を与える という文なのでえうを作る時も非常に厳密 に作ったんではないかっていう風に言われ てるよう ですからこちらは芦川吉明があ分な元年に こうたごけ認中当てに文興の省として当て を行うっていう風に出した文章これ2つ あの関数になってましてこの文助そのもの の存在はあんまり学会にはさほど知られて なくってえ表圏内にある文助でうの文助な んですけども全く疑問女っていうわけでは ない今回の消防も出てくるないわばあ歴史 的な価値に非常高い文助ではありながら 例えば兵庫剣士の資兵にもこれは取り 取り上げられていないえところそののま 先代のご親戚の方でえ研究者の方が いらっしゃってご自身があま宝塚にお 住まいの時に顧問所紹介されたりとかいう ことで一部の方には存在を知られててえ そのさる公明な先生も実物をご覧なったり とかしてでえ亀岡京都亀岡の資料官の方に はの文助出品されたことはあるようですで 今回お聞きしますとそれ以外に外におかし したことはあ地元の稲川町さんでの催し 以外にはないですという話でしたんでえ 今回ではそう意味ではえ本当久々特には崎 で初公開の文助になってまいります最後な んですけれどもえっと新発見の軍中上の 歴史的価値ですけども長々申し上げました けどもえ疑問所の可能性もある中上であり ますけども内容的には太平器あ太兵器その ものがねええ全く捜索の可能性もあるん ですけど太兵器の内容とほぼ一致するし他 の軍中上の内容とも一致するまた内容的に も太平器とは違ってえむしろ現実の活性の 状況に近いような内容もある等々考えます と散られてた事実をさらにより詳しく 伝える貴重な歴史資料ではないかという ことは言えるかと思いますで昼返って考え ますと尼崎の南北町内乱というのは色々 分かってることは多いんですけども まだまだあ新たに分かることもあるんだな というのは今回の資料の発見によってえ 通説に感じられましたやはり今回展覧会で も対応します太兵器これは非常に便利で 分かりやすくあの内容が非常に分かり やすくてえとっつきやすくて人々が歴史を 関心持するのは非常にいいいコンテンツだ と思いますで古来そうやってえ歴史を勉強 した方も多いと思いますけども明治になっ てえ近代的な歴史学を発達していくに及ん でえこの他兵器には市学には全く駅がない んじゃないかていう意見もあって否定さ れることもあったんですけどももちろん 内容としてはまるまる信用できないけども こういった顧問所なんかを組み合わせる ことによってより豊かな歴史が分かって いくのではなかろうかということでえこれ からもうんどんどん勉強していきたいなと いう風に思ってる次第でございますえ最後 までご成長いただきましてありがとう ございました [拍手]
令和6年5月8日の水曜歴史講座の様子です。
当館学芸員の楞野一裕氏の講演をお楽しみください。
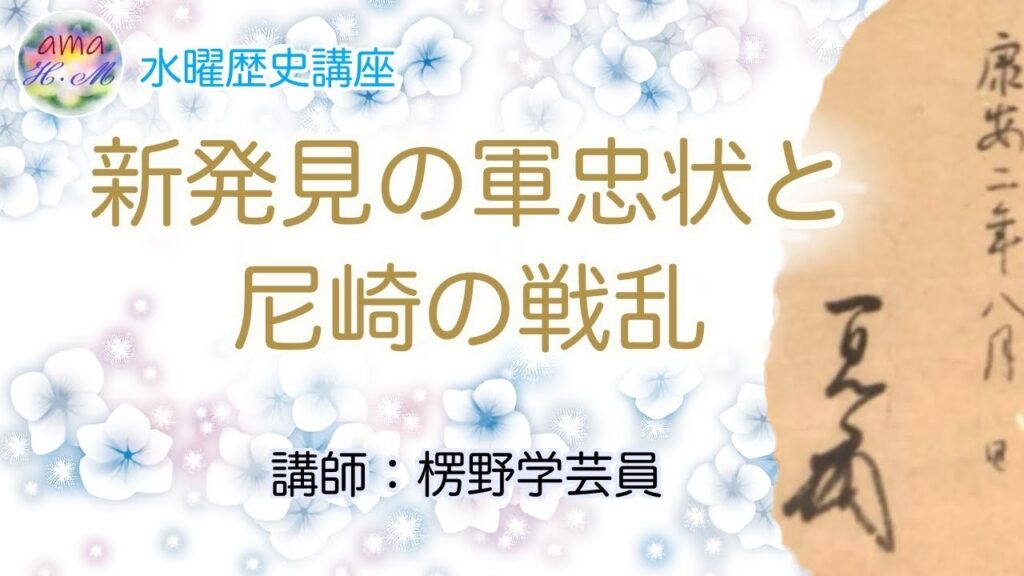
Add A Comment
