視聴者様のコメントに返事をする 追って沙汰する!-Vol.28‐
おって沙汰するの [音楽] コーナーえこのコーナーは皆様から頂いた コメントにお返事をしたり感想を言ったり まワワチとするコーナーなんですがなんか ねコメントでねおって沙汰するっていうの が上から目線でやなので登録解除しますっ ていう方がいてでそうでなんかあのまこれ ねあの最近ありがたいことに登録者様が すごく伸びてきてあのおそらくおするのね えどうしてこういう風に決まったのかをご 存知ない方もいらっしゃると思うので一応 ご説明しておきますとあの別に我々がおっ て沙汰するうんやってやろうじゃねえか 教えてやるぜとかって言って決めたわけで はないのですあの皆様からのコメントにお 返事をねするコーナーを作る時にまどう いうタイトルがいいかなコーナー名何が いいかなって募集してまあの目安箱がいい んじゃないかとかQ&A校内がいいんじゃ ないかとか色々いだいた中でおって沙汰 するっていうのをねあの言っていたい たうん方があっていやこれはちょっと偉 そうだしま上から目線すぎるしまでも 面白いから入れとくかって感じで アンケートに入れたわけなんですねでそれ で視聴者の皆様にまどれにしたらコーナー メいいでしょうかっていうアンケートを 取ったらなんとぶっち切りで追ってさがに なってしまったのでもうなんかあの我々と してはあのEU離脱が決まった時の イギリス人みたいな話ですよねえなんか 面白で反対とかって言って離脱とか言った けどえ本当に離脱しちゃうのみたいな感じ でってさするはなかろとか思って入れて たらそれがもう選ばれてしまったので ええって感じだったんですがまでもあの皆 様の総意ということね一応このおって沙汰 するというねちょっとま偉そうな名前で このコーナーをさせていただいているわけ なんですがということなのであの我々が へんと思ってやってるわけではございませ んのでできれば登録の方を持ていただけ ありがたいのですがあの本当にあの いやいやもうそんなメもございませんって 感じでやっておりますのでよしお願いいし ますちょっと偉そうだなってのはずっと心 のみこにはあったんであのまこういうご 意見もあるたびにご説明をしていこうかな と思っておりますはいえということでね 今日のおさタスなんですがえっと1発目が ね結構面白くてえニャーメロぐしろさんの えコメントでありがとうございます ありがとうございますこれあのすロバート の秋山さんの助のことをね書いたコメント
なんですけど私のでは秋山さんはクカル君 と呼ばれてい ますで光る君にかけてクカルキいいねと 思ってなんか今後うちのチャンネルでは あのロバートの秋山さんの実をクカル君と 読みましょうかねなかなかこれはナイスな ネーミングと思ってねうんで実際実という のはイケメンだしできる男だしねヒル君と 並ぶぐらいねいい男だったわけなので黒い か どうでしょうか皆様も賛成だったら賛成と コメントいただいたら今後はクカルになる かもしれません次ですねこれはねあの何人 かあの結構コメントをいただいてあの直秀 がいるじゃないですか山岳で真広ちゃんと あの道長のね間を取り持ってるあの人が墓 ではないのかね墓じゃありませんかとか あるいはあの藤原の康助なんじゃありませ んかとかっていうコメントをたくさんいい たんですねうんうんうんあの墓て覚えて ますなんか聞いたことあんのそうな以前に ほら日本で最初1番最初に説服したのは誰 っていう話をした時に袴だれっていうのが そうなんじゃないかっていう話をしたあの 人なんですねおこれがちょうどその平安 時代のこの時代の人で混じ物語なんかには キったが大きくて腕力も強くて足も早くて でま腕利きで頭も良かったのうんでまに 並びなき人物だったなんていう風にま盗賊 なんだけどかっこいい盗賊すごい盗賊とし て書かれている人物で実はねこの1番最初 に説服した人っていうのは藤原の安って いう人なんですけどただ後にこの藤原の 康助っていうのもまあまあ若干悪党なんで ねこの悪党の藤原の康助で説服した藤原の 康助とこの混じ物語なんかで有名な墓 っっていうね貴族的な盗賊がこうごちゃに なっちゃっ て呼ばれるようになるんですよね2人が 同一人物みたいになんかなっちゃって本当 は違うんだよ本当は違う人なんだけど なんか同じような人になっちゃってなんか 後にま藤原の安は墓だみたいになっちゃっ たので一応ま別人なんですけれども まあまあどっちも盗賊ででしかもあの藤原 の安っていうのはま説服したっていうこと でね割と有名な人なので実際に藤原の安は 実在してるしでま墓はちょっと物語的だ けど族みたいな感じでかっこいのでこのは これをモデルにしたんじゃないかというま 説をまコメントなんかでもねあのいいたん でああなるほどなとそれはあるかもって 思いましたね実際現時点でもなんかこう 貴族っぽいなんかねその腕っぷしも強いし 足も早いし頭もいいしっていう盗賊として
描かれてるしだからひょっとしたら直日で 説服するかもよ えねだからが服してなくなるみたいなこと があったらもう間違いなくねこうモデルは 藤原の安だって墓康助なんじゃないかって 言えるかと思うのでまそそれなんかも ちょっとね頭に置きながらあの今後見てく と面白いかもしれないですねこれも我々 忘れそうですよね難話か先だったら言って たっけだうん聞いたことあるぞぐらいは あるかもしれけどうん覚えそれこそここに 紙張ってこうこうこの辺にこうずっと止め といたらどうでしょうかは 秀は墓 墓まわかんないけどねわかんないけどま なんかコメントでたくさんいただいてあ それはあるかもなと思って実際この時代の 盗賊としては墓っていうのは非常に有名な 人物なのでねそれがモデルっていうのは あるかもしれまねで次ですね虎猫さん コメントありがとうございました ありがとうございますえっと大代理の位置 はなぜ変わったのだろうかっていうねあの これあのこれ大代理という代理の位置が 変わって今その5書っていうのがある場所 がいわゆるあの平安鏡の当初大代理があっ てその中に代理があったっていう位置じゃ なくて随分東の方に移動してるんですよっ ていうその動画のまご質問みたいな感じな んですけど一応ねあの代理がね村上天皇の 時にあの家事で焼けてしまったんですよね うんでそれであの代理時点が焼けてしまっ たらじゃあ他のとこに住むしかないって いうので里代理って言ってその別の場所で この代理が再建さうんまで天皇がお住まい になるみたいなことが行われてでそれでね ちょうど今ドラマでやっている道長とかの 時代に代理が焼ける火災がね頻発するん ですよ多分放火だと思うんですけどねうん でそれでそのいわゆる一条天皇なんかも そのいわゆる元々の代理より里代りで 暮らしてる時の方が多かったんじゃない かって言われるぐらいもう火災再建火災 再建で里代っていうのをの暮らしててで しかも里代がいつも同じ場所じゃなくて やっぱりあ移動するんですよねその時その 時ででそれでまだから今の五所ってのも 元々は里代理だった場所でそれをねあの 江戸時代に松田定信あの例の義者を書いて いただいたあの言ったら多くで田沼つの 失客させそれで自分も失客しちゃってその 後一生懸命義者ので書いてくれたあの人ね なんでこういう義者とかの本書いたかて 言うと実は江戸時代にあの代理をね再建し てるんですよでその時にやっぱ彼が担当で
再建してるからこうのいうんだったり いろんなものをその時に調べてそれをま後 にまとめてるっていうまそういう繋がりも あったりするんでねでなので今の御所って いうのはま江戸時代に松田サブあの いわゆる白王っていうのが再建した場所に 立ってる建物ですよってことなんですねま こうこういう風に歴史というのはいろんな とこで繋がってくるんで面白いんですよね うん今あのほらあの代理の中見学できる じゃないですか春と秋だとあの公開してる 日があるしあと申し込んだらいつでもあの 見んうんうんなのでその申し込んで見た時 にこれが松田コが作ったやつかと思って見 ていただけるとより楽しいんじゃないかと 思いますはいで次ですねえマンボさん コメントありがとうございますえ義者です が江戸時代の頃も使われていたのでしょう か亡くなったのはいつ頃でしょうかという ねえご質問なんですけれどもあのま元々ね 義者っていうのは貴族のステータスの 乗り物で別に乗り心地がいいわけ あの移動するのにすい早いわけでもない 不便な飲み物なわけですよでなのでえっと ね鎌倉時代以降にその区以外の物資特にま 将軍ですね将軍家は義者の使用が認められ はしたんですけどまでもあんまりのだから もうステータスとしては乗るけど移動とし てわやっぱ乗りたいぜって乗り物じゃない んであんまり乗られてはいなくてでしかも 大人のラ以降にね室町の大人のラ以降に なってくるともうクも者には乗らなくな ちゃうです腰に乗るようになるんですよで ま1つには室町時代の大のラこお金が なくなってきてねクたちもねその維持費 ちゅうのがねまあ言ったら出せなくなった からだろうしあとやっぱりその維持費かけ てまで便利かていうと便利じゃないから そういう意味ではま利便性を取ればもう こっちの方が早いしねってなったんじゃ ないかなっていうのでま一応江戸時代には そのギシというのはまほぼなくなっていて ま室町鬼以降にははまクたちでもえ義者に はあんまり乗らなくて腰を使うようになっ てたんですよっていうことですねうんはい えじゃあ牛さんたちはどこ行ったんやろ 食べられたんかな うんまあの別に使わなければさその言う たらギ用にもの京都に持ってこないだけで 元々その濃厚用だったりとかあのそういう のでね牛は貴重なので別にねあのあの荷物 運ぶとかいうのはやってるんでねなので まあまあその食べられはしなかったと思い あのま室町は食べたかもしれないけどま 江戸時代になるともうねそういうなんか肉
食べるのがちょっとねあのやっぱ仏教的に 良くないみたいなだからまあなので江戸 時代の牛さんたちは食べられなかったとは 思います濃厚牛になってたんじゃないかな と思いますけどねあれかな農家の人がさ この牛実は藤原のなんとかさんの列車引い てたんだぜとかって自慢したりしてたかな ちょっとあったかもしれないねそのまだ から鎌倉鎌倉ぐらいだとさこの牛は将軍の のね義者を引いてた牛なんでって大事にし てね祭ってたりとかもあったかもしれない ですよね本当かどうかわかんないけど言っ たもんがちだからねそんなのはねはいあっ たかもしんないですねそれはねうんはいと いうことでえっと佐藤さんですねコメント ありがとうございます平安時代にも何かお 間はあったのでしょうかご存知でしたら 教えてくださいねえ平安時代にもおじいは あったのかございましたそれもたくさん ございます 今でもなんかおまじないとかってなんか するまあのちっちゃい子が転んだら痛いの 痛いの飛んでけとかったするねたけどうん 昔さあの霊者見たらさ親指隠せとかって言 なかったうんあったあった親の死目に会え ないからそうそうそうそうとかあなんか今 もおまじって結構ね色々あるのかなと思い ますけども平安時代にもねそんなおまじ ないが山ほあってあのまずね足が釣った時 にねその釣ったところをさすりながらうん キキュウリて唱えるんですよ何それ キリキリ食べ物のキュウリそうそうあの キュウリ自体はね6世紀にもう中国から 入ってきてるんでま一応薬用として日本に あったのはあったんでま薬だったんです けどあの多分ねこれはそのそっちのキウリ というよりま薬用の薬だキウリっていう 言葉はあってでそれでしかもあの多分お給 吸える急を吸えろっていうのと薬だった キリっていうのでキリキリだからあの薬の キリで治るみたいなおえるみたいなところ から来たんじゃないのかなっていう風に 言われてますねうん うーやってみよう今度なん聞くかどうかは わかんないけどやってみてください キュウリキュリあとなんかそれとなんか似 た感じなのとだとあのくしゃみをすると なんか早にするって当時思われてたらしく てであのちょっと時代は下がるけど つれづれ草なんかにはそのいわゆるこの くめくめって言ってくみをした時にそれを 言うと早人にしなくてうんみたいなその 呪文があってでそれでその自分がねその 育てたあの目のをやってたねあのうばさん が若様が今もくみしてると怖いからって
言うんであの若様のためにずっとくみくみ くみてそのなんかくみ封じのね呪文を唱え 続けてるみたいな話があったのでなんで くしゃみをした時もなんか呪文唱える みたいなのはあったみたいですねなんで 海外とかだったらゴッドブレスユかな なんか神のなんかあるよねそうあるある あるなんあるよねそれがやっぱ代もあった みたいですねやっぱりなんかほらクション て言とそっから魂飛び出しそうっていう イメジがやっぱりあるからさなんかしない とっていううんそれはなんか多分世の東西 を問わずあるんだろうねうんへそんなのも あるしあとねあの今でもその京都とか東京 のこの辺でもあのよく古い家なんかをやっ てるんですけど家の片隅にあの語弊をこの 神をこう切ったこう神さのこうこういうの のうんうん うんうんずっとあって部屋時代の場合は あのなんか木の札みたいなのをさしてで こう疫病が退散するようにとか病気になら ないようにみたいな感じでこのぬさをね 語弊を立てるっていうのがあったらしい です ねであのこれがさあのちょっと時代下が るって鎌倉時代になるとあの民将来の子孫 って書いた札家の入り口に張 るっていうのがあってこれあのどういう話 が元になったか知っ てるうん庶民将来っていう人があの言うた ね昔そのあのなんて言うかな疫病の神様 みたいな疫病を広める神様みたいなのが やってきてそうそうでそれでその人が言っ たらそうちょっとなんかこう貧しいね老人 の過去してやってきたらその庶民将来って いう人があそんな気の毒に行ってて家に 止めてご飯食べさせたりとかしてくれたん で大事にもてなしてくれたんでその神様が あの今後お前は庶民将来のこうしし孫孫 庶民将来の子孫ですって書いて家の前に 貼っといたらあの優しくしてくれた庶民 将来の子孫だからって言って自分は疫病を ねそこの家は伝染させないように避けて 取ってあげるから書いとけよって言われて でそれでこう代々庶民将来の子孫っていう のを書いてっていうのがあって今でもあの 例の三重県のあの鹿島かなんかのあの辺り 行くとね島のとこに都民将来の子孫って 書いた普段本当に家の前に貼ってるところ があるんで私見に行ったことがあるんです けどそうだからあの今でもこれは生きて いるあの鎌倉時代からずっと続いてるもの なんですねあそう三重県とかあっちの方 ってあのお正月とかにさやる何スメナ みたいなのをずっとやってて忘れてんのか
なと思ってたら真ん中に正門笑うもんて 書いてそれをずっと張ってるところが多い んだけどあれもなんかそういう関係があん のそうそうなん結構だからあのそこの正文 のところに庶民将来の子孫って書いてる 部分もあってだから常にその薬業神という か病気のね疫病の神様が入ってこないよう に守っとくっていうような意味合いであの 家の前に飾ってるらしいんでなのでねそれ も忘れてると思ってこれ書いてる人は本当 に子孫なのいやいやいやいやだからもう もうなんかそれやったらなら言ったでやっ てるいるよねあかりやもう今や今やぜどれ が子孫とかてまあまあほら子孫の隣の人も 子孫みたいなもんじゃしあの日本のね言っ たらまあまあまお隣さんも一緒でいいじゃ ないすかていうねそういう日本のね心 優しい風習ですよそれでま広まってる みたいなところをあるみたいだけどねまで もほらあの島のあの三重のあのねその島の 辺りだとま言ったら全部子孫ちゃ子孫 だろうからさまそんなにあの厳密に言うと 違うかもしれないけど大はそうなんじゃな いっていうことでオッケーなんじゃない ですか適当やその辺がまあなんか日本風で いいかなって感じそういうのうんうんあ あとね金家パパのそのお父さんであるモス なんていう人がいるんですけど藤原のモス この人なんかもやっぱおまじないで助かっ たっていうエピソードがあってあの夜中に ね百期夜業って言ってあのいろんな鬼とか 物のけが京都ではあわの辻とかっていうね あのあの辺りに出るっていうねま言ったら 百業うんの言ったらあのいっぱい出てくる 百業銀座みたいなとこがあるんですよ京都 にでそこを通りかかったらやっぱり百業が 出てきたんでああって言うんでこの損傷 だらにというねま言ったらそのま呪文です よねそれを唱えて助かったっていうこの 損傷だらにっていうのがやっぱり白き野形 よけに聞くっていうのはなんか常に言われ ててあの後にまひろちゃんのあの紫式部の 旦那になるご先祖様にあたる藤原の高富 っていう人がいるんですけどこの人なんか も100百期業に出会ったんだけどこう衣 にね損傷だらにっていうのがこう縫いつけ てあったんで無事だったとかっ言われてる みたいに割と100期業の時には損傷だら にみたいな感じでなんか本当にうんお腹が 痛くなったらセロがみたいな感じで聞くて いうので言われてたみたいですあそれで だらっていうのなんかそうそういやそれは どうかわかんないけどねまでも損傷だに から来てるのかもね何でも聞くよみたいな 感じでねひょっとなんなはだだなんダラス
てのがある黒い眼薬でね多分そう総省ダニ とかから来てるのかもしれない例言新た かってことでね来てるのかま私もしないよ しないそのそダラニスを飲んだことはある けどその由来まで調べたことがないんで ひょっとしたらねうん違うかもしれない けど村長誰にがもとかもしんないですよね うんあとはねあのなんかこれこれ結構ね あの長いんだけど雷がなった時にやっぱ雷 っていうのはま音量の怒りだったりとか天 の怒りだったりとかそういうよう意味も あるんでなんか聖も雷大嫌いだったらしい んですけどその雷がなった時にうちらが ほらおへそ取られないように昔おへそ隠し たみたいな感じで平安時代の場合はなんか ね東に向かって赤田南に向かってリテ西に 向かって菅田で北に向かってそだにって 唱えるとまあ言ったら雷に当たらないって いう風に言われて覚えれそうで覚えられ ないんで覚えられないでにいてらしいね壁 とか柱にそうすと雷がなった時でも大丈夫 みたいな感じだったらしいですね ふうまあなんかねこれも本当一部で一例で ねもう色々平判時代って割と今から思うと さあの言ったらもうその名神山ほどだから そういうおまじないとかっていうのが言っ たらもう山のようにあった時代なんでね もう語り出せば切りがないぐらい色々あっ たんですよねなんかいい張り紙だらけやっ たんやろなそうね色々ねいろんなもんが あったと思うよねまでも今も京都のさ なんか古いお家とかに行くとさもう大所 いっぱいいろんなもん張ってあるからね なんか山のひりのなんとかとかさあと なんかあの冷え山の現神さんのなんかの あの役のなんとかとか更新さんのなんとか ていっぱいあるからねまあんまり変わら ないのかなっていう気はしますけどね私の 友達は一緒にこうホテルとかなんか旅行で 泊まりに行くと絵の裏を絶対見てた何か札 が張ってないかどうかて ええって怖いからあったら嫌じゃんうん あったら怖いからつって確認してた確かに なんかなんかそれこそさあの何なんかあの 悪霊退散とか入ってやったらやだよねその 部屋止まれたくないよねいやなのでま私 あんまり探さない方ですねあんまりったと 怖いからでも友達はやたら探してたでも 会ったことはなかったからよかっ た良かったあったら怖いわちょっと面白い けどうんドキドキする けどはいで次がちえみのマンマさんかなえ コメントありがとうございますあの諸新王 って33か所巡礼を対抗した火山法とえ ドイツ人物ですか清らかな気持ちで巡礼を
していたのでなんか心がざわつくというか ショックですドイツ人物ならばあんな はちゃめちゃな人がどうして仏道に励む ようになったのか知りたいですっていうね ままあの一応あの あの33年の礼復興したのはあのあの はちゃめちゃ火山天皇でございます火山法 でございますまでもでもねそのなんかこう ショックって言うんだけどはちゃめちゃな その行動と極楽上土を強く願う気持ちって いうのは別に同時にあるわけでしょ1人の 人間の中にね別にそんなもう全てが正常 でっていうようなそんななんか成人主 みたいな人だけがねそういうことやるわけ じゃなくてむしろ煩悩まみれだからこそ 救われたいっていうねまそういう思いも 強くなってそういうことをや るっていうのはまあまあよくあることで あのそれこそ俺診断商人とかも自分はね すごい煩悩まみれだからそれを救うため にって言うんでねあのあ物に一生懸命 すがるんだってあの白場してらっしゃる 白女っていうか告白してらっしゃるような ぐらいやっぱま煩悩強いのが人間で強けれ ば強いほど救われるために仏にすがりた いっていうのは別に矛盾はしてないわけな んですよねでしかもね火山天皇がそういう その仏 あの楽願う気持ちが強くなったのはあの さん最愛のである子さんがなくなってから なんですねでこれねもこう聞くと泣かせる よ本当にねあの火山天皇はちゃめちゃて いうけどね私は大好きなんだけどあのなぜ ならね部屋当時って部屋のあの頃って妊娠 中とか出産が原因でなくなった女性は成仏 できないって考えられてたんですよなので 天からしたらさんっていうのは妊娠中に なくなってしまったじゃあこんなに最愛の 人なのに彼女は極楽上土に行けないのか 成仏できないのかなんて哀れなんだなんと か彼女を成仏させてあげたい幸せにせめて 極楽上土にまでねなんか行かせてあげたい だからそれがなんとかできないのかって 言ってそのものすごくその信仰に のめり込んで修行するんですよなのでこの いわゆる火山天皇のそういう極楽情動を 願う気持ち仏道に励む気持ちていうのはよ さんうんへの愛から走ってるんですよおま それを後にね金家パパにつけ込まれちゃっ てね色々まそのいろんな事件になるんです けどもまでも言ったらその火山天皇はま はちゃめちゃな部分もあった人だけれども やっぱよし子さんへの愛が深かった強かっ たがゆえにより彼女を救いたい気持ちが 仏道にそののめり込ませたんだっていうの
はね言っておきたいと思いますなので別に 33元巡礼をなんかもやんとせずにああ そんなあの言った妻への強い愛から一生 懸命修行した人が復興してくれたんで ありがたいなと思って巡っていただければ いいんじゃないかと思いますということで ちみのマンマさんあのこれからはそういう なんか火山店のあ人間らしくて素敵と思っ て巡礼していただければなと思います最近 火山店の鍵薄い からえでも今回さそのなんかよし子の なんかねこう具合悪い時にあのハニの カナダさんがさ私を天皇にの紹介して くださいとかって言って言ってなんか 生臭いこと言ってるのに比べてさもう言っ たらあのすっぽんポンのままですよね先も つけずに慌ててきて大丈夫かって手を握る っってねあの本来そういう病気の人とかさ そういうところに天皇という正常波が 近づいちゃいけないのにそれでもそれを 押してでも見うっていう本当になんか やっぱりそういう天皇のそのお仕事とか 今日そういうの無視してでも近づいて握り たいて思うぐらいの愛を感うん すいいいシーンだったから短かったけど 今回ねすごい火山のやっぱりよさんが好き だったんだなっていうのが分かるしでま ちょっと破交差もこうねむき出しの曲げと か病人のところに行っちゃうみたいな ところで出てたしあのすごく両方の面が出 ていていいシーンだったなと思いました けどねすぽの姿焼きはショックやった けどそう ねこれはに71さんなのかなはいコメント ありがとうございます5せの舞お衣装は それぞれのお家が準備したのでしょうか いうねまあの例えばまひろちゃんの場合 だったらね謝大臣がね言ったら身代わり にって言てお願いしたんで左大臣機が用意 したのかっていう風なご質問なんですけど あのそれはもう舞姫を出す家で用意しまし たなので舞姫4人だとま4つの家から出る んでそれぞれの家が準備するんですねで しかもま今回ドラマではねささすがにそこ までできなかったんですけど舞姫ってさ あの5説の前の時って実際3回踊るんです よねあの言ったらえっと長大の試みと午前 の試みとそれから問明りの設営っていうね でその時にあの全部3回とも衣装を変える んですええ全部別のもの着るんです水本の 高平っていうのが最期っていうのでま言っ たらその輸送個をね書いてるのがあってで そのそこで書かれているその時の後世で本 の高のやつがどう来たかっていうのは えっと長大の試み1回目のねリハーサルの
の時には赤色の折りものカゴを着てで地 その言わやてすり出した毛をつけたいうで 次の午前の試みの時には青色キジのカゴと それから酢裾ごもっていうのをつけて菊人 っていうのはねなんか今のモスグリーン みたいなちょっとめったに来ちゃいけな いっていうねあのなかなか切れない色なん ですけどそのそういうこう色をしたカゴも 着てであのえス裾ごっていうのはあのス っていうのはまちょっと紫っぽい色です裾 だからグラデーションでだんだん下の方が 濃くなっていくようなすごいおしゃれなも をつけてるっていう感じのものででそれで 豊明の設置の時にはラの青なりのカゴとで それからやっぱスを目覚めのもっていうの をつけててだからえっとラっていうのは ちょっとこう荒い荒い目のなんて言うのか なその織り物の総称なんででそれでこう その青とりだからそのやっぱり愛染でね すり出したってあの前言ったみたいなね そういうので着ててでそれでツだから言っ たやっぱ紫色っぽいでえっと目染めって いうのはねあの今でいう絞り染めです なんかこう星みたいにこう白い点々が紫の 中にこう散りばめられてるみたいなもを つけてたっていう風になってるんでなので ななかなかねあのお金もかかるしでしかも 毎年毎年だからあの舞姫を出すっていうの は非常に名誉なことでもあるしお金ないと 出せないっていうねあの言ったらもう一等 の貴族じゃないとなかなか出せないみたい なところだったのでだから中級貴族たち なんかはやっぱ上の貴族たちがあの声かけ てお前のどこから真姫出してくれって言っ たらその上の方から当然ねそういうものは 用意してあげるからみたいな感じで実際 現地物語なんかでもヒカル源二がね言っ たらメのトのところのあの娘出せって言っ た時に全部ヒカル源二が準備するっていう のがあってでしかもそのいわゆる舞姫の 衣装だけじゃなくてその舞姫にお月の 召し使いの女房とかさあの目の笑わていう 女の子とかさそういうのの衣装なんかも 全部言ったらそのあの姫出うんが準備して でしかも毎回毎回ねやっぱその今年はどう やってやろうかみたいな感じで思考を凝ら すっていうのがこう話題性もあるわけなん でみんなが注目してるわけなんですよで 実際紫式部日記なんかではあのその年藤原 の実成それから藤原の金高そから藤原の 中清それから高の成東って4人がねま舞姫 出したんですけどそれがどういう風な舞姫 出したかみたいなの感想を紫式部が書い てるところがあってでそれによると藤原の さなりが出した舞姫はなんかんモダで一味
違うわって書いてあるしでその藤原の金高 のところはそのお月のね目の笑わたちって いうのがなんかこうきちんと水黒いしてい てなんかひびて微笑ましいみたいなから みんながちょっとねあのすごいこうさこっ たきっちりした格好してたんで逆になんか 堅苦しい感じがひなびてるなってそれが 面白いなみたいな感じで書いてるしで藤原 の中清はなんかね海沿いの女房たちの身長 を揃えたらしいんですよだからもう シンクロナイズのスミングじゃないけどみ そのぐらででなんかそれが雅で奥ゆかしい とかねであと高の成はあの舞姫のね海沿い の人が女房があの2式のカゴムを着てるん だけどその2式だからその銀子かなんかで 追ってるもんだからそこが夜に踊るからね その夜の闇の中でもこうキラキラしてそこ のところだけが光って珍しくて非常に立派 だったみたいなことを書いているのでなの で舞姫出すのは姫の衣装だけじゃなくで その女房だったりお月の目のだったりの 衣装も大事だしその主今年はどういうので 行くぜみたいなのも大事だったんですよ 紅白歌合戦の小林幸子さんの衣装のようだ ねそうそうそうそうだからあの本当もう 毎年今年は何で行くみたいな感じでみんな がこうそれで競い合ってどんどんどんどん 派手になってったらしいんですねそれが 決まるじゃないで3回服ま着替えて着物 着替えるんだけどそのもはもちろん次の年 とかには切れなかったりするよねなでもっ てそれを普段着使いもできないわけ使って いうかあのま中級のその舞姫なんかだっ たらそれをさ言ったらあの褒美みたいな 感じでね頂だいてでそれで家で着るとかは あったかまもちろん清掃で全部切 るってことはないけどね下のカゴロモを なんかの時に着るとかそうあるいはなんか こう仕立て直して切るとかそういうのは あったかもしれないですねうんあ良かった もう1回切りだったらもうったバラバラな のバラバラなのだからそのどこの家が今年 は1番だったとかねそんなシジやのに みんな好きかってな書こして大丈夫あそう だからその豊明かりの設への1番上のね 言ったおもは一緒なんだけどその下の モードだからも物ね模様とかなんかも すごい凝っててうんでそのそれがどんなの か今年は何が来るかみたいな感じでみんな すごい楽しみにして見てたっていうねそう いう感じなんですよねかぶることないの かしら色がかぶったわとか れでなんかそうするとその色のその染具合 のうまいところとかさその言ったらその色 のグラデーションで上下つつけるとかそう
いうのもあったんじゃないですかね当時 あの言ったらあの布そうそういう着物の あの衣装っていうのはみんな上級貴族に なると自分地で作らせるんですよねま天皇 はもちろんその代代理の中にそういう専門 の部署があるんだけどだから自分とこで どういう布を折らせてでそ糸なんかの染も ね色なんかもだからさっきから素って言っ たら大体紫って言ってるんだけど実はスっ て言われる色も100種類200種類と 濃いとか薄いとかちょっと赤身があるとか ないとかで全部違うんですよだからこの素 はうちではこういうのでちょっとね秘伝で こんな風ななんかよそにはない色で染める ぞみたいなところもあれば今年の素は ちょっとこうこういう感じの思考で行こう ぜみたいなのもあるっていう非常にだから ね色なんかも当時の人たち色彩感覚すごい から全く一緒みたいな今みたいな科学繊維 でね全部被るっていうよりは若干違って うん食べろからそれを楽しむみたいな ところもあったのかもしれないですけどね だから何々家の染はやっぱり腕がいいよね 綺麗だよねとかいうそういう表も出てき たりするわけです よ当時の衣装を見られへんのねま当時その まま残ってるのなんかもちょっとはねある けど布っていうのはやっぱ劣化が激しいの とあと色がやっぱり退職して当時たの天然 の線量だからね退職して当時のままの色 っていうのがやっぱなかなか難しいわから ないねあの再現しようとしてね京都なんか の染物屋さんがやってるのを見たりするん でこういうのなあの結構思ってる以上に 鮮やかだったりするのでねそういうの なんかは見られるんですけど当時そのまま のっていうのはやっぱちょっとあのやっぱ もう色がくんだりしちゃって残ってない からね布自体がやっぱり残ってなかったり もするんでたまたまあってもさお寺とかで こうこういう巾着にねこう作り替えたのが 残ってるとかはあってももうでもそれは だいぶもう色がね落ちちゃったり釣れ ちゃったりもしてるから当時と同じって わけにはいかるですけどねうん鮮やかだっ たんだろうなうんでもまあその当時のその 女性っていうのはあの染め物と縫い物って いうのはあの言ったら花嫁修行じゃない けど上級の貴族の娘さんであればあるほど できないといけないセンスが問われる みたいな染めっていうのはすごいそういう 大事な女性の1番センスが問われる部分の 言ったらあの1つのねあのなんスキルだっ たわけうん うんということではい今日今日のおさるは
この辺でお開きにしたいと思いますえなん だっ けこれにて久しぶりだったで忘れました これにて一見 落着楽しかったでもなんかこうすごくこう 平の鮮やかなねていうのを感じ取れたから うんもっとこうカラフルな感じして見る ように しようさあじゃあ久々にラットちゃんの 今日のピアスは何のコーナーもやりたいと 思い ますねこの頃ね桐さんもお忙しいという ことで1ヶ月に1度ぐらいのペースになり ましもうストックはどんどんと増えており ます今回も新作でございますそして今回も またまたうちの旦那様がおこれに今かけて いるのかどうかわかりませんが探しをして おりますでナンナ様が買ってくくれた今回 はタキ ピーああピーナッツとピーナッツおお ピーナッツとかきの種なんか唐辛子か なんかかハネるとなんかかと思ったら そそうかカキピーとピーナッツピーナッツ なんだピーピーそれ食べられるもう1個の 方がそ食べられるのこれは食べられない 残念ながら疲れた食べようと思っけどもう 1個 がおかきと ピーナッツそれも食べられないんだそう こちのねすごい出が良くて美しそうすごい 食べられそうでしょうんな乗り美味しそう ね美味しそうめっちゃ食べられ そうそれを買ってくれましたのでまた今回 も旦那様の目線がもう変わってきてるよね この頃やたらともうピアスばかりを購入し てくれるというありがたいことにありです 今年の分はだんだんこれで十分いけそうな のでこれからもやっていきたいと思います のでえなとちゃんのなんか今日のネイルが さエナジードリンクみたいなんだけどそう なのこれね本当はねま2月ということで あのバレンタインのチョコにのイメージで やったんですけどちょっとカラフルにし すぎたら私の中でもエナジードリンクの ようだなんかなんかエナジードリンクにし てるのと思って 違うんですよこれはちゃんとねこう チョコレートのこうタレ具合みたいなのを 出したつもりが色をねついつい私としては カラフルにしてしまったのでねエナジー ドリン全にエナジードリンク完全に エナジードリンクだなと思ってそっちに なりましたなんか違うと思ったらそっちに なりましたなるほどなので今月のネイルと 今日のピアスでし
[音楽] [笑い] た [音楽] お
#光る君へ #平安時代 #解説
※概要
いつも沢山のコメントありがとうございます。
今回の内容は 02:15 実資は「黒光る君」? 03:08 直秀は袴垂保輔? 06:16 内裏の位置は何故変わった? 08:40 牛車はいつまで使われていた? 11:13 平安時代のおまじない 21:04 三十三ケ所巡礼を再興したのってホントに花山天皇? 25:26 五節の舞の衣装について となっています。
2024年、NHK大河ドラマ「光る君へ」解説動画です。
メンバーシップやってます。(月額490円)
https://www.youtube.com/@kashimashi_rekishi_ch/membership
毎月、長編動画1本、短編動画1本配信
特典はバッジ、メンバーのみが使える絵文字などです♪
X(旧Twitter)で配信情報とか配信前のネタをフライングでつぶやいてます。
Tweets by rGDfU0KgzH2ankI
▼エンディング曲
お祭り太鼓 (feat. マニーラ) / Stardom Sound
(P) & (C) Star Music Entertainment Inc.
▼使用効果音
「効果音ラボ」
https://soundeffect-lab.info/
「DOVA-SYNDROME」
https://dova-s.jp/
▼使用画像
「Wikipedia」
https://ja.wikipedia.org/wiki/
Webニュース各サイト
▼使用動画
「MotionElements」
https://www.motionelements.com/ja/
※素材提供ありがとうございます!
▼お問い合わせ(☆を@に変えてください)
tonreki.ch☆gmail.com

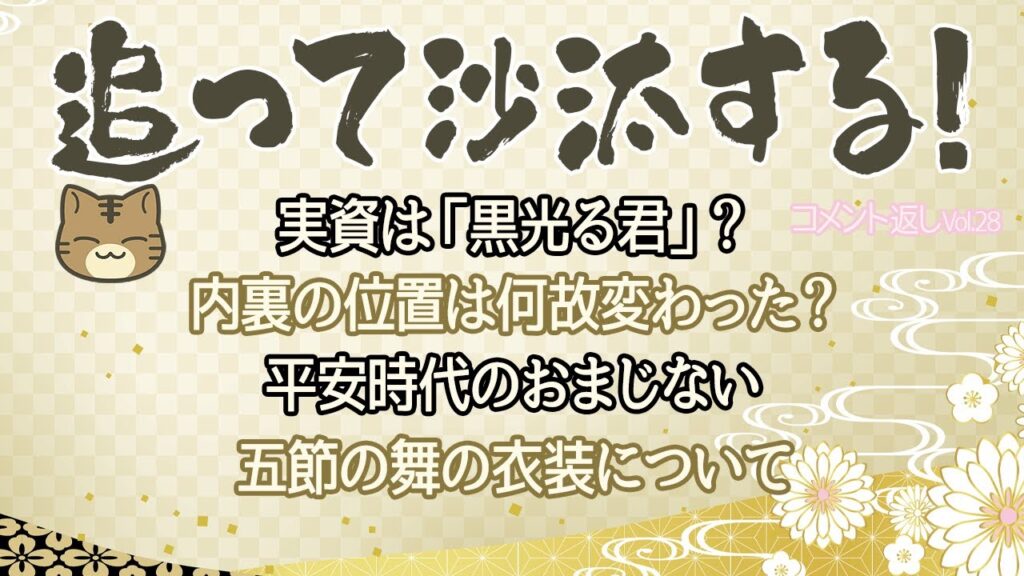
49件のコメント
ラットちゃんのピアス、旦那さん、かけてる!のですね。期待しています!
『く~さんの純粋な瞳…』キラキラしていましたねぇ。
五節の舞姫の衣装の話、源氏物語や日記にも衣装の細かな描写がたくさんあって、すごく興味があります。
岩手県奥州市黒石寺の蘇民祭、最後の祭で、テレビでも中継していました。千年以上も続いていたんですね。すごいです。
またまた、楽しくて、勉強になりました❤
こんにちは、初コメよろしくお願いします❣️
どなたかもコメントされてましたが、
蘇民将来子孫也 のお札、祇園祭の長刀鉾のちまきに付いてますね😊
ウチでは毎年、玄関の上に飾ってます。
追って沙汰する〜
が
いつも
追って "さとふる"
に聞こえて
他のCM画像が脳内に浮かぶ
のは私だけ?😅
黒光る君 良いですねぇ 素晴らしい❤
オニキスみたいで、出来る男を彷彿とさせてカッコイイ🤗
それとは別に色鮮やかさを思い起こさせる、蘇芳などなどの綺麗な言葉が出て来て楽しかったです
ラットさんの旦那様は一体どこでピアスを購入しているのでしょう?
今日のピアス欲しい‼️』と思いました
いつも楽しく拝見しております。
ずっと気になっていた事があり、ご教授賜りたく存じます。
半陰陽(両性具有)について、古くは天照大神や徳九代将軍家重がそうであったのでは?と言われていますが、神として崇められたり化け物として扱われたりと時代に翻弄されて来た者たちとして現代も息を潜めながら存在していると思っています。
野村萬斎さんの主演された安倍晴明でも化け物として描かれていました。
私は佛大の教授から授業で聞きましたが、龍谷大の史学部出身者は知りませんでした。
ご存知であればご教授頂き度何卒宜しくお願い致します。m(_ _)m
黒光る君…賛成でーす😂
やけに顔黒いなぁって思ってました〜
本日もお話とても楽しく参考になりました。ありがとうございます。
追って沙汰する~ いいと思います!
蘇民将来子孫也の護符は祇園祭の粽にも貼られてます。
花山天皇の仏道修行は忯子さまのためだったんですか。泣かせる・・・😢
五節の舞の装束が、4人それぞれ家の趣向を凝らしたもの、というのはびっくりでした。神事だけど、楽しみなイベントでもあったんですね。そして家の権勢を誇る、勢力争い・・・・戦よりいいと思います。
色彩、源氏物語絵巻の復元模写も澄んだとても美しい色で、磨き上げられた美、ですね♥
京都御所は 通年見学出来るようになりましたよ。申し込みなしで、当日行っても見学できます。(入場無料です。私も一度行きました。)月曜日が休みで、月曜が祝日の時は 翌日が休みになります。ただ 開場の時間は 時期によって違ったり、行事などで休みになる時もありますので、「京都御所 見学」などと検索して、調べてから行って下さい。
アンミカさんの感性は平安時代からあったのね!すごいなぁ
「追って沙汰するのコーナー」は他にないセンスで大好きです❤
独りごとのように「追って沙汰するのコーナー」とつぶやき、
きりゅうさんの口調を真似してる自分がいます。
タイトル名の件ですが、アンケートの時から知っています。私も追って沙汰するが良いと思っていたので、決まった時には手を叩いて喜びました。上から目線なんてちっとも思いませんでした。
学生が親しいゼミの先生と雑談しながら歴史の知識を深めていってるような楽しい時間を過ごしています。
「きりゅうさーん 7話! 御簾がミスってる!」
『光る君へ』のオープニング曲が流れるたびに、アート・オブ・ノイズの『ロビンソン・クルーソー』を思い出すのは私だけでしょうか(冝保愛子さんの番組のエンディング曲です)。毎回、懐かしい気持ちになります。
狂言で「くっさめ、くっさめ」って表現してますね😊
今回も御沙汰を賜り恐悦至極に存じます…などと悪ノリするくらいに楽しんでおりますので、「追って沙汰する」で続けて下されば有難く思います。
くしゃみ、諸説の一つとしてくしゃみの勢いで出来た隙に悪霊が憑くから厄除けに「糞食め」と言った説を聞いたことが有ります。東西問わず、くしゃみは危険という事でしょうか。面白いですね。
黒光る君
ナイスですね❤(笑)
植物園に行ったらちょうど梅林を特別公開してました。いろんな品種の梅があり見ていたら「五節の舞」という紅梅がありました。紅色の大きな花びらで、思わず「おぉっ」と声が出てしまいました。何でも江戸時代から生まれた品種だそうですが、名前の由来を知りたいですね。牡丹にも「五節の舞」があるそうですが、牡丹の読みはゴセツノマイ、梅はゴセチノマイというのが面白いです。
ウチは毎年、伊勢の方からしめ飾りを取り寄せているので「蘇民将来」や「笑門」の木札は玄関に飾ってありますよ。
まひろが彰子を産むのかなっていう予想をしていますね・・・まひろの母を第一話で殺してしまうとんでも脚本だから・・・
明石の上みたいになるのかな・・・
私が思いつくような脚本にするのかな・・・楽しみです。
くーさんの発言、ほんっと!いつもオモロイ😂。追って沙汰するの回、すごく勉強になります。
追って沙汰するのコーナー待ってました。安心してドラマとして楽しくなってきましたね。倉本先生が公平な方で実資への信頼が脚本にも反映されているのがわかります。その実資を黒光りの君ですか。面白いけれど、それ以上でもない。ごめんなさい。
良くそれは実用的ではない言われますが、平安時代と今の感覚を比べても?十二単衣が良い例。
五節の舞を踊る人は10歳くらい、高階業遠の子供と紫式部の子供が結婚、散楽の座頭の名前は輔保。
実資に黒光る君は良いネーミングですね。私はあえて髭黒大将と呼んでいますが。
うちの近所の信濃国分寺では毎年1月7日の八日堂縁日で、「長者大福蘇民将来子孫人也」と書かれたお守りが頒布されます。
この辺の家ではそれを玄関に置くことが多いです。
変な話をしてよろしいでしょうか。今更ながら、先日「どうする家康」の一向一揆の話を見ていて、大坂の陣の時、家康が南無阿弥陀仏を書き連ねていたのは、空誓上人との話に感じ入ったからなんだなと思い当たりました。見返してみると、気付くことがありますよね。
いつも楽しく拝聴しております。もし、きりゅう先生がどこかの予備校講師として、日本史や古文漢文を教えてくれたら、教室は超満員で立ち見がでるでしょうね!
自分が高校生だった頃に授業を聞いていたら、もう少しいい大学に受かったかも…
いつも動画面白くて大好きです!
追って沙汰するコーナーも毎回楽しみにしています!
光る君へも、歴史物だから結末はだいたい知ってるはずなのに毎週毎週「これからどうなるの!?」「もう史実とかどうでもいいから道長とまひろちゃん幸せになって😭」と思いながら楽しんでいます。
その熱い思いをいつかかしましのお三方と語れたらな〜と夢見ています笑
なのでオンラインファンミーティングとかいつかいかがでしょうか?😊
もしよければご検討くださいませ🙏
あと質問なのですが、くーさんとラットさんのお仕事を教えてください(絵描きさんとのことですが…)
今回花山天皇がおいたわしかったです😢
ドラマではまったく喪の描写がなかったのですが、平安の時代、実際にはどのようなお見送りをしていたんでしょうか。
追って沙汰する〜ひゅうひゅうひゅう〜って始まり大好きです❤
地元で昔から続いている文化に「詐欺じゃん」と言われ少し悲しい気持ちになりました。
黒光る君 大賛成‼️
こんばんは。😊😮😊😮
直秀のモデルは「ラブパック」(大和和紀先生作)の
"疾風"かと思っていましたw
幼き日の出会いなど、何某かの影響を受けている可能性があるのかも…
柿ピーのピアスいいですね~♪ 観ながらお腹すきました😋 次は何か黒光りするピアスをお願いします😅
私、追って沙汰する大好きです!名前決まってからますます大好き!!何回も見直して勉強しちゃうくらい大好きなので。たった一人の言うこと、気にしないでくださーい💦
なんで裸にまでなるの?と思っていたら、あの怪我を見せるためだったのか!
黒光る君……ネーミングセンス良すぎです😂
黒光る君、賛成!
「黒光る君」ナイスです✨
毎日アップされているか確認して楽しみにしております。
ところで宮中などで働いている女性達もお給料(?)をもらっていたのですか?
父親が官職に就いていればダブルインカムで裕福な感じなのでしょうか?
紫式部さんももらっていたのかな?
皆様のコメントが面白くて深いので感嘆しきりです😂
かしましの皆様の解答や分析も面白いのです。😊
平安時代と十二単衣大好きなので五節の舞の衣装のお話スゴく楽しかったです❤そういえば京都御所は数年前から通年公開されてます。月曜日と行事のとき以外は入れま〜す。来月左近の桜が咲く頃にこちらで楽しく学んで行ってきます😊
今の御所の建物は、松平定信が建立したものではなく、幕末も幕末に建てられたものだったのではないでしょうか?
何時も拝聴させて頂いています。
御三方のやり取りが面白くて良いですよね!そんで持って勉強になるし楽しいですよ!ら で!
追って沙汰するのコーナーですが、変えるのもありだと思います。
家康さんの時に決まったので!合ってると思うけど平安時代のことに追って沙汰するは、ちと違う気がします。例えばきりゅうさんのサロンのコーナーとか!サンガクのコーナーとか!おじゃる丸のコーナーなど平安時代にまつわるものに変えても良いかと思います。変えなくても良いとも思います。一度みなさんにアンケートを取られたらどうですか?
ご検討を!
さっき、途中までしか読んでいなかった大河ドラマのガイドブックを読み終えて、ショックを受けているところです。
ラットさんとく~さんが、「そこ教えてほしい!」ってところをズバリ質問してくださるので、本当に勉強になります☺️
早口で知識が飛び出る。なんて頭のいい、そして回転の速い方なのでしょう!
桓武天皇の百済のご実家と、平清盛のお母様のご実家は同じルーツでしょうか?『蘇民子孫』騒動から当時の似た現象に、後々、桓武平氏として台頭し日本を震撼させた『六波羅家』が出て来ますが、これは相当残忍な一族で平四郎はサイコパスだったと、五木寛之さんの小説には六波羅童の六波羅王子が渾名とあるみたいですが、藤原氏も源氏もとんでもない窮地に追いやられた陰に、藤原と源氏がバチバチってさせた工作員的漁夫の利を得た黒幕的存在がいたのでは?これは今の日本の現状にオーバーラップするような、ちょっと現代風な分析なのですが、とすると、豊臣秀吉の立身出世の原動力も、方や、藤原道長にとって紫式部が描く源氏の源氏物語は嫌じゃ無かったのでは?微妙なお話ですが、五木寛之さんの書いた小説では、平四郎の母は船の中の慰安婦のような生き様の表現で、平清盛の子であるような噂がありとすみたいな…史実と違う事は小説にも大いにあるとは思いますが、調べて書いてあると感じますし、そうなると朝鮮半島からの人々の船がルーツかもと…源氏は天皇の子孫で藤原と血のつながりは濃いですからね。源平合戦で平氏と源氏が戦っています。平氏は桓武天皇から勢力を伸ばした氏族であるなら、是非、この辺りの闇を教えてください。2024/2/23 8:13
いつも為になるお話をありがとうございます。
きりゅう先生をよく「きゅうり先生」と空目してしまうので、足がつった時は私は「きりゅうきりゅう」とおまじない唱えようと思います。